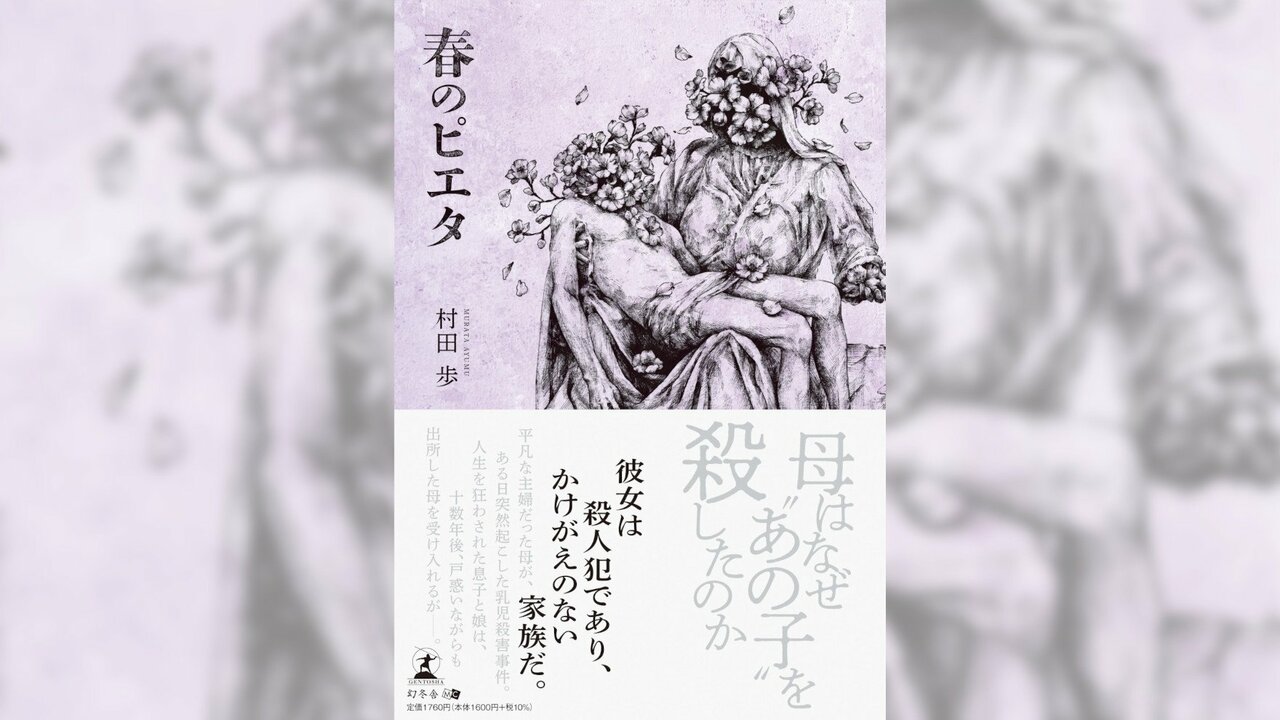優子 ―夏―
ただ救われたのは、最初に、まあ優子ちゃん、と言ったときの明るさを、美津子さんの声が失っていないことだった。もしかしたら美津子さんの中では、おにいちゃんのことはとうに整理がついているのかもしれない、とそのときのあたしは思った。
「ユニ2(ドゥ)というお店よ。銀座の七丁目、並木通りのビルの五階。たしか一階はテーラーになっていたわ。えーっと、ドヴステーラーだったかな……」
ドブス……あたしは笑ってはいけないところで思わず吹き出した。でも銀座に店を構えているくらいだから有名なお店に違いない。貧乏人の無知の笑いだと、吹き出した直後に自己嫌悪に陥った。なんて優しいのだろう、美津子さんはあたしに付き合ってすこしだけいっしょに笑ってくれた。
「お店は七時始まりだけど、八時くらいまでお客さんは来ないそうだから、その間に電話してみるといいと思うわ。佳香の源氏名はセリナっていうの」
「え? 源氏?」
「お店での名前よ。電話番号は……ああ、去年の手帳を見ないとわからない……そうだ、優子ちゃん。もしよろしかったら、お昼ご飯でもいっしょにいかが? 私の勤め先は新宿だから、近くまで来てもらうことになるけれど、美味しいランチをご馳走するわ。優子ちゃんはまだ学生さんなのかな? お昼の一時間くらい、だいじょうぶよね」
「はい、行きます、行きます」わたしは即答した。
会う約束をして電話を切った後、なんの迷いもなく、聖はお義母さんに預けよう、中学のクラス会だと言って、と決めた。今思えば、ウィークデイの昼間にクラス会というのはあり得ない話だが、そこまで考えがまわらなかった。
あたしの中には、おにいちゃんのことはちょっと脇に置いといて、美津子さんという女性に会ってみたい、という強い思いがあった。つまり、佳香さんを訪ねようと思うといろいろな困難が頭に浮かんでくるのは、あまり気が進まないからなのだろう。あたしはおにいちゃんの家出をそれほど切羽詰った問題としては考えていないのだ。
しかし、それは当然と言えば当然だ。十分に生活能力を持った二十六歳の男が実家を出たからといって、いったい誰が心配するだろう。妹のあたしくらいだ。