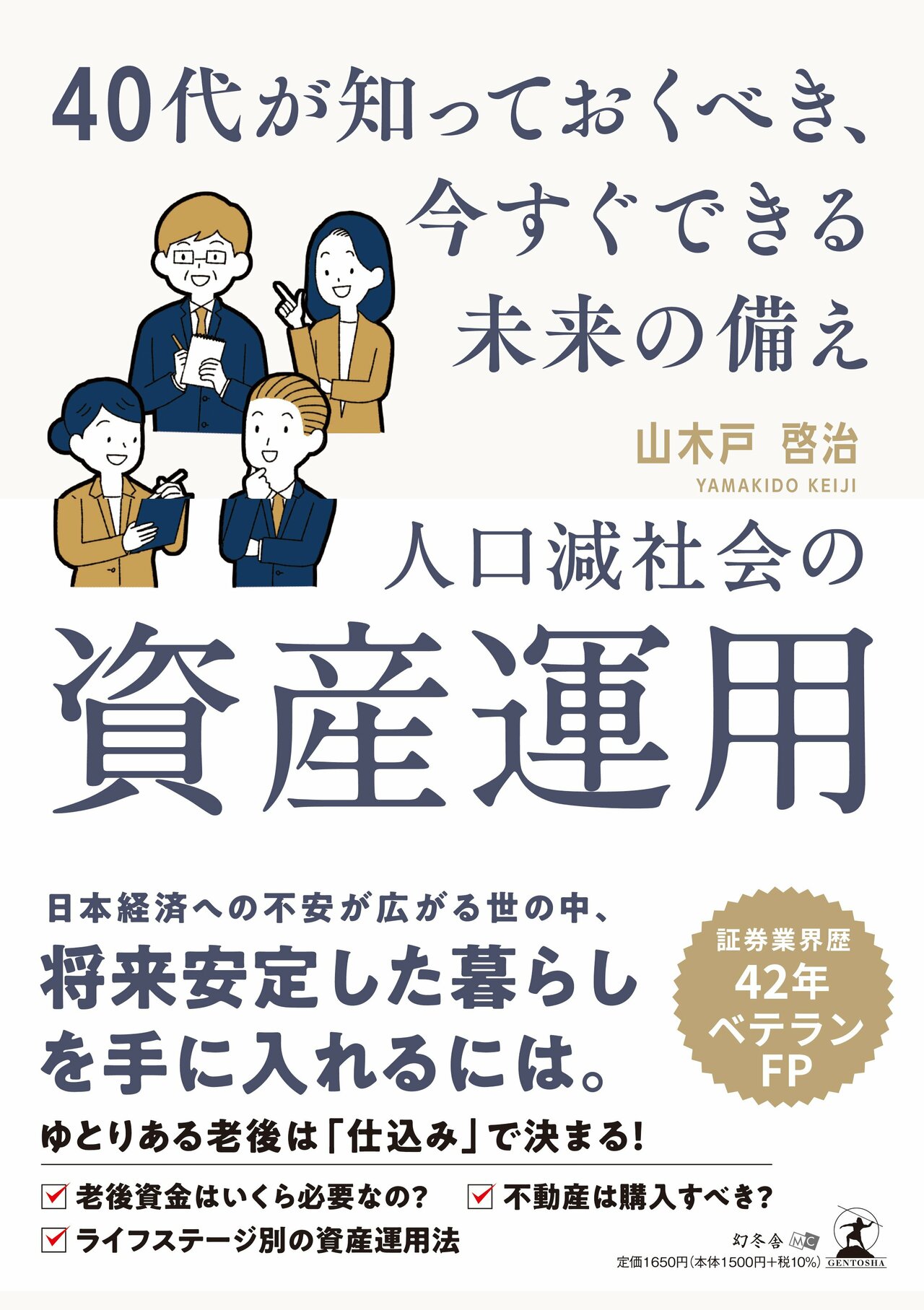(B) 一定の経過年数を経た後の、物件売却時の手取り額の割引現在価値注3
(C) 住宅賃貸費用総額の割引現在価値
●賃貸料 ●礼金・敷金(敷金は契約終了後返還)
●契約更新料 ●共益費(マンションの場合)
●借家人賠償責任保険特約を含む火災保険料
(出典)著者作成
あくまで、購入した住宅地の地価が、値下がりするか、値上がりするかで、損・得が発生するということです他の条件が一定であるとして、住宅費を考えると、一般論として購入と賃貸ではどちらが得か、損かという考え方は成り立ちません。
5 郊外型ニュータウンのケースに注意
持ち家取得を考える際に把握すべき問題があります。開発された時期にはもてはやされた、最寄り駅からの距離が遠い郊外型ニュータウンのケースです。
開発から50年経った郊外型のニュータウンでは、施設の老朽化や住民の高齢化が顕著です。首都圏のかつてのニュータウンが、人口減と高齢化が同時に進み、超高齢社会の最前線となっています。
一時期に開発され、一斉に均質な住民が入居したことから、一転して過疎化が懸念されるケースが見受けられるので注意が必要です。
過疎化の主な要因は、郊外に建設された当時に入居したニュータウンの住民の子供世代が、域外へ流出してしまったことにあります。
郊外へマイホームを購入した世代が、一斉に高齢化を迎えていますので、大都市の周縁部といえども人口減少が進むと予想できます。
高齢化の波が都市近郊にせまりつつあることから、以前には人気エリアであった大都市圏近郊でも、過疎化は現実のものとなっています。高齢になり入浴など日常生活のすべてで介護が必要な段階でも、自宅暮らしを続ける場合もあります。
一方、加齢に伴う心身の衰弱に合わせて、高齢者住宅や介護施設への入居も選択肢になります。有料老人ホーム等の入居金づくりのために、持ち家を売却する場合も想定されます。
持ち家を金融資産化する場合のことも想定し、購入と賃貸にかかわる問題を含めて検討すべきです。将来、金融資産化することを念頭に置いて、購入を検討する宅地の20年後はどのような変貌を遂げているのかを想定すべきです。
注1 国土交通省 不動産鑑定評価基準 Ⅳ 収益還元法p .27 ~ 31
(https://www.mlit.go.jp/common/001043585.pdf)
注2 マンションは管理費・修繕積立金を見積もる
注3 1981年建築基準法改正以降に建築確認された住宅の場合
【前回の記事を読む】「高齢化、あるいは人口減少が止まらない限り住宅価額は下がり続ける」 持ち家はリスク資産と考える…