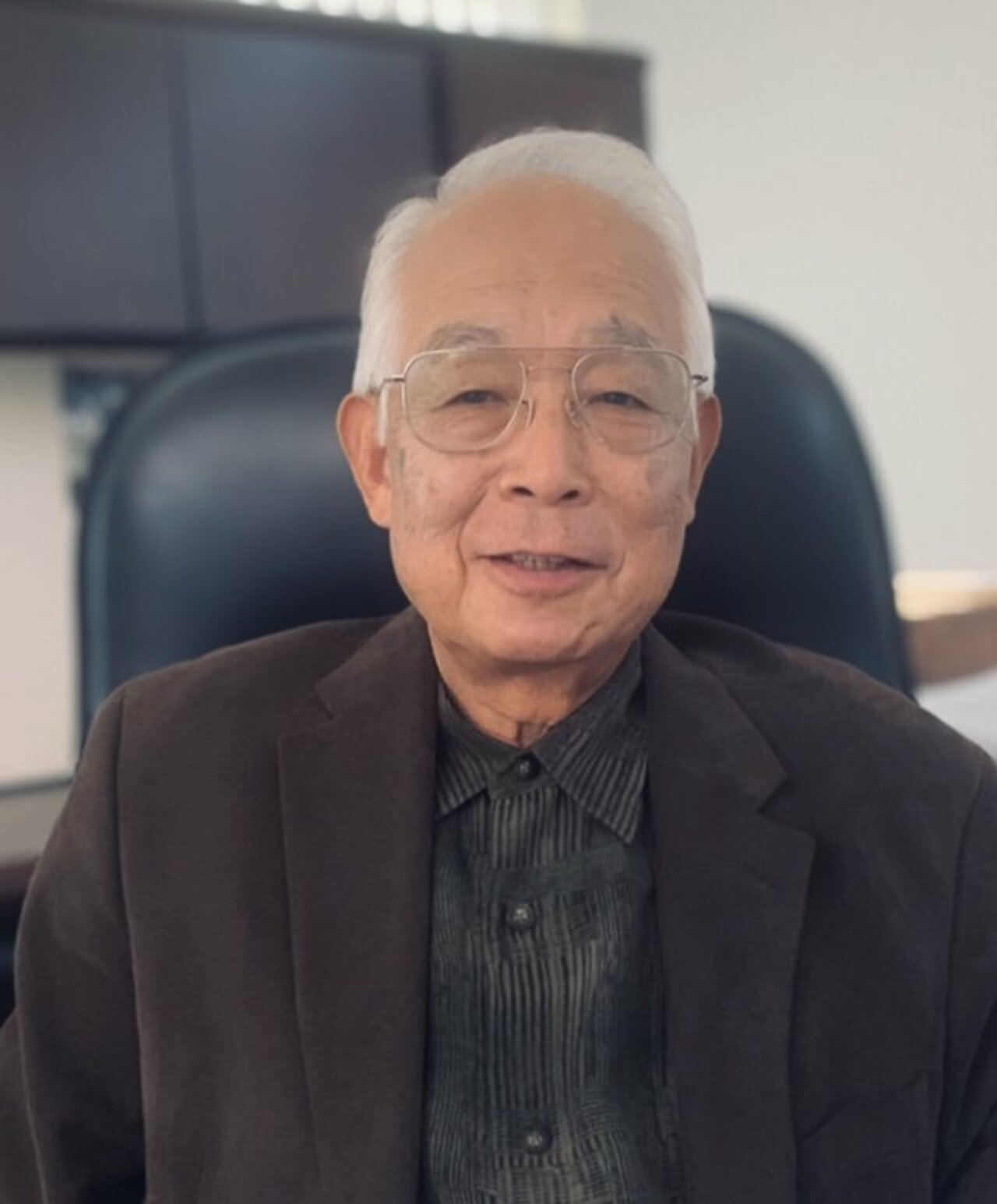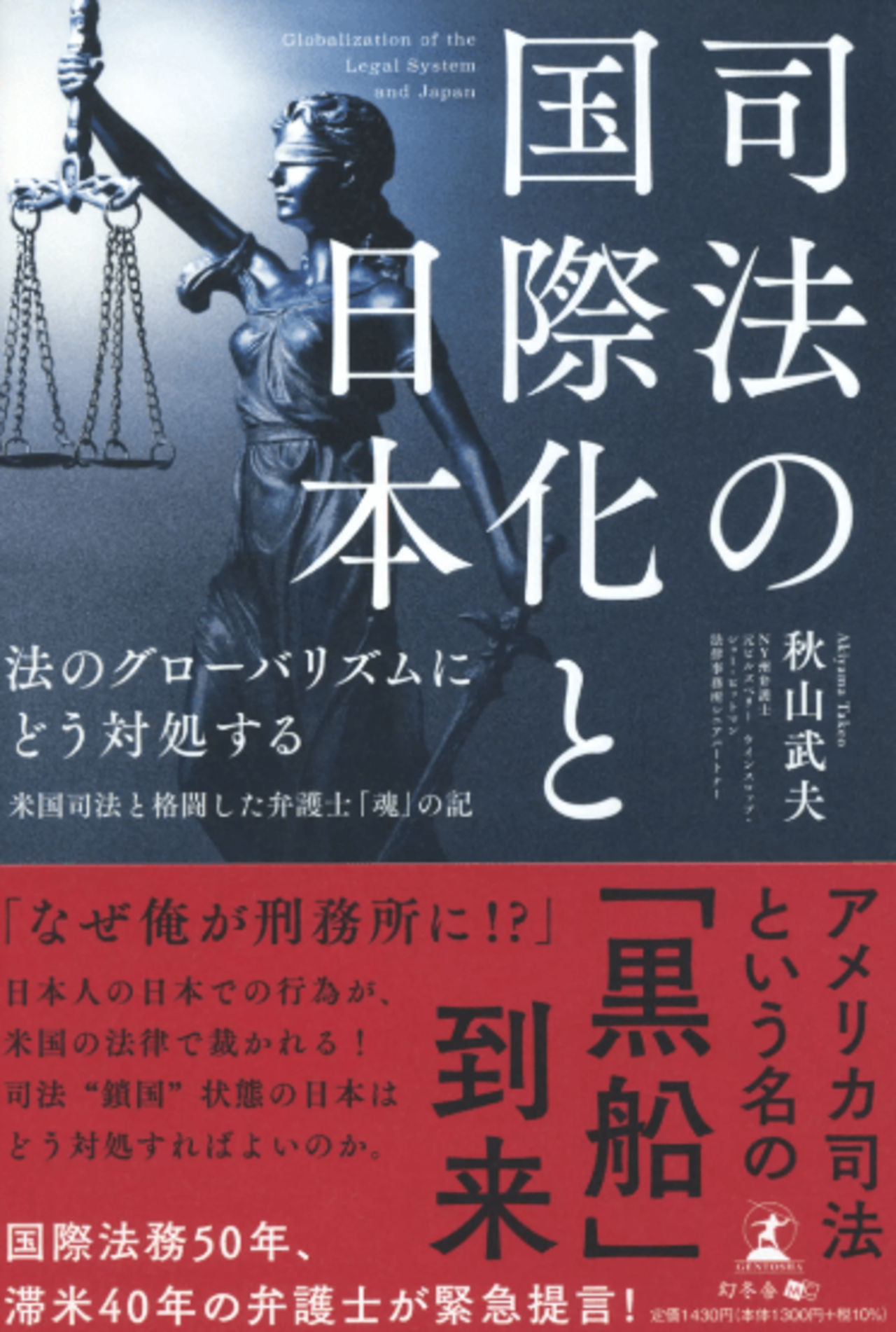察するに降格という従業員にとって不利益を与えるのであれば、せめて給与はそのままにしておこう、といった日本的温情があったのかもしれません。降格をしたうえに給与を下げれば従業員からの反発が必至で、訴訟にまで発展するかもしれないと危惧したのかもしれません。
パフォーマンスに問題がある社員に対し、とりあえず成績は「Good」にしておくといったことは日系企業ではよくあることです。
しかしながら実際に訴訟になった場合、「この社員のパフォーマンスが悪いので解雇した」という日系企業の立場は、成績が「Good」であるとの書面での人事考課と矛盾することになります。陪審がどちらを信用するか、答えは明らかです。
その場限りで問題を回避しようとしたあまり、きちんとした説明もせず、抜本的な対策も取らず、問題を先送りにしてしまっているのです。
筆者が繰り返しセミナーや法務相談の場で語りかけてきたのは〝温情が仇〟ということです。
ワタナベ社長は親会社である日本の神崎製紙と毎日のように連絡を取っており、裁判の中で、日本の神崎製紙の定年制に触れたメールのやり取りが見つかっています。
ワタナベ社長がブラウンリーさんの解雇に関し親会社の承認を求めた際に、人事部から発信された一通のメールでした。
「この社員は何歳かね」との人事部の質問に対し、ワタナベ社長が答えました。
「61歳です」と。
これに対し人事部からは、「日本では定年の年齢ですね」というメールが返信され、解雇が承認されたのです。
これらのメールはのちに説明する米国の証拠開示手続きを通しあからさまになったもので、これが決定的な証拠となりました。