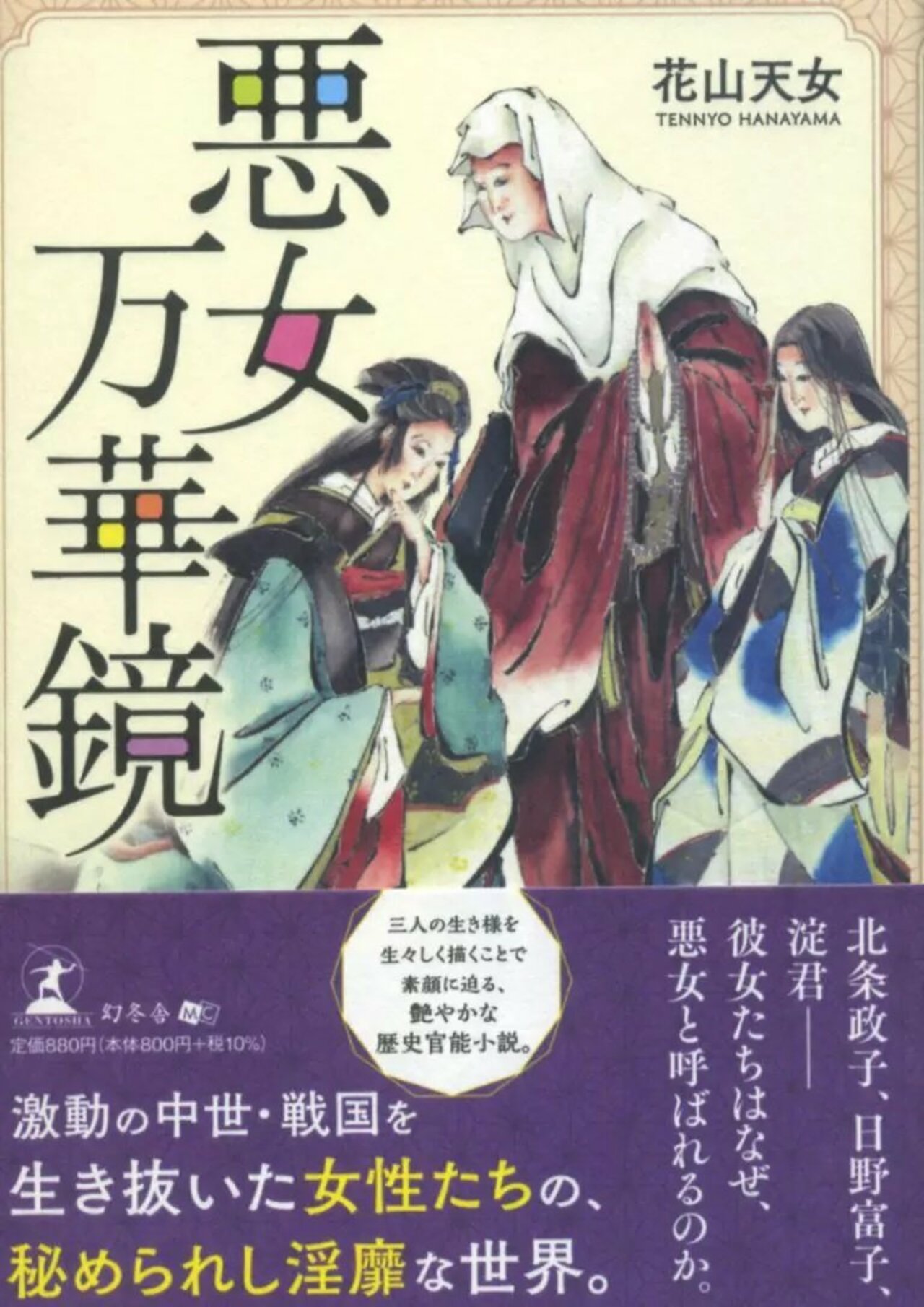「しかじかのことがあるので、どうか合点(がてん)して后のもとへ行ってたもれ」と帝が山部に伝えると「めっそうもない、そんな畏れ多いことを……」と辞退しましたが、父の言うことに従うのが孝行というものと、しぶしぶ承諾されたといいます。
山部には皇后に対する同情心もありました。光仁帝はもう六十歳半ばで、その方の元気も萎茎(なえまら)で頓(とみ)に衰えていますし、しかも山部の母、高野新笠以外にも妃が多くいて、夜のお勤めはとても后まで行き届くものではなく、そのためこのところ、「役立たずの老いぼれのくせに」と寂しく空閨を過ごす義母の気持ちも解からぬではありません。
称徳女帝の姉妹というプライドと強(こわ)らかな性格があいまって、思いがけない博奕の勝利で、久しく耐えていた情念が女の炎に油を注いでしまったようです。
「嬉しやのう、待ちかねておった、もそっとこちらへ……」
満面の笑みで皇后は、美しい反物(たんもの)や心尽くしの品々を揃えて膝(ひざ)をにじりよせました。それからは山部の賜り物を大いに満喫(まんきつ)なされ至極満足されたということです。
この時、皇后は五十六歳、山部三十六歳でした。ご自分の不心得からとはいえ、こんな状況を苦々しく思ったのでしょう、その後の光仁帝は、なんとなく山部を遠くから見るようになり、次男の早良親王に目をかけるようになられたといいます。
更に皇后は、光仁帝の即位に尽力した百川も嫌っていました。良継の娘の乙牟漏(おとむろ)(後の桓武皇后)、百川の娘の旅子(たびこ)(夫人)とも山部王に嫁がせていて、姉の称徳女帝の死を早めたのも百川の対応に問題があったと考えていました。