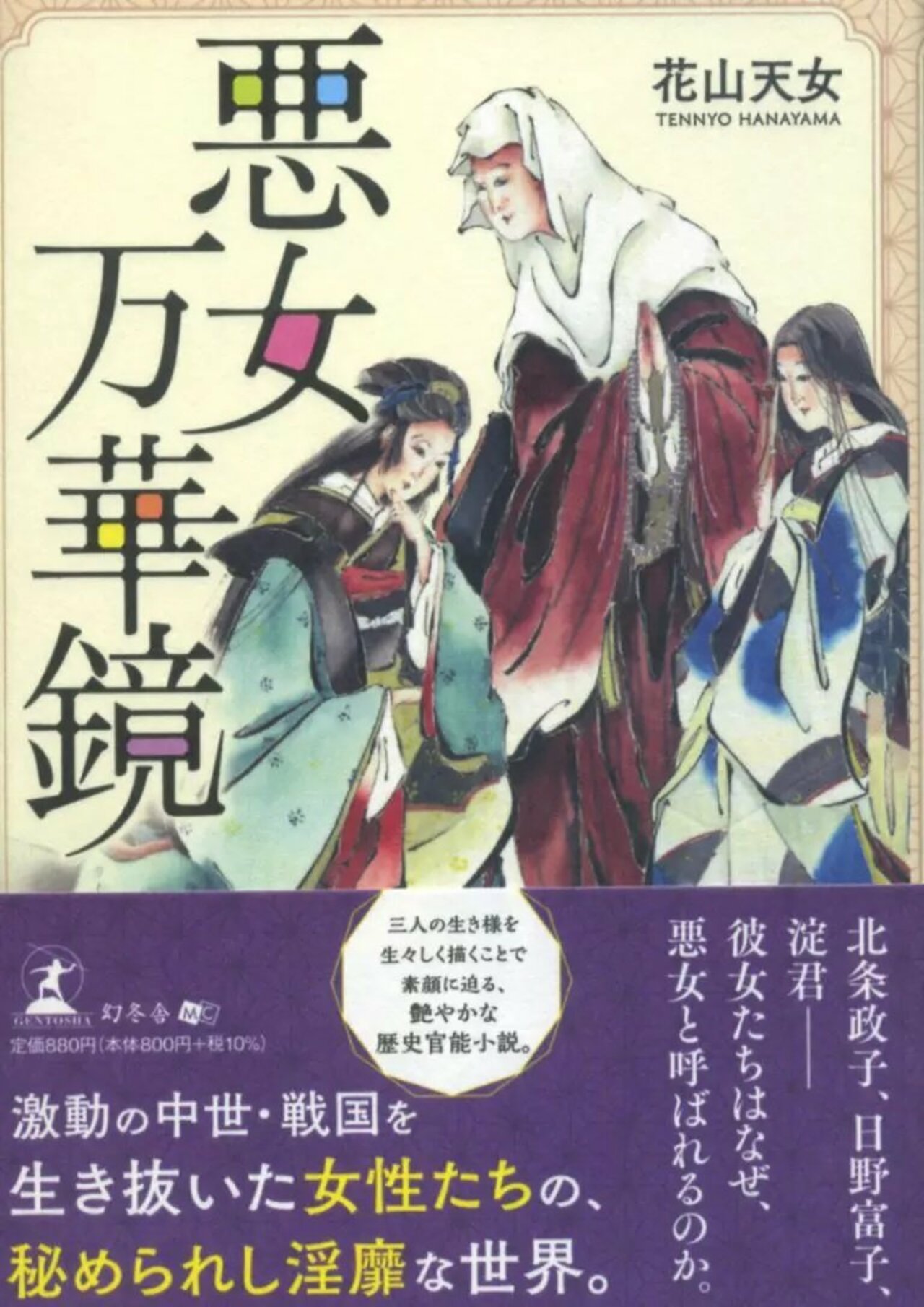その後に続くのは、志太三郎先生義広(しださぶろうせんじょうよしひろ)どのではないか、多田蔵人行家(ただのくろうどゆきいえ)どのの姿もあるようだ。いずれも頼朝によって滅ぼされた源氏の亡霊たちがジッと頼朝を睨んでいた。
冬の日は日暮れが早いとはいえ、いかにも、おどろおどろしい薄墨の夕やみの中に、その身が閉じ込められたとき、馬上の頼朝は「あッ……」と小さな叫び声を漏らし大きく揺らぎ、その瞳はこの世ならぬものを見てしまったそれであった。
ともかく、急がねば……と、やっと鎌倉が見える稲村ケ崎(いなむらがさき)に着いたところ、今度は夕風に波が高まり始めた海面が不思議な盛り上がりを見せ、その中からぼうっと光るものがあらわれた。それは十歳ばかりの童子(わらし)で、
「汝(なんじ)を此のほど随分窺(うかが)いつるに、今こそ見付けたれ、我をば誰かと見る、西海に沈みし安徳天皇(あんとくてんのう)なり!」と叫んだ。
そしてこの日、頼朝は御所に帰るやいなやドッと床に臥せ、まもなく世を去ったというのである。
頼朝の死は、彼のために非業の最期を遂げた源氏の一族や、平家などの怨霊によって呪われたのであり、多くの人々を死に追いやったことによる祟りであると『保暦間記』では解釈している。
四 お牧の方の憂鬱
頼朝の死後、長男頼家が十八歳で二代目の鎌倉殿の地位についた。
だが父の代からの宿老や重臣たちの存在が何かにつけて彼の行動に制約を与えることになると、その反動が生じてか、彼は蹴鞠(けまり)にふけるなどの享楽(きょうらく)に心を寄せていく。
更には父譲りの女好きもあり、女性問題にはことのほか多忙で、家臣を出張させその隙に妾(めかけ)を奪い、帰ってきた家臣を討とうとする、典型的な二代目のお坊ちゃんであった。
【前回の記事を読む】嫉妬心は愛情生活には切り離せないが、それが限度を超えてしまうと悪となる