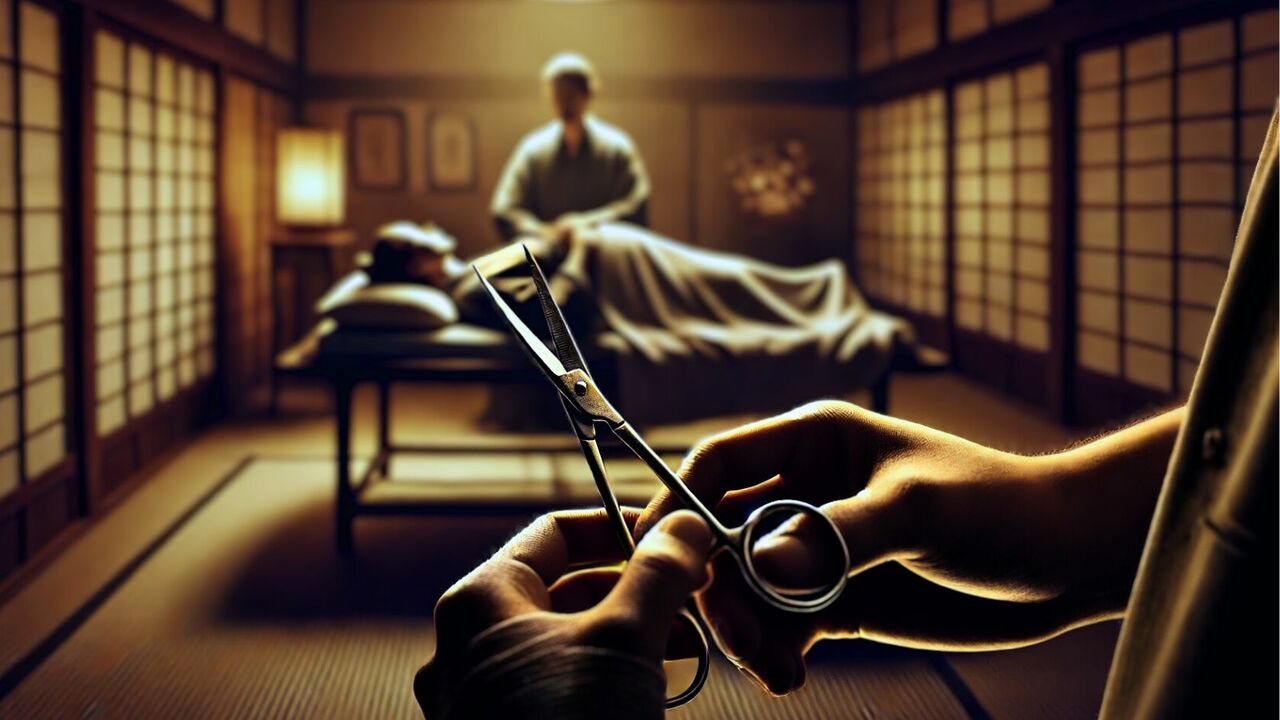「どうぞよろしく、お願い申し上げる──」言葉と裏腹に、いかにも尊大な態度で現れたのは、新政府の役人だった。
幕末の混乱期、長州や薩摩などの有力藩は、こぞって京都に屋敷を置いていた。維新後は、中央政府が薩摩と長州の元武士を、役人として派遣し始めた。
やがて彼らは、京都の街を我が物顔で闊歩するようになっていった。権力をカサに着た、彼らの傍若無人な振る舞いは目に余った。
いつの時代でも、小役人ほど意地汚い連中はいない。京都人は、そんな連中を斜め後ろから冷ややかに眺め、服従しているふりをしていた。だがそれは、京都人が千年の歴史で身につけた、一種の処世術でもあったのだ。
もちろんヨンケルは、そんな事情など知る由もない。自分を頼って訪れた患者を、優しく出迎えた。
「ここのところ、喉の調子が悪く、咳もよく出るのだが……」
その小役人は、ヨンケルではなく通訳の大木に向かって、ぞんざいな口の利き方をした。
そして西洋人の医者の実力がいかなるものかと、ヨンケルを胡散臭そうな目で見ていた。
一方、ヨンケルは患者の訴えに、真剣そのものの表情で耳を傾けていた。
すべて聞き終えると、ヨンケルは患者の口を開かせた。そして舌圧子(ぜつあつし)を挿入し、喉の奥を覗き込んだ。
呼吸器の病気とのことで、ヨンケルは特に念入りに胸の音を聴取した。そのあと、最初の患者と同様に、首から腹部に至るまで触診していった。すると小役人の患者は、少しずつ態度に変化が見られ始めた。
ヨンケルがこと細かに問診を追加しているうちに、言葉遣いも丁寧となっていったのだ。信頼を寄せ始めている様子だった。
ヨンケルは、漢方医と違い、決して知ったかぶりをしなかった。知らないことや、わからないことははっきりと認め、また漢方のような秘術めかした誤魔化しもなかった。
客観的な事実に基づき、病気を治すことに専念する態度が、万条にもありありと感じられた。
投薬を受ける頃には、患者の小役人もすっかり態度が改まっていた。尊敬の眼差しでヨンケルを見つめ、米つきバッタのように腰を折り曲げると、厚く礼を述べてから帰って行った。
結局その日の患者は、坊主と役人ばかりだった。そしてみな、感謝感激して仮設の診療所を後にした。
万条も、これが本物の西洋医術かと、すっかり度肝を抜かれたのだ。
【前回の記事を読む】いよいよ西洋人医師による西洋式病院と医学校の開校計画が京都で始動!