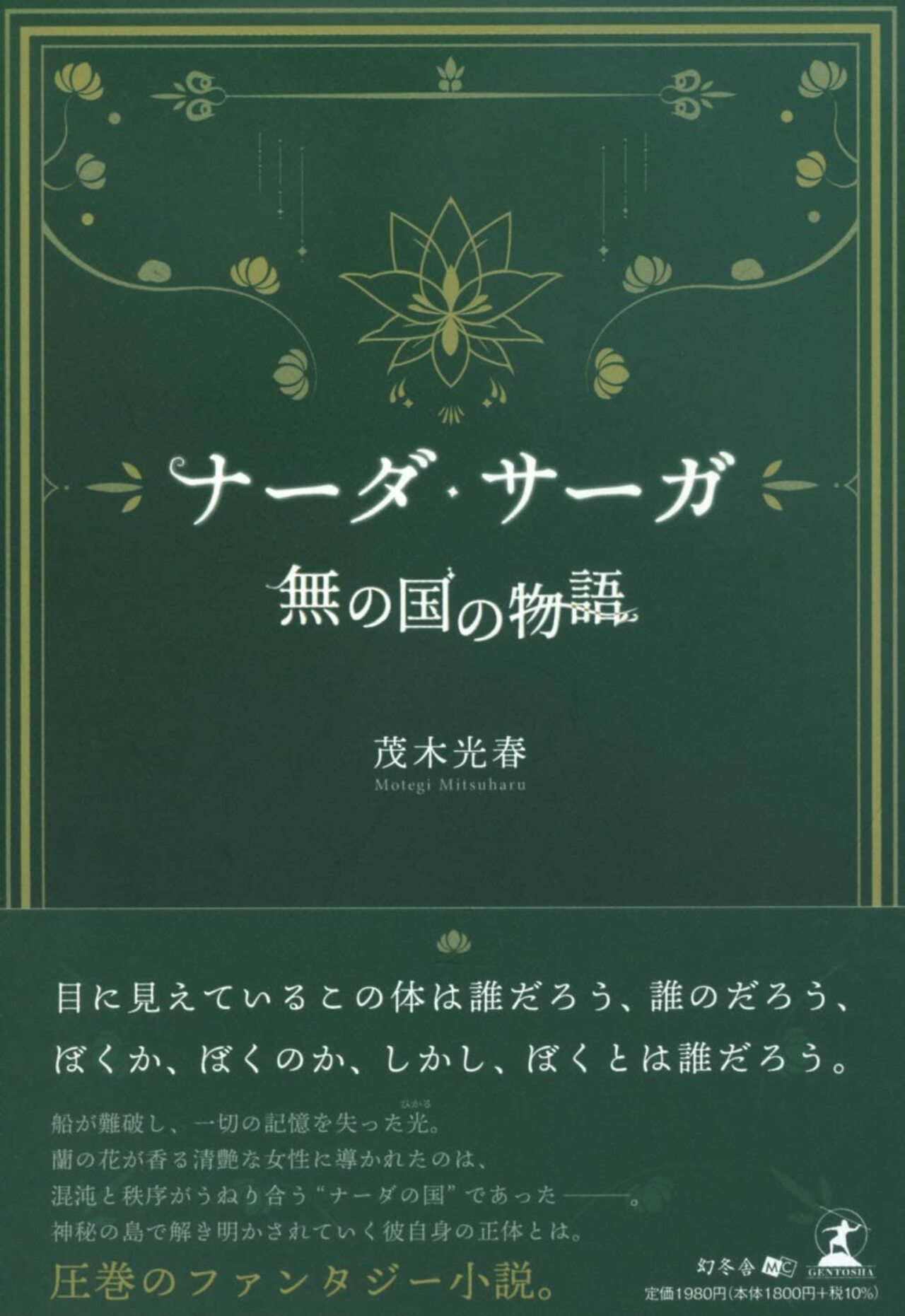どうぞ、ご覧になってくださいませ。かすかに匂うております。沙羅の木の花の匂いでありましょう。しかしながら、お釈迦さまの匂いのようでもあります。また迦葉さまの匂いのようでもあります。またその時の拈華微笑の匂いでもありましょう」
花屋の娘さんが花に囲まれて立ちつくし、右手に持った沙羅双樹の花の枝を右頬の辺りまで掲げてみせたのである。通りかかって、娘さんの口上を聞いていたものがいつの間にか二、三十人にまで膨れ上がり、花屋の前に立ちつくしていたのだが、その光景を見て、ただうっとりと見とれるばかりであった。
店の娘さんはつつっと前に歩いて来るや、人々に向かって「さあ、どうぞ」と言って、一人一人に手に持った沙羅の木の花の枝を差し出したのだ。
しかも不思議なことに、見た通り手には一本の花の枝しかないのに、居並ぶ人たちすべてに次から次へと花が手渡されることだった。ぼくにもそれは渡されて、手渡す瞬間、娘はほおおっと優しい艶やかな笑顔をぼくに送った。
それはぼくに届き、伝わり、ぼくの顔の、絶えて浮かべたことのない笑顔、言うなれば、顔の古層に眠りこけ埋もれていた笑顔にまで届き、伝わり、ふっと一つに合わさり、溶け合い、強ばった顔の表層を崩し、雲散霧消して、古層の笑顔が匂い立つのが感じられたのであった。
ぼくの笑顔、ぼくの顔に限られた笑顔というのではなく、ぼくという限りを崩して、周囲の大気と一つになって漂い出し、香り出すがごとき笑顔、言わば、大気の笑顔とでもいうものが広々と大らかに広がり渡っていたのであった。拈華微笑とはこのことかと、自覚されて来るところがあった。
ぼくは花屋の店を後にした。