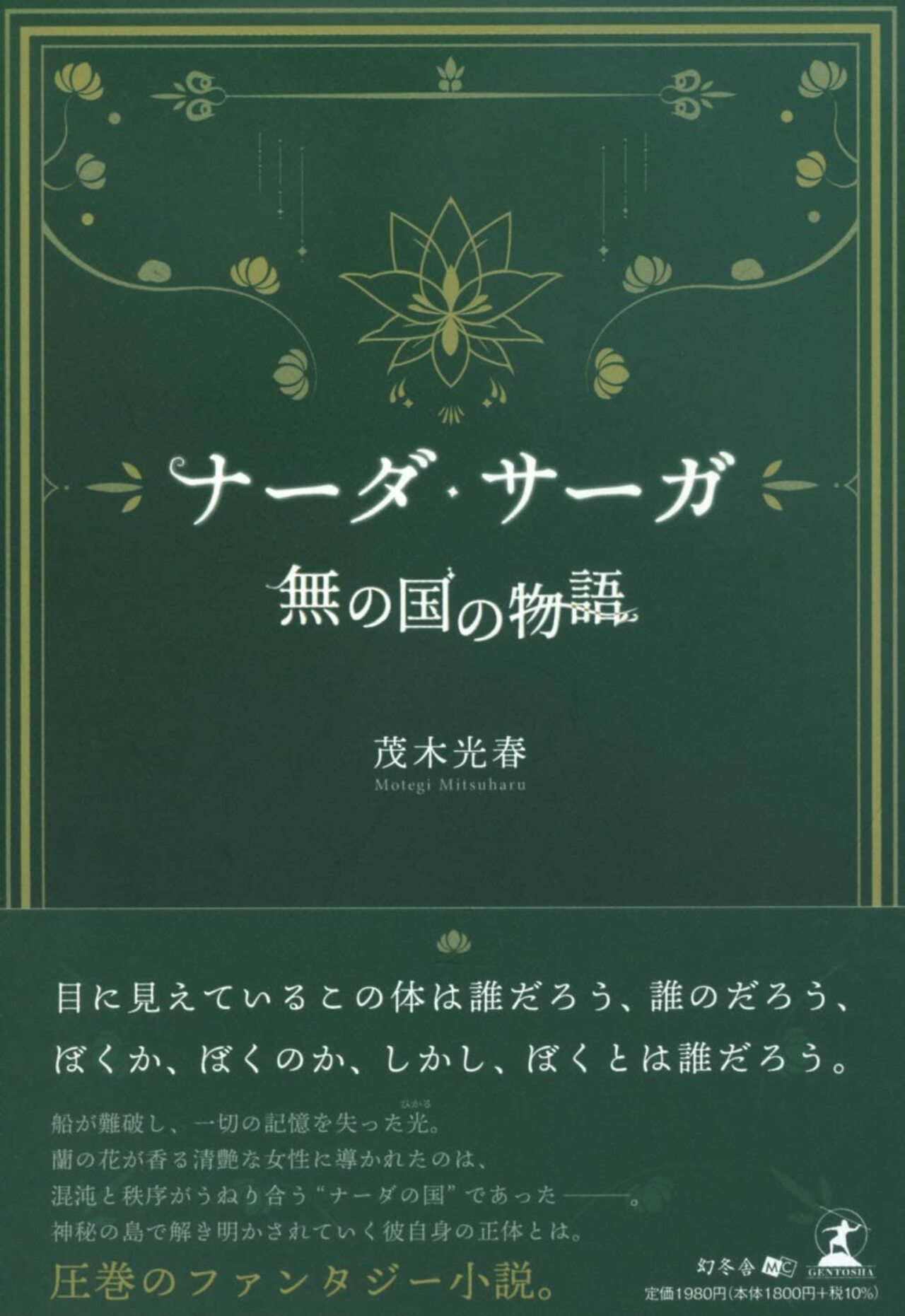三 バザー・ナーダ(聖書の木を売る店など)
次から次へと店が続き、人々が詰めかけ、店の者は大声で客を呼んでいて、賑わいは賑わいを誘い、バザーを喧噪の巷と化していた。
八百屋があった、乾物屋があった、お茶屋があった、飴屋があった、一杯めし屋があった、鰹節屋があった、肉屋があった、鰻屋があった、鯰(なまず)屋があった、蛇屋があった、猫屋があった、犬屋があった、鞄屋があった、靴屋があった、下着屋があった、宝石屋があった、墓石屋があった、十両(りゃん)を五両で売る店があった、百両を五百両で売り飛ばす店があった、贋金(にせがね)を売る店があった、古着屋があった、骨董屋があった、花瓶屋があった、夢屋があった、空屋があった、無屋があった、有屋があった、有屋無屋があった、本屋があった、古本屋があった、トコロテンを無理矢理食わせる店があった、立ち食いショップがあった、そば屋があった、ラーメン屋があった、いきなり一泡吹かせる店があった、優しさを売る店があった、消費税をきちんと払う店があった、言葉を売る店があった、言葉を買う店があった、痺れる店があった、だるい店があった、媚びを売る店があった、油を売る店があった。
それらの店はどれもこれも大変面白く興味をそそるものばかりであって、立ち止まり、売り子店員の売り込みの言葉を聞いてみたいと思ったのだが、そして、先ほどまで一緒だったセイレイ嬢に言わせると、この国には時間がたっぷりあって、いくらでもかれらの油を売るのを聞いていても構わないはずだったが、全部を見かつ立ち寄ることはできなかった。
ただその内のいくつかはさすがに通り過ぎるのももったいなく、立ち止まってしまった。
たとえば、夢屋というのがあった。
店にはおびただしい数の、そしてさまざまな大きさの樽や瓶や壺が置いてあって蛇口やらコルクの栓やらがついていた。
そしてその中に一人の老人が座り込んでいて、通りかかる人々を憮然とした面持ちで見つめ、つまらなそうに扇子を使って自分の顔を扇ぎつつ、時々よく分からない言葉を、客に向かってなのか辺りの空気に向かってなのか、言わば上の空で語りかけていたのであった。
白髪の上、白い顎髭を長く太く垂らしていて、細く痩せこけていながらも、すっくと姿勢良く、端座していた。
話の断片から老人は自分を鄲邯(かんたん)老人と呼んでいて、何でも、ナーダの国へ来る途中、中国は邯鄲という町で、日が暮れ、一夜の宿を取って休んでいた時、土間の方で、夕食の粥を作っている匂いを嗅ぎながら、うとうとと眠ってしまった。
やがて目を覚ましてふたたび旅を続け、ナーダの国にやって来て国一番の大学を出、国一番の役所に入り、係長から課長へ、課長から部長へ、部長から局長へ、局長から事務次官へと昇進した。
その間、名家の娘を三人も妻に娶り、子供もでき、ついには望まれて、大臣のポストにまで就くに至った。折しも、国土交通大臣になってからしばらくして、ナーダ国と中国との間で、いくつかの島と海を挟んでの「第二オリエント急行・五年計画」が持ち上がり、その第一回のトップ会談を行うために部下や秘書を連れて船に乗り、車に乗りして、中国は北京に向かった。
しかし道中の邯鄲という町で日は暮れ、駅前の鄙びた一軒の宿に入った。
そして夕食のできる前に、急に疲れが出て部屋で眠ってしまった。
どのくらい時間が経ったのか、ふと目覚めて辺りを見回すと、古くさい旅籠屋の土間の上がり端に寝ころんで、自分はうたた寝していて、土間の向こうではまだ粥はできておらず、ぐつぐつと泡を立てているところだった。
そして自分の身なりを見ると、相変わらず汚い旅の服を着たままの若者に過ぎなかったと言うのだ。
それから五十年、いろんな国を訪れ、働き、偉くもならず、落ちぶれもせず、ようやく憧れのナーダの国にたどり着き、こうしてその都で夢屋を開業したと言うのであった。
「でもな、お若いの」
と、ぼくを見ながら、老人は言った。どうやらぼくは若いらしい。鏡を見ていないし、自分に纏わる記憶もないから、自分がどういう存在なのか見当もつかない。
「思うに、わしはまだ邯鄲の夢を見ているに過ぎないのかもしれん。
邯鄲の宿で一つの夢を見て、それから覚めてここまでやって来たとしてもな。まだわしは同じ邯鄲の宿にいて、次の果てしない夢を見始めているに過ぎないのかもしれんからな。
夢の中で、こうしてお主に会い、わしは邯鄲老人と名乗って、夢屋という商売をしておるに過ぎないかもしれんからの。
まあ、それはよい。
人間のアイデンティティなどというものは極めてあやふやなもんじゃ。
この世のアイデンティティもそう。この宇宙のアイデンティティもそうじゃのう。
まあ、まあ、いろんな夢を見て行ってくだされい」