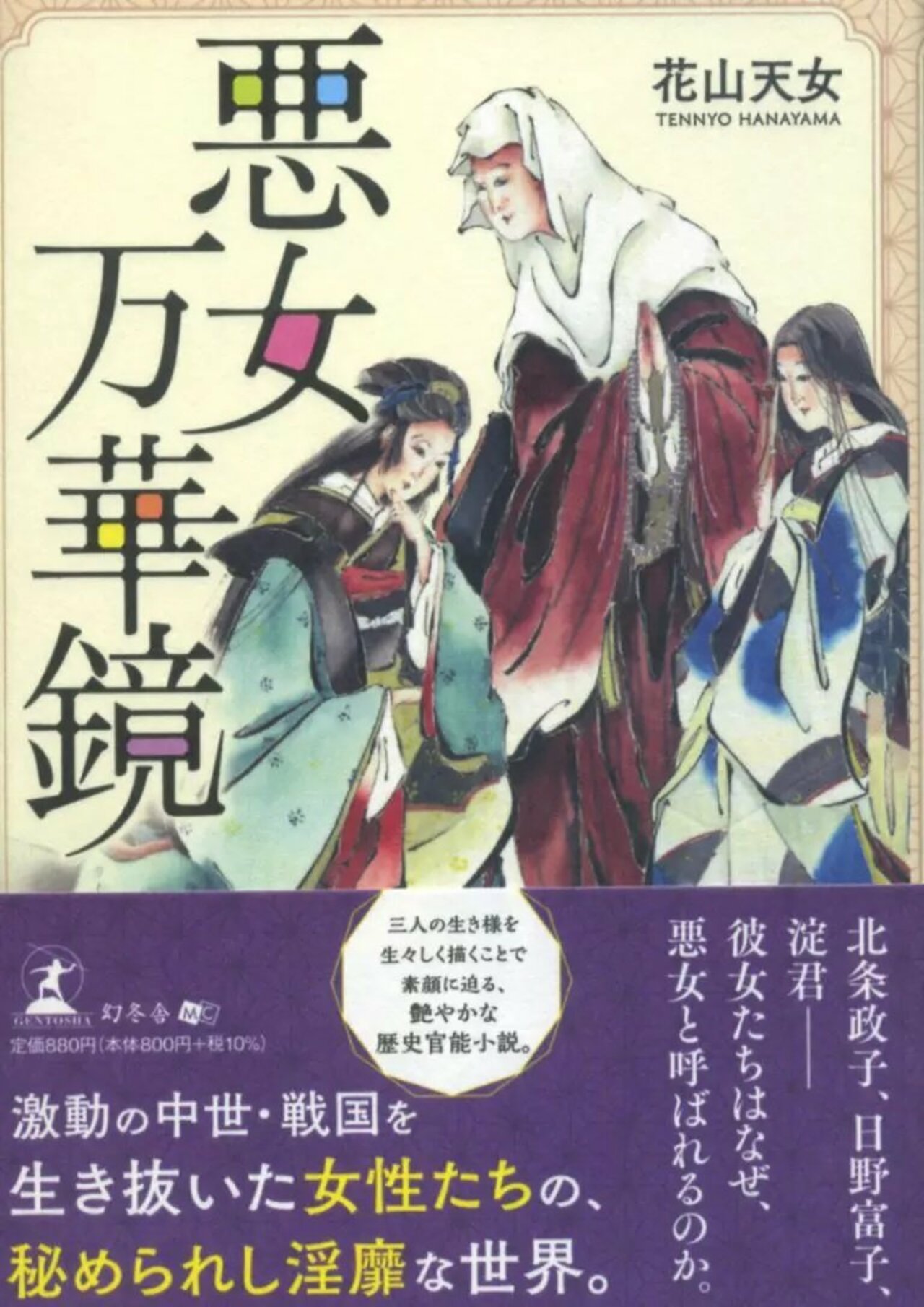第1部 政子狂乱録
三 亀の前の厄難
後手の荒縄で結わかれた女囚は、恥辱に染まり悩ましく裸身を震わせながら口答えしたものだから、政子はあきれて、
「こりゃ、悪いことをいいましたな!」
ぽかん~とした顔から、政子はみるみる表情を不快なものにした。
「バカも休み休みいわっしゃい、勝手な惚気を言いおって! 妾というものがありながら、殿がお前のそんな童顔に惚れるわけがなかろう、そなたが臆面もなく上様に色目を使ったに相違あるまい、殿はそんな丸顔はお好みではないぞ、妾のような細面のキリッとした様子がご趣味なのじゃゾ、戯言も大概にせい」
と、あべこべに眼を据えて睨み返えした。
亀の前は返す言葉もなく快楽の余韻を残しながら悔しいけれど涙にくれてうつむくばかり、目を伏せると長いまつ毛が一層きわだった。恥辱心や躊躇いは、肌に潤いと艶を与えて女をめだって美しくするものだと気がついて、政子の怒りはますます高まった。
(裏口から入ってきながら……よくもまあ、まじめくさった戯けたことを、片腹痛いわ、こんな小生意気な女は、串刺しにしてヒイ、ヒイ鳴かせねばなるまい)
政子の顔は夜叉のごとく引きつって、崩れた頭髪は怒りで逆まき天を衝くばかり。
天井の唯一の小さな灯とりから差し込む光だけが、両手を後手に戒められた妖艶な女囚の幻影を周囲の白壁に映していた。
「では……止むを得ませぬな」
政子は淫靡の悦びに喉を鳴らしながら、女の秘所を覆っている唯一つの赤い布をむしる様に取り去った。露出された妖花を覆う漆黒の性毛が芳香を漂わせ、さわさわとなびいている。
「亀どの、この赤褌はなあ、上様ご愛用のお品であるぞ、そなたを可愛いと褒めてくれた愛しい男の匂いがするであろうが、どうじゃ嬉しくはないかえ……」
政子は片方の手も後ろに回して、両方の指を使いながら、すすり泣く美囚の前後の秘所を同時に弄んだ。
「ヒイッ……あ、熱い、お腰が蕩けてしまいます……御台様ああああ~」
絶望的な恥辱と快楽、そして忌まわしい苦痛に泣きじゃくりながら、政子の巧みな指虐にどうにもならない女の生理を征服されて、またしても陰門からは甘酸っぱい匂いを漂わせながら潤いが湧き出して、黒光の床板を濡らす。
美しくも妖艶に縄化粧を施され、喘ぎながら責めを受ける女の美しさは、その柔らかい弾力のある女体が、たっぷり愛汗を吸い込んだ荒縄で異径にくびれ、くぼんで弩脹するところに生まれる。
(どうも、この女は可愛いおぼこのように飾ってはいるが、自分の身体は男のためにあると、とっくに知っているようだ)
女は、すっかり観念したようだ。