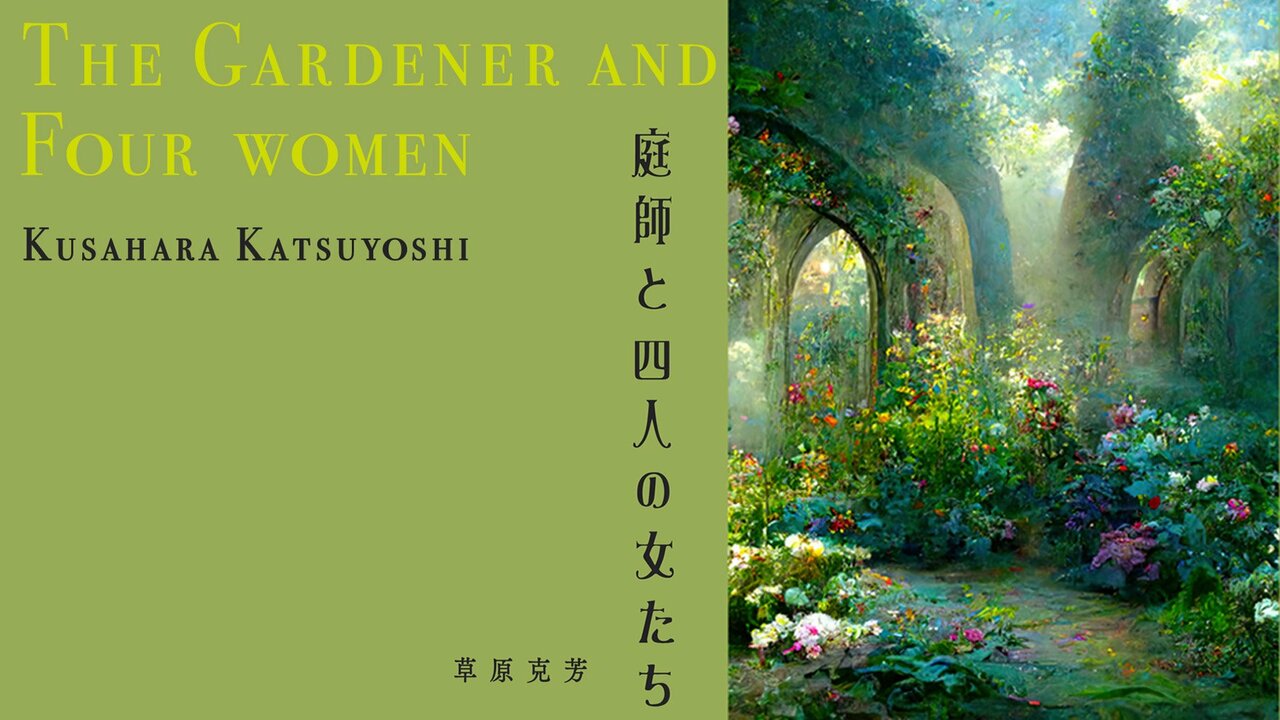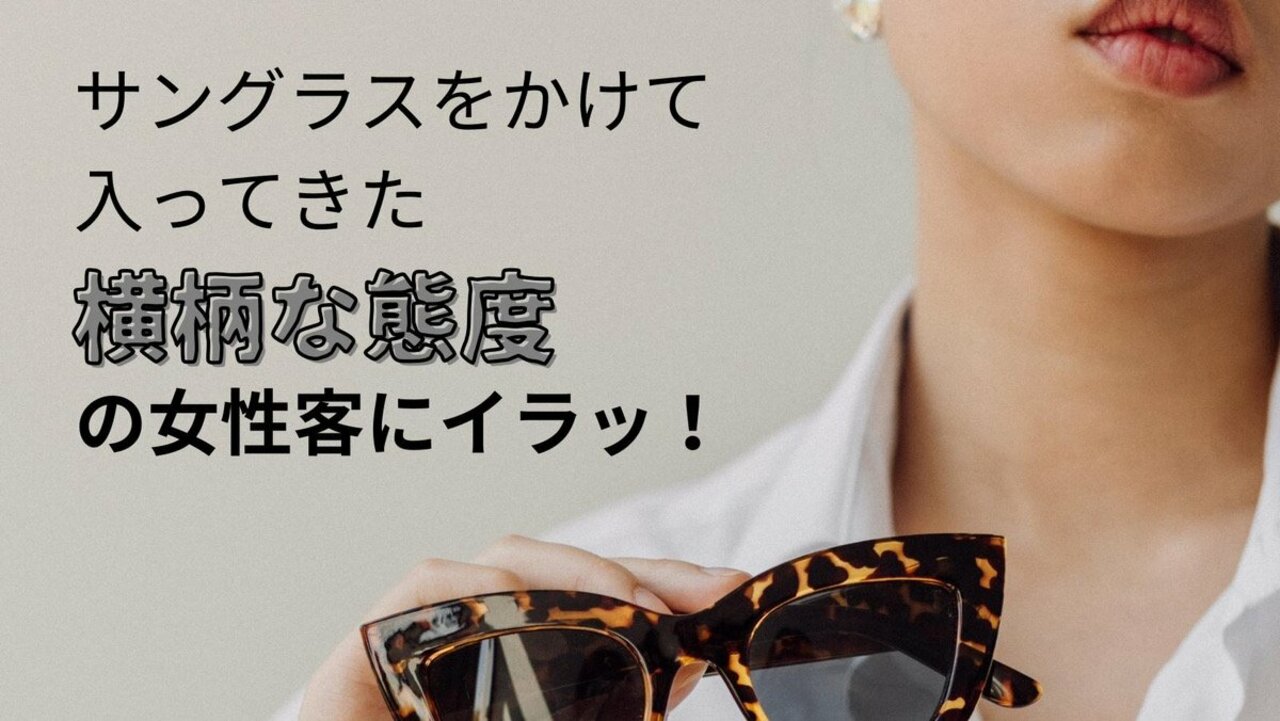庭師と四人の女たち
3
――睦子とマス江が、変わり映えのしない世間話を続けていると、入口に下げられた真鍮製の鐘が鳴った。
入ってきたのは、褐色の細いサングラスをかけた三十代くらいの背の高い女であった。彼女は黒崎耀子といって、やはりこの中庭に面した南側の二階建て低層マンション「ヴィラ・フローレンス」に住んでいた。
グレイのシャツを着て、小さなバッグの中から薄い緑色のタバコの箱を取り出した。睦子ママが行くと、耀子はシナモンティーを注文した。そのとき、テーブルに置いてあった彼女の携帯電話が鳴り出した。舌打ちをして、立ち上がる。
「はーい、あたし。なんだァ、淳か。暑いわねえ。ううん、ちょっと部屋から出て近くの喫茶店に来ているの。あそこよ、そうそう『パンタレイ』。この間来たでしょ、ここの店」
彼女は携帯電話を耳に当てながら、南側に開かれた窓から入ってくる日差しを避けるため、おでこのところに左手を翳した。
「もう忙しくてさ。先週からバタバタしっぱなし。そうじゃなくて。クライアントが阿呆だから、ベースになるデザインが、なかなか決まらないわけよ。そいでまた、その上司が、もう、最悪でさ。なにせ一度フィックスしたことをひっくり返すのが、奴さんの趣味ときてるんだから。あれでちっぽけな権力の快感、感じてるの。最悪でしょ。うんざりよ、もう。……そうね、プレゼンはぎりぎり再来週の頭かな。やりたくないんだなぁ、こういうタイアップ広告。でもあそことのプロジェクトが失敗したら、いままでの蓄積がパーよ。あたしの立場だって、危ないわ。営業に睨まれてね。これでもさ、切られないように、おべっか使って泳いでんのよ。どうせスタイリストとかコーディネーターなんて、そんなもんよ。雑用係ね」
カウンターの袋田マス江が、下唇を突き出しながら後ろを見た。そして声を低めて、店主に顔を近づけた。
「あの女さ、最近よく来てるけど、ああいうのは何だか、キザったらしくていけないよ。何でわざわざ仕事の話をヒトに聞かせたがるんだい。キャリアウーマンでございましょう、って感じでさ」
「ちょっと。聞こえるわよ。彼女、黒崎耀子さんよ。アパレルとかマスコミ関係、ファッション雑誌のプロダクションにでもいるんじゃないかしら。会社名、何とか言ってたわ、カタカナで。よくこの店でも、大柄のずんぐりした髭の男と打ち合わせしてるわよ。何でもカメラマンみたい。きっと彼氏だわね」
「ふうん。そうかい。……でも、虫酸が走るんだよ。ああいう連中は。聞いてるとさ、自分が世の中動かしているみたいな言い草じゃないか。それに、いつも思うんだけど、ケータイってのはさ、自分の話をこれ見よがしに人様に聞かせるには、いい機械だねえ。あたしゃ、絶対持ちたくないわ」
「シッ! 声が大きいわよ」