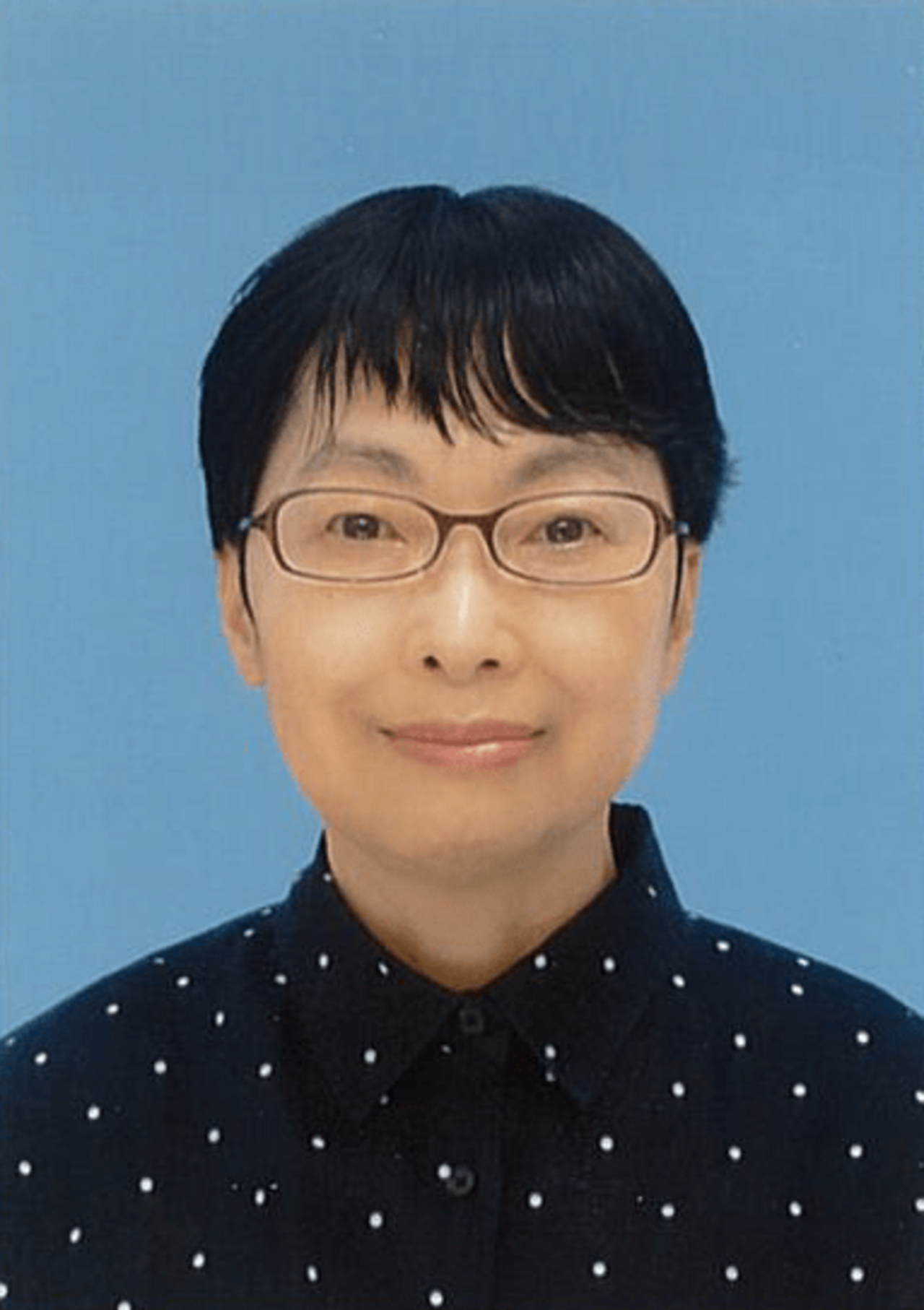翌日の午後の一時になり、リエとユミの二人が、私の家にやってきた。
「こんにちは。久しぶり」
「どうぞ上がって。私の部屋でゆっくりしましょう」
「ええ。ありがとう」
私は、二人を私の部屋へ案内した。それから私はアイスティーを作って、自分の部屋へと運んだ。
「お茶どうぞ」
私は二人にアイスティーをすすめた。
「私ね。二人に聞いてもらいたい話があるの」リエが言った。
「改まっちゃって。一体、何?」私は聞いた。
「実はね、私、恋をしちゃったみたいなの」
「えっ、ウソ。だってリエ、恋なんかしたくないし、結婚もしないって言ってたじゃない」ユミが言った。
「そうよ。恋なんて時間を奪われてリスクだって言っていたよね」私も言った。
「うん、そうなのよ。だから自分でも意外過ぎて驚いているの」
「一体、どんな人?」
「今、二十八歳で商社に勤めている男の人なの」
「どこで知り会ったの?」
「この間、私の家で出会ったの」
「家で? どういうこと?」私は尋ねた。
リエの父は高校で数学の教師をしているが、学校には英語の教師をしているアメリカ人がいる。彼は高校の時ホームステイで来日して、すっかり日本のファンになり、日本の大学を卒業して父と同じ高校の英語の教師になったのだ。その先生の家族が先日、リエの家に遊びに来て一緒に昼食をしたという。
リエのお父さんとその先生は同い年だけど、お互いの子どもの年齢は十歳離れていて、その男性は二十八歳。今は商社に勤めているらしい。
「フムフム」
私は頷いた。
「奥さんは日本人でね。子どもはだからハーフなの。子どもは一人だけなの」
「その子どもが、二十八歳になる商社勤めの人というわけ?」ユミが聞いた。
「そうなのよ。身長が一八〇センチくらいあって、ハンサムで英語と日本語のバイリンガルなの」
「私の母が、恋心は、ある時、突然降ってくるように心の中に現われるものだって言っていたけど、まさにそれね」
私は先日母が言っていた言葉を思い出していた。