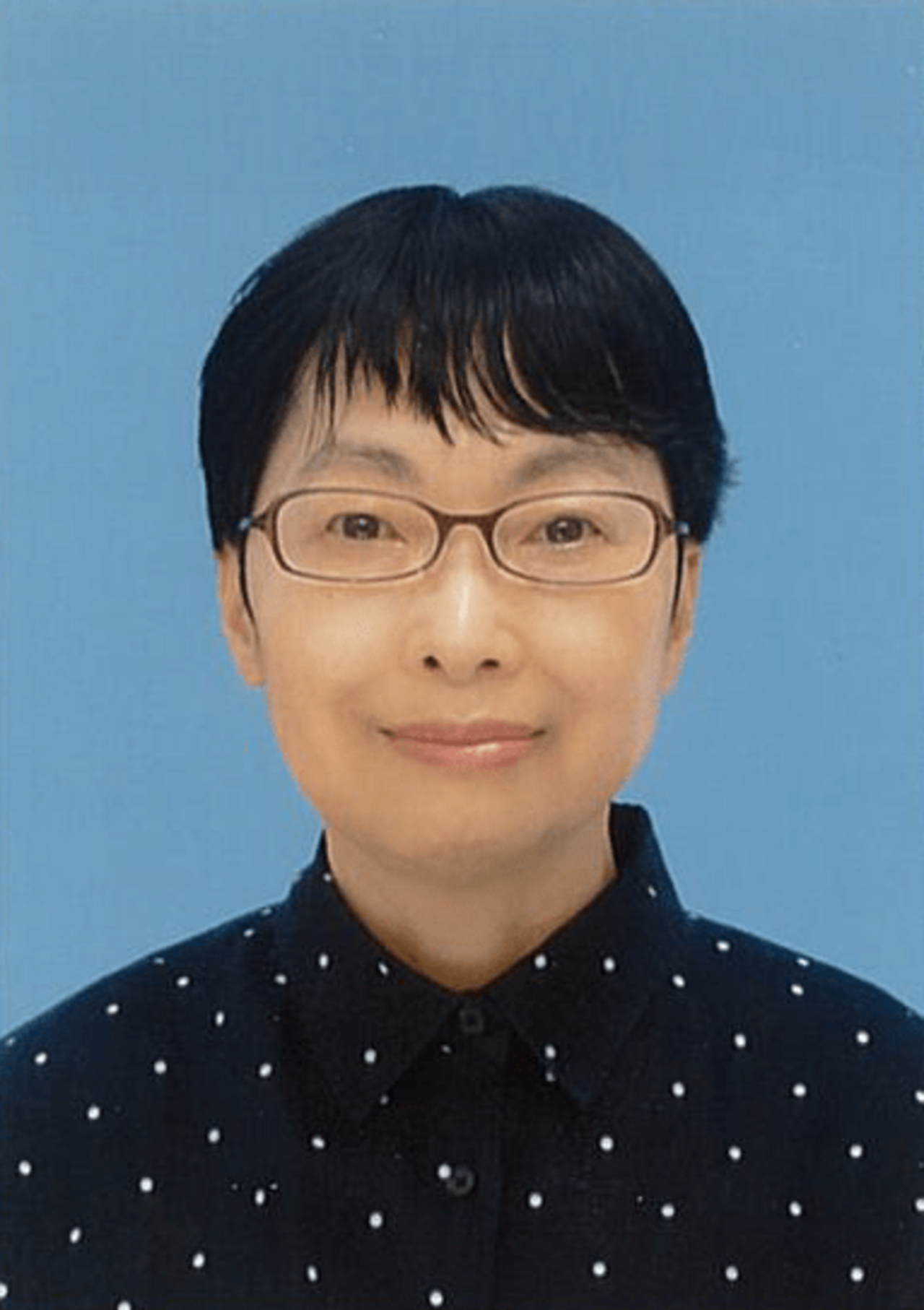私たちの春
私は、母の言った言葉、恋心はある時、降ってくるように心の中に現われるというのを、頭の中で繰り返していた。あんなに恋愛に拒否反応を示していたリエが恋に落ちるなんて。自分にもいつかそんな日がやってくるのだろうか。でも、今は、精神的に経済的に自立した大人の女性になることに全神経を集中させたい。
それに私は、本当に男の人には全く興味が湧かないのだ。多分、私は、まだ精神が子どもなんだと思う。私は男の人のことよりも、今晩の食事の献立を考えたり好きな音楽のメロディーを聞いたり、両親と家族団欒を楽しんだり、リエとユミとおしゃべりをしたり。そういうことの方が、毎日が充実していていいなと思っていた。それに恋に盲目になるなんて。
そんなことストレスになってバカらしいと思われた。両親やリエとユミと時間を過ごすことの方が、はるかにずっと楽しくて幸せだと思う。今のままの生活スタイルで充分満足していて、恋愛なんて、私の日常のすきまに入り込む余地なんて、これっぽっちもないと思った。
九月になって、二学期が始まった。私たち三人は、いつものように、お昼休みに一緒にお弁当を食べていた。
「京子とユミ聞いてくれる?」
「何?」
私は尋ねた。
「いつか話した彼のことなんだけれど」
「どうしたの?」
「彼、今度から毎週日曜日の午後に私の家に来て、私に英語を教えてくれることになったの」
「えっ、ホントに?」
私は驚いた。