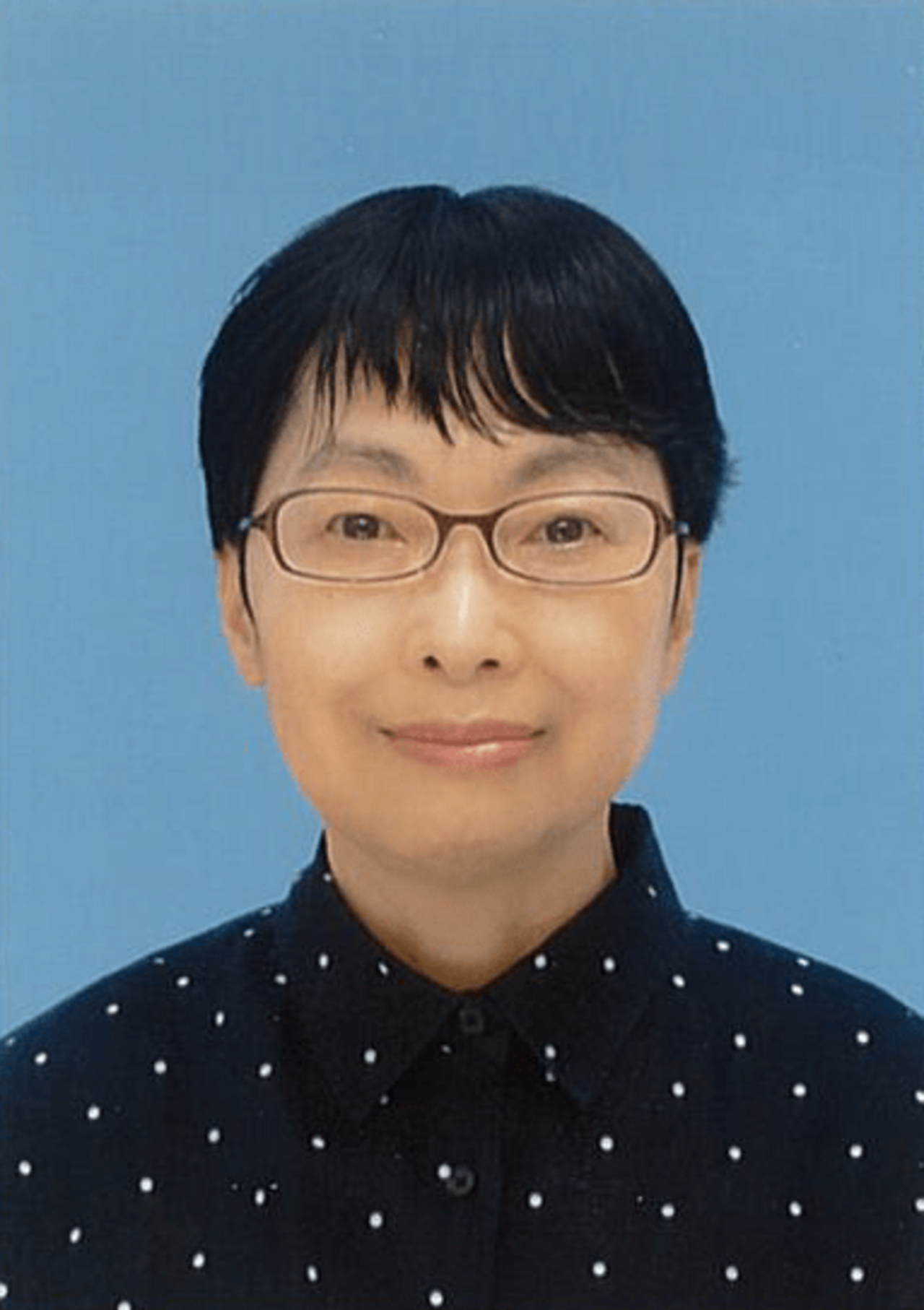「彼の名前、正樹さんていうんだけれどね、私、正樹さんに思い切って彼女さんはいるんですかって、メールで聞いてみたの。そしたら、今はいなくて週末は暇にしていますと返信があったの。そして僕で良かったら、英語の勉強を見てあげますよということになったの」
「わー、スゴい」
「良かったじゃない」
「うん。私、嬉しい」
「恋と勉強、同時進行して、理想の青春じゃない」
「両親もね、喜んでくれているの。彼のお父さんと私の父は仲の良い同僚同士でしょ。父は、しっかり勉強を見てもらいなさいって言ってくれるの。そして勉強が終わったあとは、母が夕食を用意してくれて、私の家族と正樹さんの四人で一緒に食事をすることになったの」
「家族ぐるみの付き合いをするのね」
私は喜んだ。
「そうよ」
「彼のことをよく知るチャンスじゃない」
「ええ。彼が英語が使える人という段階で、私の理想の人というハードルは越えているの。外見も、申し分ないし。大手商社にも勤めているし。親同士もよく知った間柄だし。あとは、彼の人柄を知ることができれば、私と正樹さん、恋人として発展していくようになるかもしれない」
「半年前には、恋人なんていらない。時間が奪われてリスクがあるだけよと言っていたリエなのに」
ユミが言った。
「この変わりよう」
「ホント、自分でも信じられない。こんなに自分の気持ちが変化するなんて」
「彼女さんがいなくて、ラッキーだったね」
「うん。彼女さんがいるかどうかについて尋ねるのに、すごく勇気が必要だったけど、思い切って聞いてみて良かった」
「普通は、娘に好きな人ができた時、親は、相手がどんな男か、心配するものだけれど、リエの場合は、まず父親同士の仲が良かったというのも、幸いしたね」
「リエのお父さんが、彼の家族を家に招待した時に、もう既に、リエのお父さんの心の中には、リエと正樹さんが、親しくなるのを望んでいたんじゃないの?」
私は感想を言った。
「ええ。もしかするとそうかもしれない」
「年頃の娘に、むしろ、良い男性を紹介してみたいくらいの積極的な気持ちがお父さんの心の中にあったのかもね」
私は言った。
「うん。それは言えてるね」
ユミも同調した。
「これからの私の恋の行く先を、京子とユミの二人で見守ってね」
「ええ、もちろんよ」
「応援するわ」
私たち三人は、仲間のうちの一人に好きな人ができたことにワクワクしていた。私たち三人は、これまで三人のうち誰も恋したことがある人間がいなかったので、リエが、最初の恋愛体験者となることに、未知との巡り合いのような感覚を味わっていた。