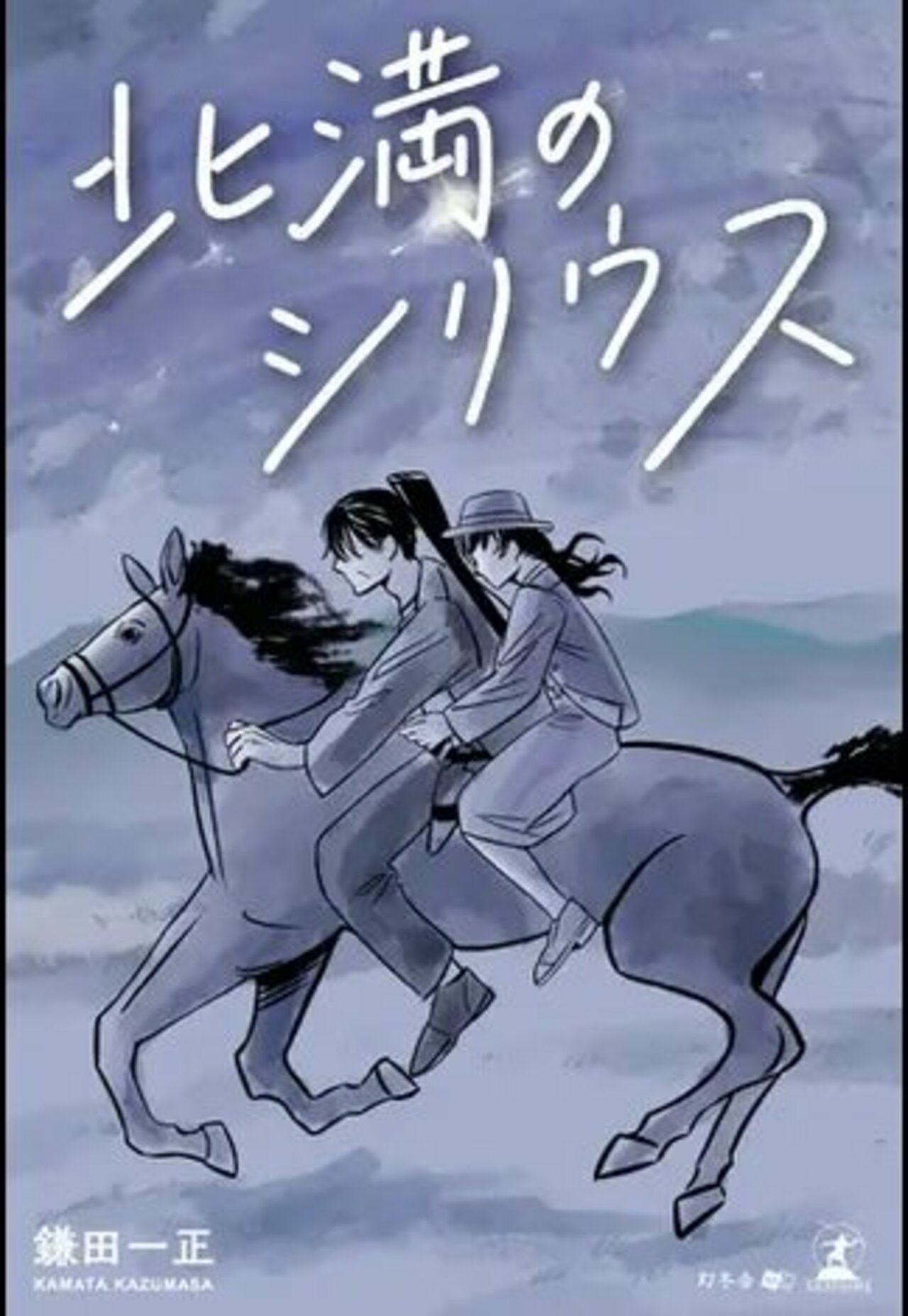一九四五年八月七日 午後一時頃 ハルビン ハルビン街 青島診療所
ハルビン駅から車站街に沿って南東に真っすぐに進むとほどなくして、ハルビンのシンボルであるサボール(中央寺院)が見えてくる。そして、このサボールのあるロータリーで車站街と大直街が交差している。このロータリーをそのまま、まっすぐに突っ切ると、ハルビン街につながる。
さらに、そのハルビン街を南東に二キロ進んだ先に、ナツの通うハルビン富士高等女学校や、アキオの通う花園小学校がある。その手前一キロほどのところ、つまり中央寺院との真ん中あたりの北東側の道沿いに青島診療所はあった。
夏真っ盛り、診療所の開け放たれた窓からは、今日もゴーン、ゴーンという鐘の音が、当たり前のように聞こえていた。
午前中に受け付けた外来患者の診察は、ほぼ終わり、残るは、あと一人だけだ。ハルは、その最後の一人、坂口茂夫の診察を今、終えたばかりである。坂口茂夫、年の頃は、六十代か七十代か、カクシャクとした老人である。
茂夫と向き合って座る白衣姿のハルの明るい声が、診察室中に響き渡った。
「どこも異常はないですよ。寝冷えをして、夏風邪をひいたのかも知れませんね。処方箋を書いておきますから、あとで薬局に行って下さいね」
「そうか、そうか! 安心したわい! 何か大変な病気にでもかかっとるんじゃないかと心配しておったからの。大したことがないとわかった途端、急に力がみなぎって来おった!! これで、また、隣組の手伝いが出来るわい。何しろ、体力があり余っとるからのお!!」
ランニングシャツ姿の茂夫は、左右の腕を持ち上げ、力こぶを作るポーズをとってみせた。彼が腕を上げ下げする度に、椅子がギシギシとかすかな音を立てる。
その姿を見て、ハルは、右手で口を覆うような、女性がよく見せる仕草をとりつつ、クスクスと笑った。
「茂夫さんって、本当にいつもお元気ね。でも、決してご無理をなさらないようにして下さいね」