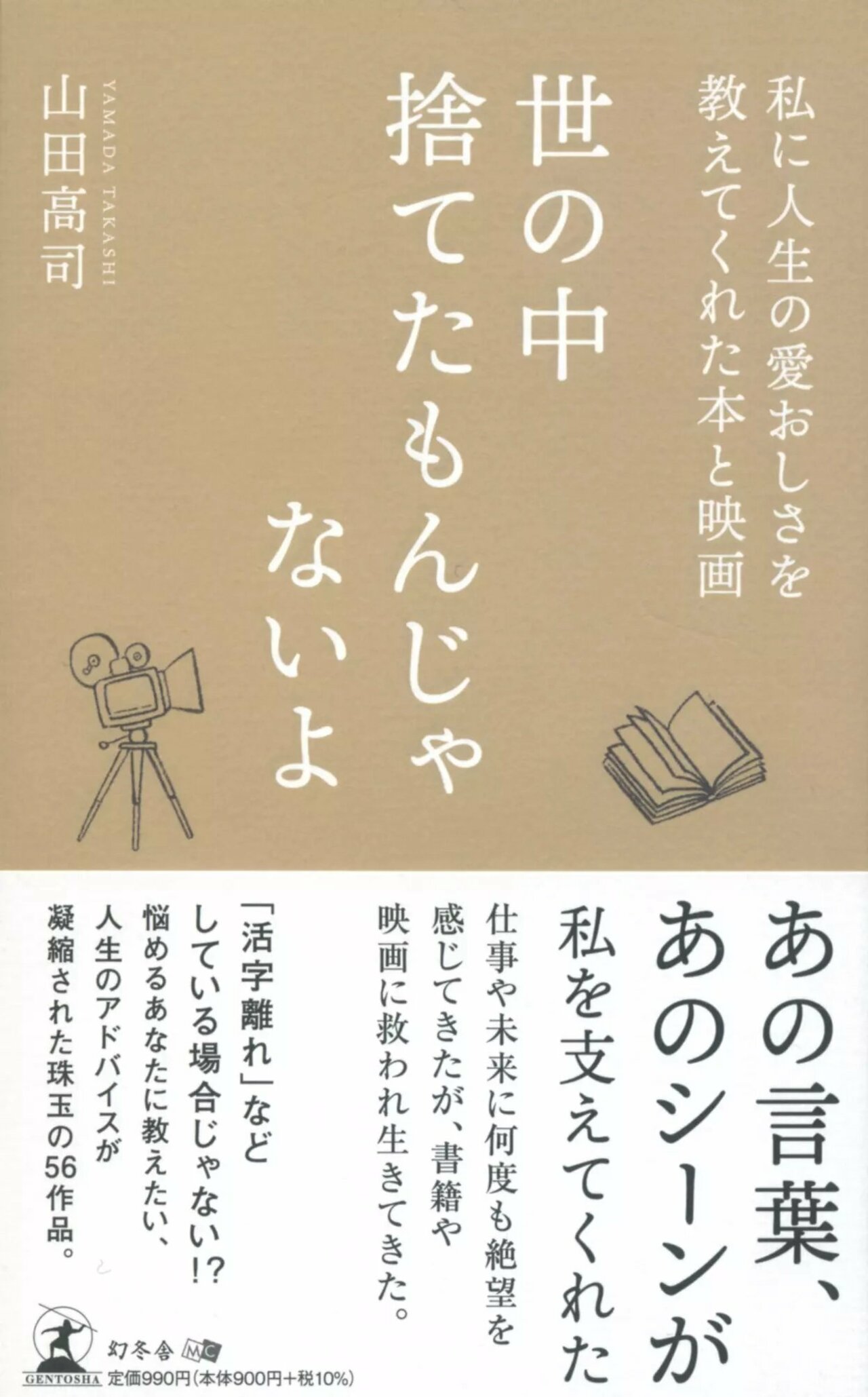『青べか物語』山本周五郎 新潮社 一九六四年
大正末期の社会、貧困、刹那主義、それでも生きる
大正の末頃、千葉県浦安市(小説の中では浦粕町と言っている)が舞台の物語。浦安といえば今や巨大なテーマパークができて大層な賑わいとなっている所だが、当時は釣宿と貝の缶詰工場と、その貝殻を原料とした石灰工場くらいしかない寂れた場所だったようだ。
主人公である「蒸気河岸の先生」は作者山本周五郎自身ではないかと思われる。作者自身がそこで暮らし、ふれあってきた町の人々やその地域について書いた小編三十三話により構成されている。そう言ってしまうとドキュメンタリーなのだが、その地の暮らしを見聞きして空想を膨らませたフィクションとも言える。
大正の末というと今から九十年ほど前のこと。今とは異なり、人々は経済的には相当貧しい。しかし、必死に生きていく姿が文章からあふれている。
「青べか」とは漁に使う小舟のことだ。物語は主人公が村の老人から「青べか」を売りつけられる所から始まる。不格好であり、老朽化している「青べか」を法外な値段で押しつけられる。ここに住む人たちの狡猾さやしたたかさに気後れしながらも、多くの人達と接触していき、その各々の持つ物語を掘り起こしていくのだ。
ここで生活している人々は全然スマートでなく、泥臭く、礼儀正しくもない。しかし、そんな中から「蒸気河岸の先生」は素晴らしく良い部分を見つけだしていく。
一つ一つの小編は現代とは少し異なる生活環境や人柄などが「素」で表現されており、とても興味深い。また、それらの人々に接する主人公の態度も興味深い。「ごったくや」という飲み屋なのか売春宿なのかわからない店の女給、連絡船や運搬船の船員、地元の若者、そして、一番親しい「長」という名の少年など、それぞれにいろんな鬱陶しい現実を抱えながらも逞しく生きているのである。
「白い人たち」の章では石灰工場の状況が描かれている。掃きだめのようなこの場末のさらに片隅で、男も女も全員裸で貝殻を焼き、全身真っ白になりながら石灰を作っている。そこでは会話はほとんどなく、一緒に働いている者がどこから流れてきたものかも分からない、そこで起きるいろいろな事件。そんな労働の場の情景。
「ごったくや」に金持ちがくると、周囲から女給が、寄って集って金を使わせ、客は身ぐるみはがされてしまう。翌日女給たちは大挙して浅草へ遊びに行き前日に稼いだ金をすべて使ってしまう。なんと刹那的なのか。そんな時代でありそんな世界の物語なのである。