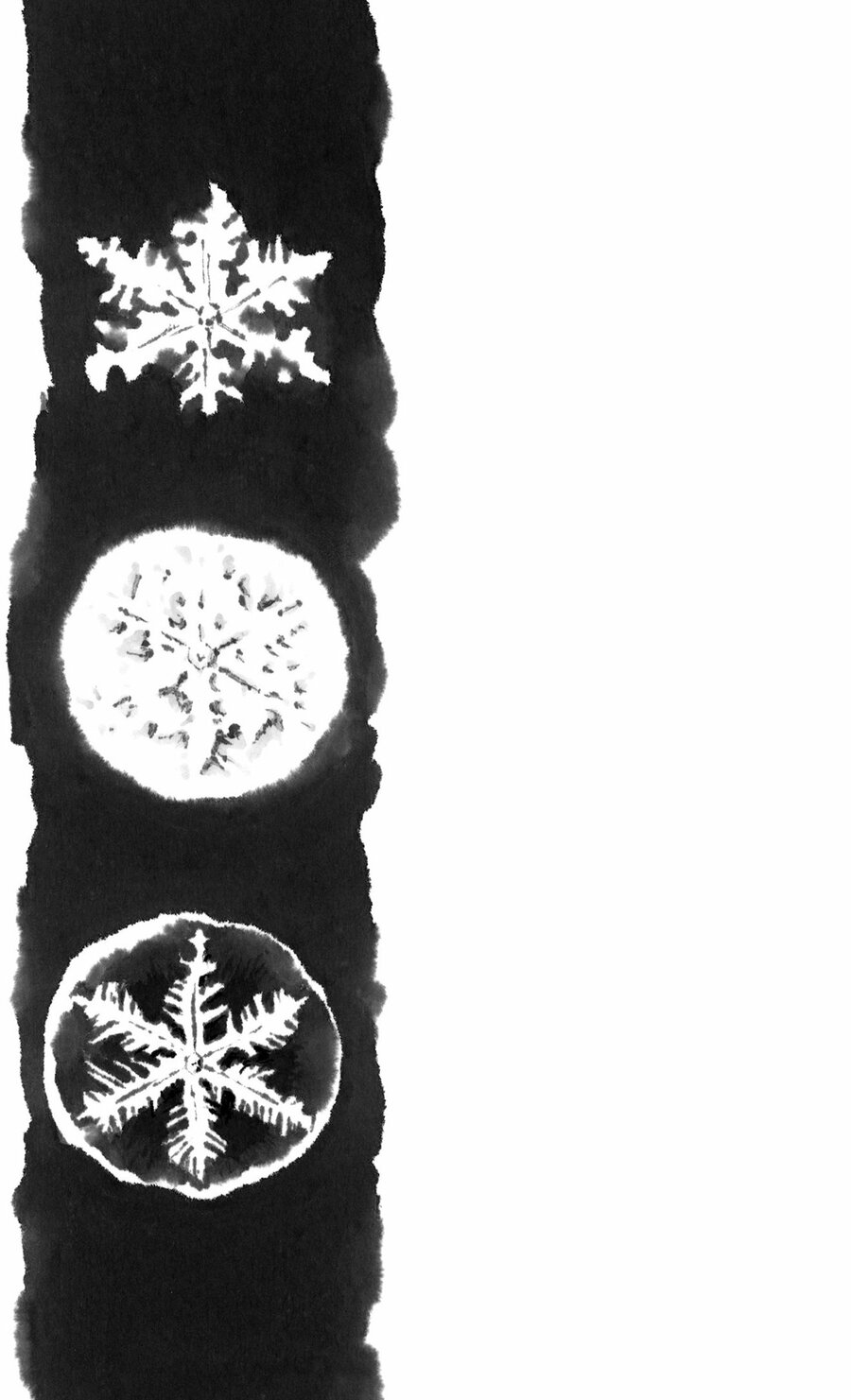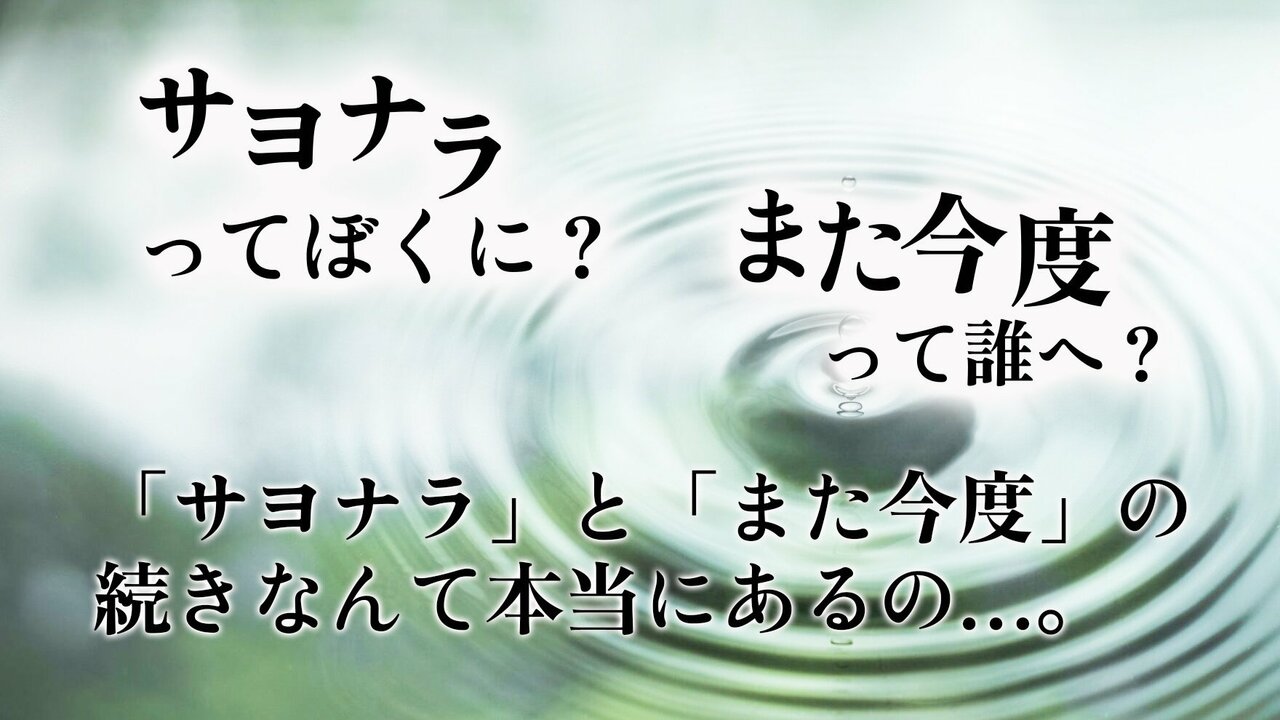(でも、本当じゃないとしたら、みんなはどこへ行ったんだろう?……)
ひとしずくは泣きたくなりました。兄弟たちの行方を考えても考えても、結局答えはわかりませんでした。みんな一様に、何者でもない透明な一滴になって、そしてそれきりただ落ちる。それから、そのあとは……? 兄弟たちは笑顔でここから旅立っていったけれど、本当は何も知らなかったんじゃないかしら。とてつもない恐怖がひとしずくを襲いました。
いずれ自分にも必ずそのときがやってきて突然いなくなってしまう。この逃れようのない運命に打ちのめされてしまったのです。不安は粗暴なまでにますます黒く膨らんで、ひとしずくのからだを翳らせてゆくようでした。
気付けば、わずかに残っている雪の結晶のひとひらを除けば、ひとしずくのからだはもうすっかり、立派な「ひとしずく」といった体でした。葉を透かして射し込む陽光が透明なからだにぴちぴちと反射して、うららかな早春にふさわしい、とても可愛らしい小粒の滴です。
ところが当のひとしずくにとって、残りわずかな雪の華の断片は、はっきりと目に見える自分の寿命のようでした。それを眼前にしながらじっとそのときが来るのを待っているなんて、それこそ恐ろしくてたまらない。ひとしずくは心底震え上がりました。
それからのひとしずくはただただぎゅっと目を閉じていました。もし自分も兄弟たちと同じように跡形もなくいなくなってしまうのなら、自分が目をつぶっているあいだに、自分が知らないあいだに一瞬ですべて終わってほしい。そう強く願うあまり無意識にそうしていたのです。
もし彼が、人間のような拳を持っていたとしたら握りしめていたでしょう。波紋がひとしずくのからだをゆらしました。またひとつ、自分のからだのどこかがほろりと溶かされくずれたようです。