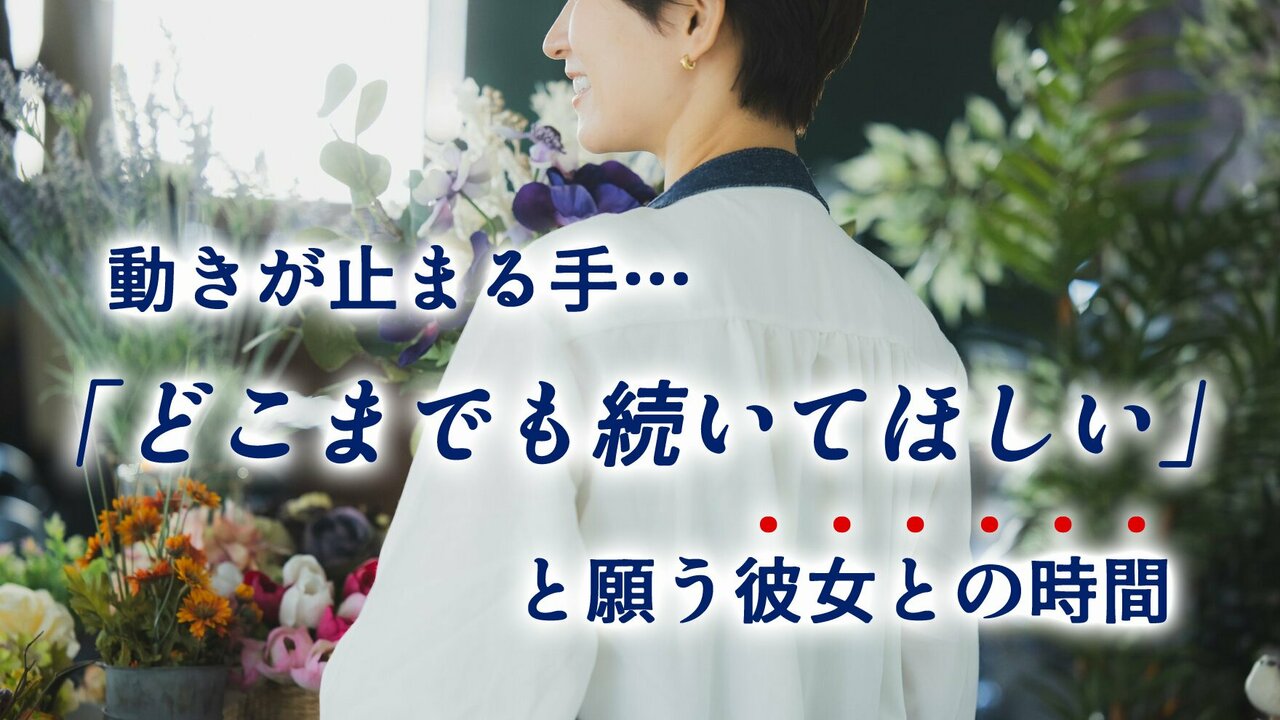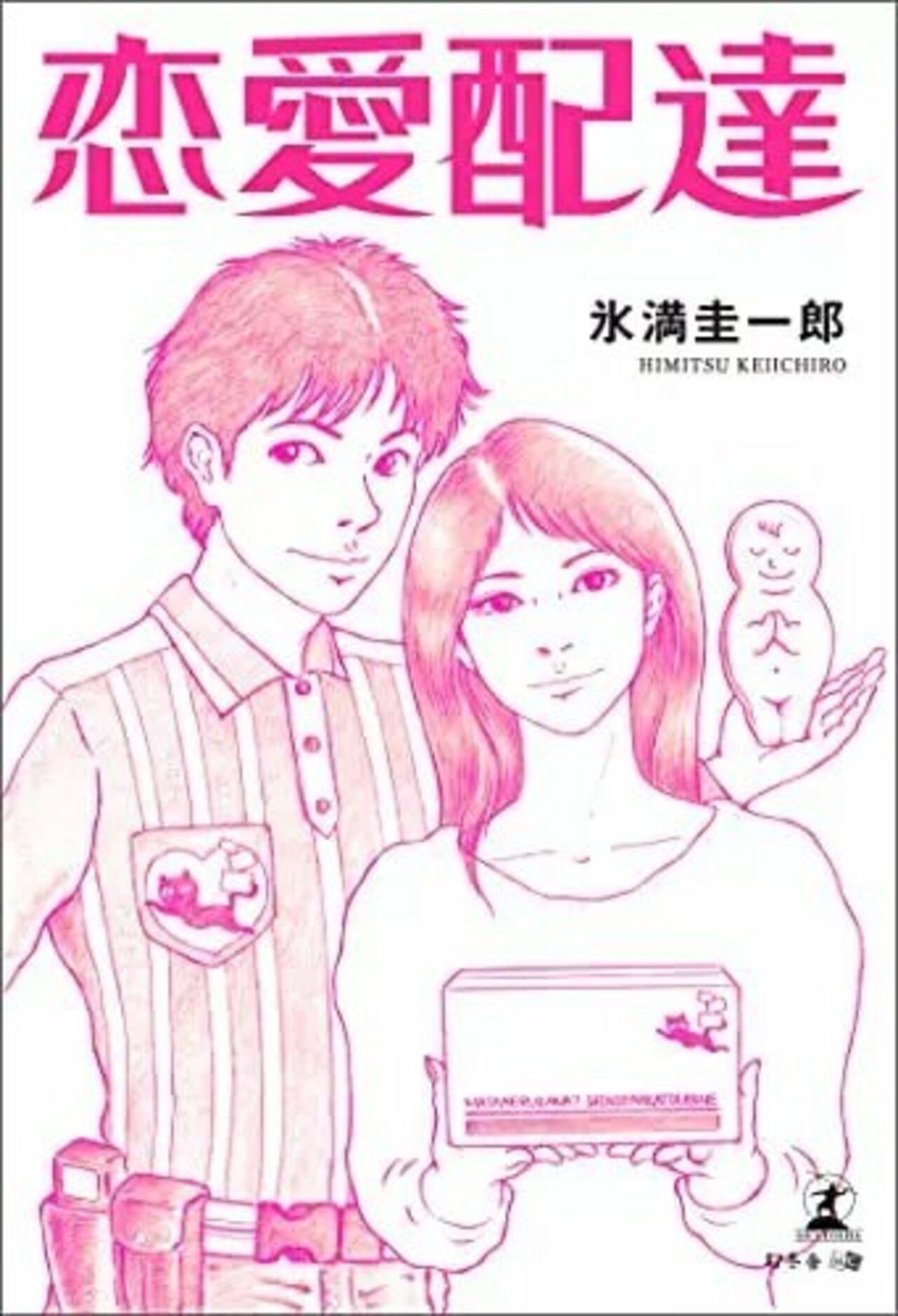【前回の記事を読む】四つ葉のクローバーを簡単に見つける母…「花の気持ちになってあげれば、わかるようになるから」
第一 雑歌の章その一
鵲の橋
いつもなら店先を飾る花は店内に入れられ所 狭しと姿勢よく並んでいた。
傘を差してはいたが、しとど※に濡れていた僕は入り口の傘立てに傘を置き、風が運ぶ雨粒を避けるように勢いよく店の中に入るとあの時と同じ女性がそこにいた。
それに心弛んだ僕を見て、「あら大変、ずぶ濡れですよ。これを使ってください」と言う女性の手には純白のタオルがあった。
「すいません、お借りします」とそれを受け取って軽く頭を下げて挨拶する。
「この間の花をとても大事にしていただいて、ありがとうございました」という女性の言葉にタオルを持ったまま応えられず言葉に詰まりながら、「あぁはい、とても良くしてもらって、こちらこそありがとうございました」と訳のわからない言葉を返してしまい僕は顔を赤らめた。
何を話したらよいか全く頭に浮かばず、花の香り漂うタオルに癒されて沈黙を続けているとそれを察してくれたのか、「今日は大学の帰りですか」と優しく話しかけてくれる。
「いえ、バイトの帰りです」と答えると、「アルバイトは何のお仕事ですか」と再び聞かれる。
「ガーデニングショップで働かせてもらっています」
「花の販売ですか」と聞かれたので首を振り、「手入れや水やりの裏方の仕事です」と答える。
「だから、花の気持ちがわかるんですね」
「えっ、花の気持ち……ですか」
「私、嬉しいんです。彼女たちをそういう方に受け取っていただけると」
前回感じたように彼女に限りなく似ていたし、声も雰囲気も同じで探していた彼女本人に間違いないと思える。そう思うことで幸せが自分を包み込むのがわかる。
彼女もこの女性も近くで相手の顔、特に視線を合わせることはできない。それ以外の女性なら顔を見ても目を見ても普通に話はできるが、その二人だけは特別な存在なのか顔を見ることも目を見て話すことも到底できない。
加えて彼女たちの視線を感じるとヘビに睨まれたカエルみたいに何故か少しも動けなくなる。
前に父親が美しさに定評のある芸能人を間近で見た時に体の自由がきかなくなったと言ったことを思い出した……僕にとってはそれと同じで眩しすぎる存在の二人。
「今日も花をご用意してもよろしいですか」という聞き覚えのある声で現実に引き戻され、「お願いします」と視線を合わせずに俯いて答える。
「今日の体調はいかがですか」と聞かれたので、「とてもいいです」と答えた。
「気分が落ち着く花と明るくなる花のどちらを選びますか」と言われたので、「今日は明るくなる花をお願いします」と前回と違う答えをしてみた。
女性は花に声を掛けながら店内をゆっくりと一回りして戻ると、「今日はこの花がいいかな」と勝手知ったる声で黄色い花を選んでくれる。
「選んだのはご存じだと思いますが、私の大好きなヒマワリです。こちらでよろしいですか」と聞かれたので、「お願いします」と僕はそれに頷いた。
※ しとどとはびっしょり濡れる様子。