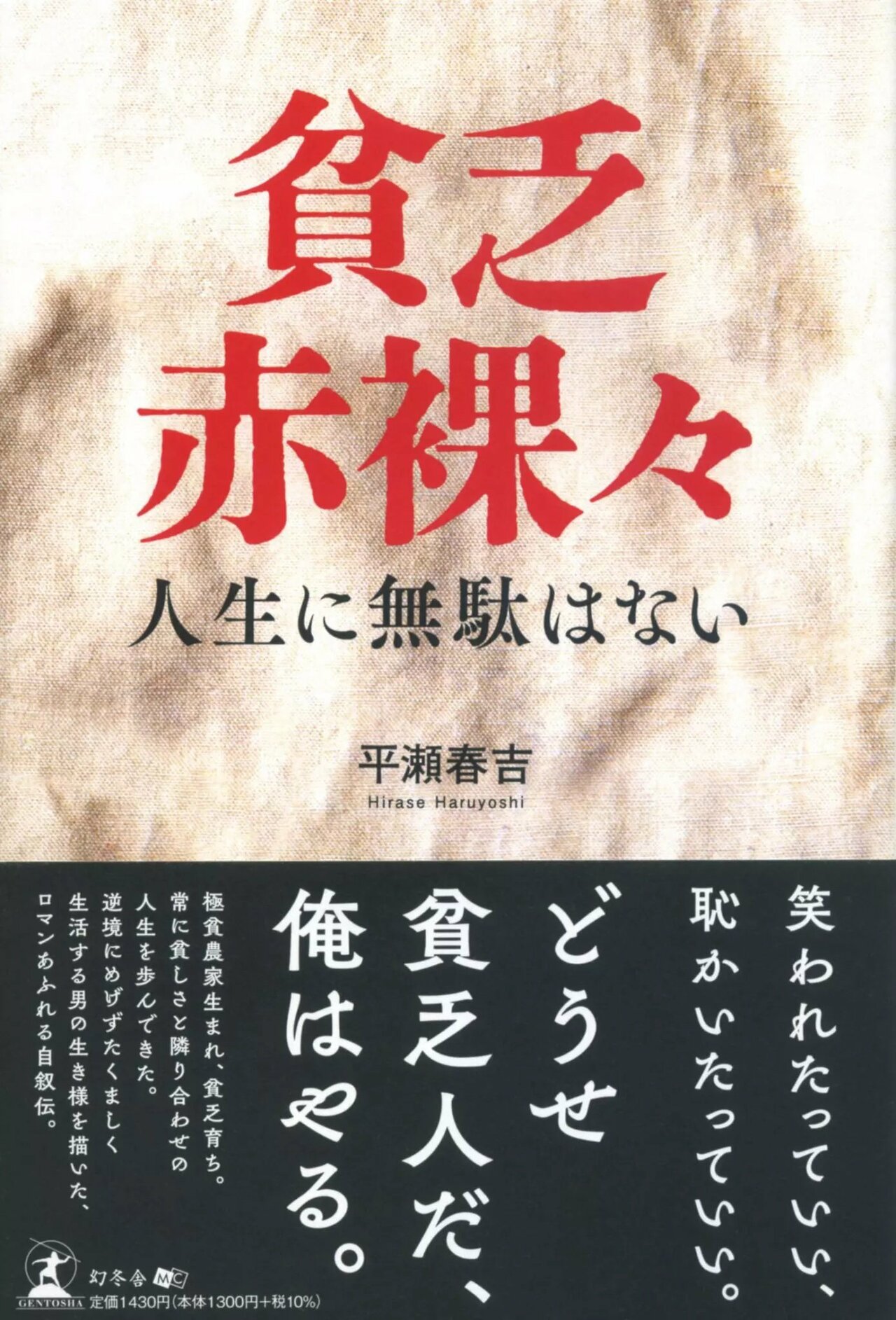その後住んでいた家は、地面に穴を掘って丸太を埋めた掘っ建て小屋で、壁も屋根もワラぶき。納屋も続きで、トイレの入口はワラで編んだムシロを下げていた。火事から立ち直れないまま、八年間も住み続けたのだ。村で母屋がワラぶきは一軒だけで、極貧そのものであった。
雨が降ると、あちこちから雨もりがした。洗面器など、いろいろな器で受け位置をずらすと音色が変わり、聴き入っていたものだ。ポツンと一軒家に非ず“ポツンと貧乏家”であったのだ。小学三年生のとき、掘っ建て小屋が大きく傾き危険なため、すぐ横に建て替えた。
土台付きで屋根は柾ぶきになったが、壁は内も外も土壁。建坪七坪トイレは別にあり、ワラ囲いだった。居間以外は天井が無く屋根裏の垂木や柾ぶきが丸見えで、冬は霜で真っ白になる農家の納屋と全く同じであった。
私の父親は、お金も無いが財布も無かった。必要もなかったのだ。いつもお金が無いことに加え、衣食住すべてに於いて耐乏生活を強いられたら“極貧”なのである。
飼っていた猫は寒さでストーブにくっつき、白毛を焦がして黄色くなっていた。居間が寒くなると猫は私たちが寝ている布団の隅を頭で押し上げながら入ってきて、ゴロゴロ喉を鳴らす。抱いて寝ると温かかった。布団はねずみ色の濃いボロ綿で、綿があちこちでダンゴになってしまうため外側の布だけの所がスースーして寒く、そこを避けて寝たものである。
私が北海道を離れてからは、何かと両親の面倒を姉夫婦が見てくれた。義兄は古材を集めて親の家を建て、「北海道のことは俺がやるから、内地でしっかりやれ」と言ってくれた人だった。
しかし姉夫婦は若い頃、仕事も住まいも定まらず、苦しい生活を送っていた。父は七十九歳で亡くなったが、墓の建立に丁度のお金を残していたため、義兄と相談して平瀬家の墓を建てた。父は村落で初めて霊柩車に乗せてもらった。これも義兄の特別な計らいであった。
母は無口でおとなしく、人の悪口を言ったことがない。不平不満をこぼしたこともない。人から何を言われても言い返すこともない。痛くて顔をしかめていても痛いと言わない人で、我慢強さは度を越していたのだ。人並み外れた貧しさにも、このような母だから耐えられたのだと思う。
ひらがなしか読めなかったが、毛糸のクツ下やモンペなどを手作りしていた。父が亡くなった後、養護ホームで二十年間お世話になったが、根気の要る手作業が得意であったため、多くの作品が展示されていた。母は九十二歳で亡くなったが、年金が貯まっていたため姉と分けて、ありがたく仏事に使った。
大雨に宮沢賢治音を上げる