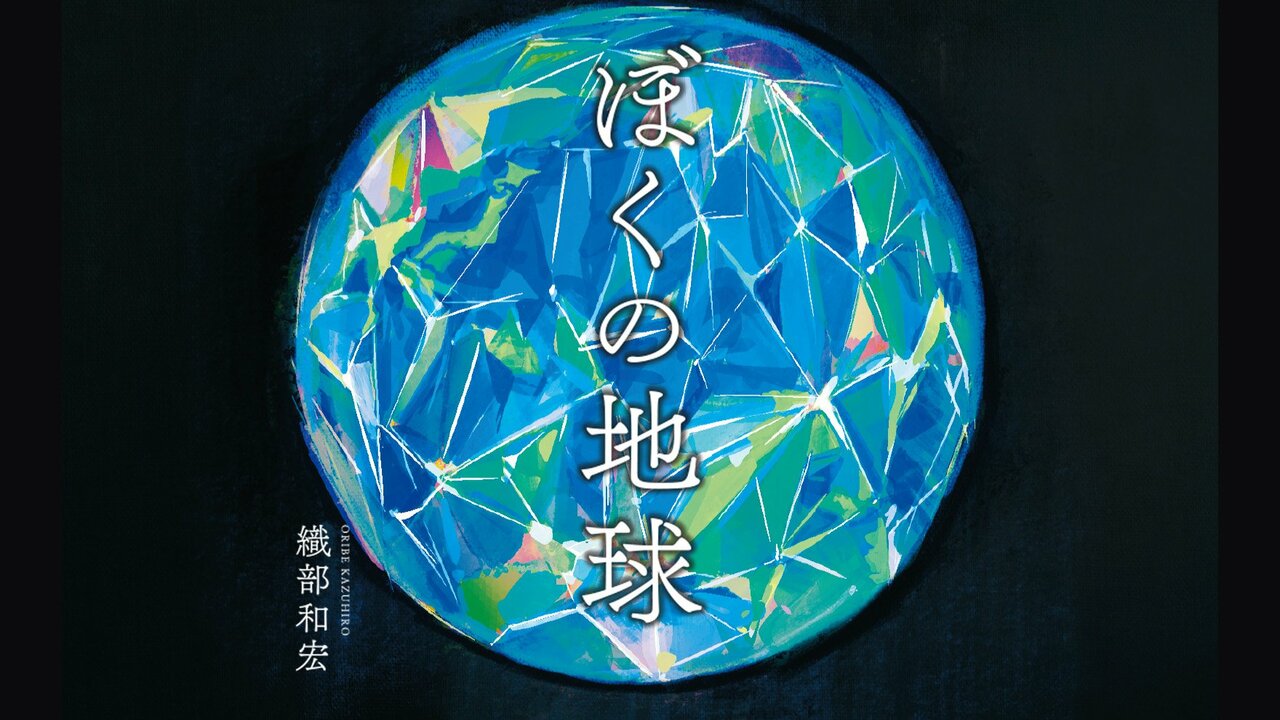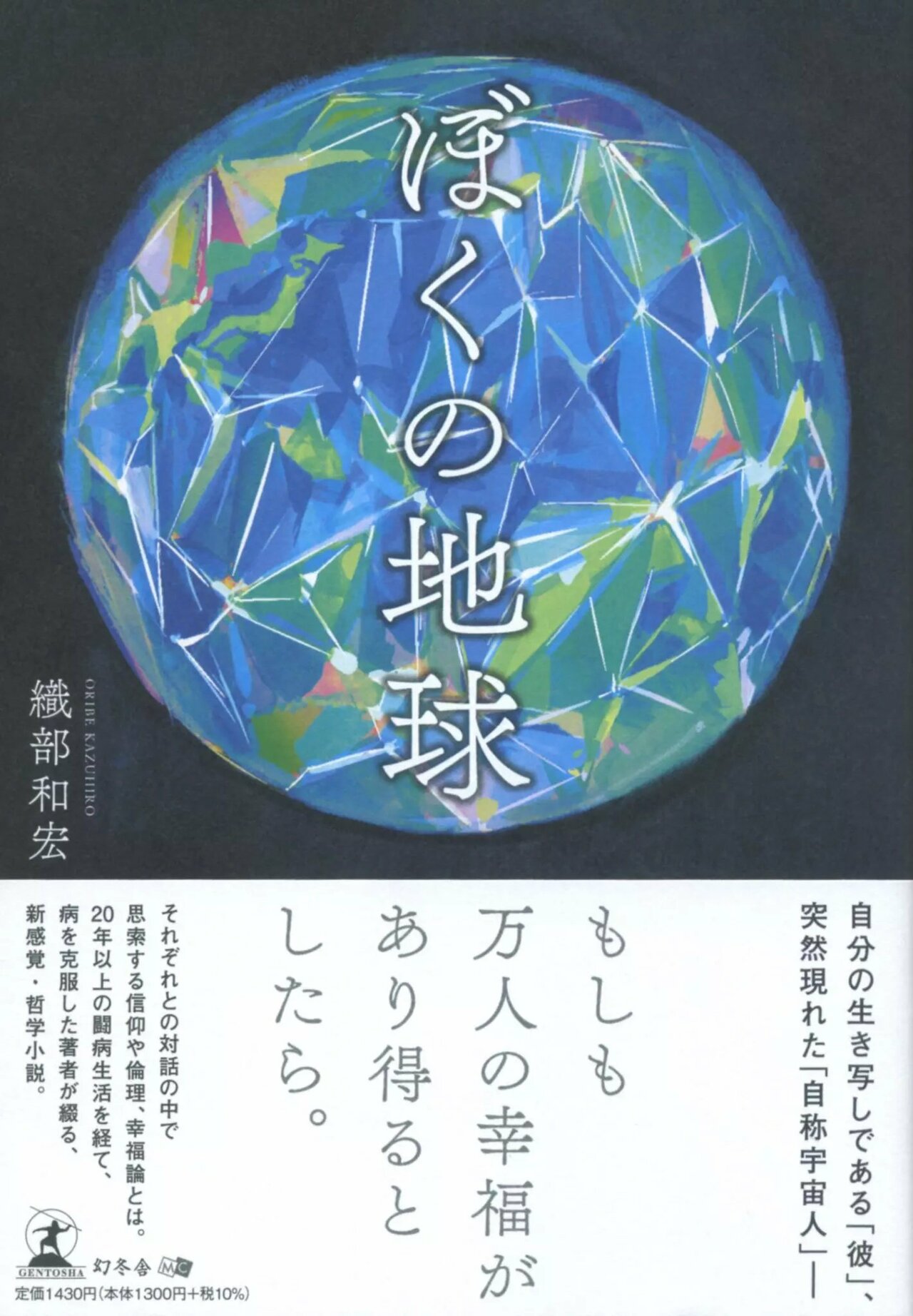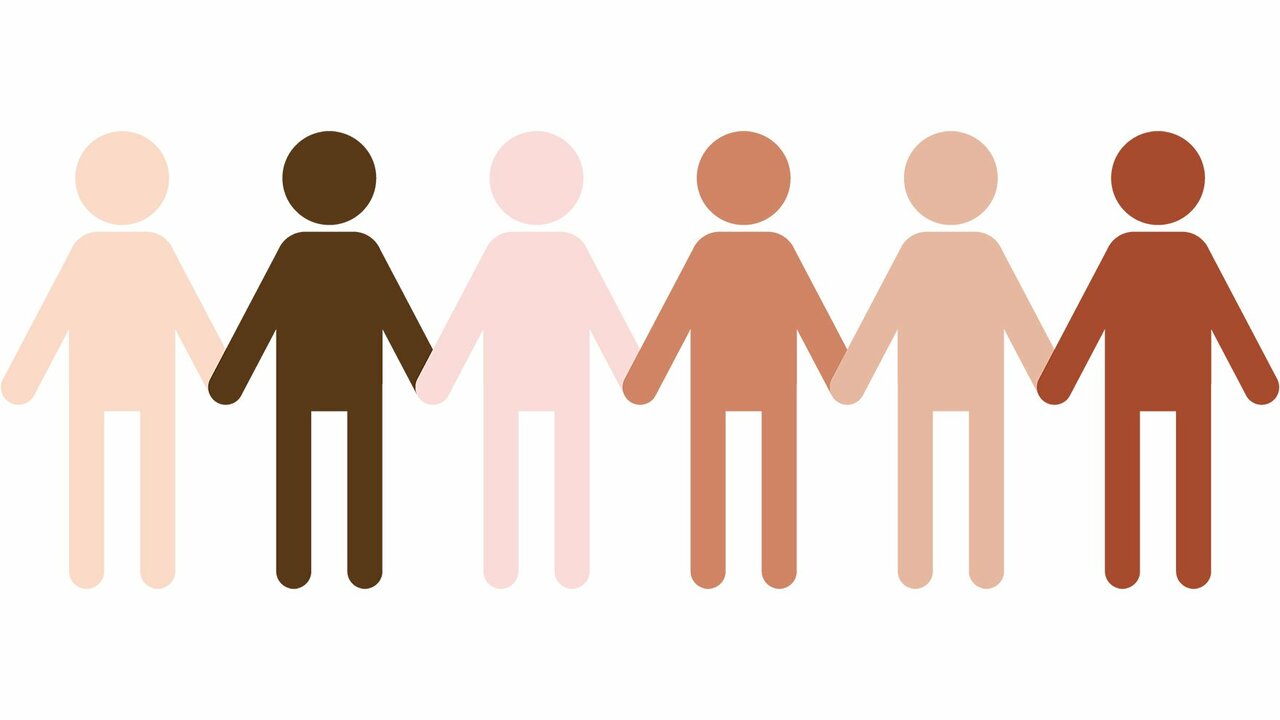ぼくの地球
第一章 目覚め 春
私が彼を最初に見た時、すでに彼はごく平凡な動作の後に、実に象徴的な対応を自身に義務付けているように見えた。そして私は、彼がある一定の法則のもとに、おそらくは原則的な動作を、おそらくは日々繰り返しているに違いないことを、極めて短時間の裡に見抜いた。
彼の一連の動作は、模範的と称されるべきものであるにもかかわらず、私の目から見てもある種の特殊性を帯びており、故に私が彼を知ってから数週間のうちにも、彼とまったく同じ動作を日常的に反復している人をついに見ることはなかった。
お断りしておかなければなるまい。彼は何らかの特別な技術を用いて、彼が果たすべきと考えている動作を完了させたわけではない。その時ペットボトルは極めて自然な一連の動作の後、コンビニエンスストアのごみ入れに収まり、彼は何事もなかったかのように、その予定外の対応から本来の対応へと素早く意識の切り替えを行っていた。そう、彼は道端に落ちていたペットボトルを拾い、然るべき対応で最もよい結果を出しただけなのである。
ここで確認しておかなければならないのは、彼の極めて自然な一連の動作が、彼の行動の非特殊性をよく表しているにもかかわらず、すでに私は去っていく彼の背中に、体系づけられた善的な個性を見出し始めていたということだ。
なるほど、ここはもう少し補足が必要な部分であろう。だが私は、彼の動作に習慣とはまったく別個の、つまり意思に基づくオリジナルの閃きを感じた。ここは極めて主観的な部分であるために、疑問を差し挟む人がいたとしても、ここを論理的に説明するのは難しいであろう。
だが(すでに述べたように)彼は若い頃の私に、その時点においてすでに似ていた。そして私は、そのことを敏感に感じ取ることができた。誰でもそうであろう。かつての自分とは、その生活が順調であったにせよそうでなかったにせよ、現在の自分に常に何らかのシグナルを発信し続けているものなのである。
したがってそこに、容姿はともかくインスピレーションの範囲内において肯定的(時に憐憫が混ざる)に解釈されるべき何らかの感覚のゆらめきが入ることは、何ら不思議なことではないのである。ここでいうかつての自分とは、言うまでもなく最も感受性の強かった頃の、つまり青春時代の自分のことである。