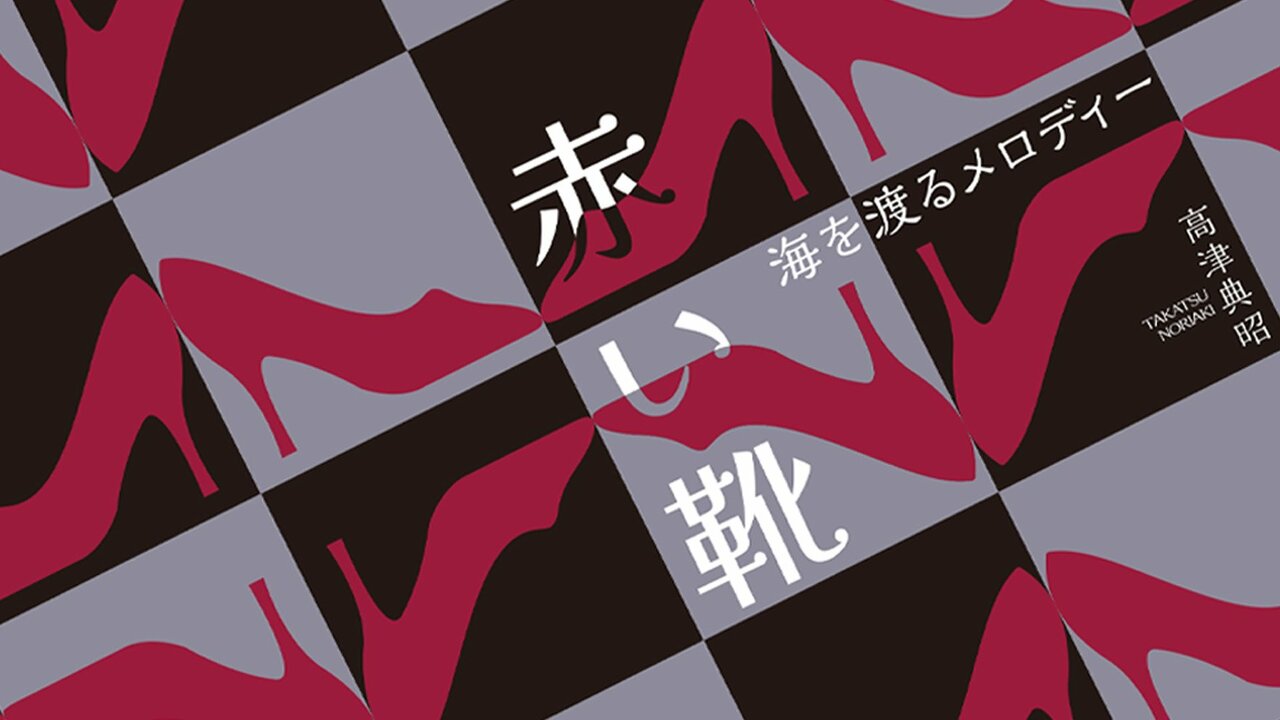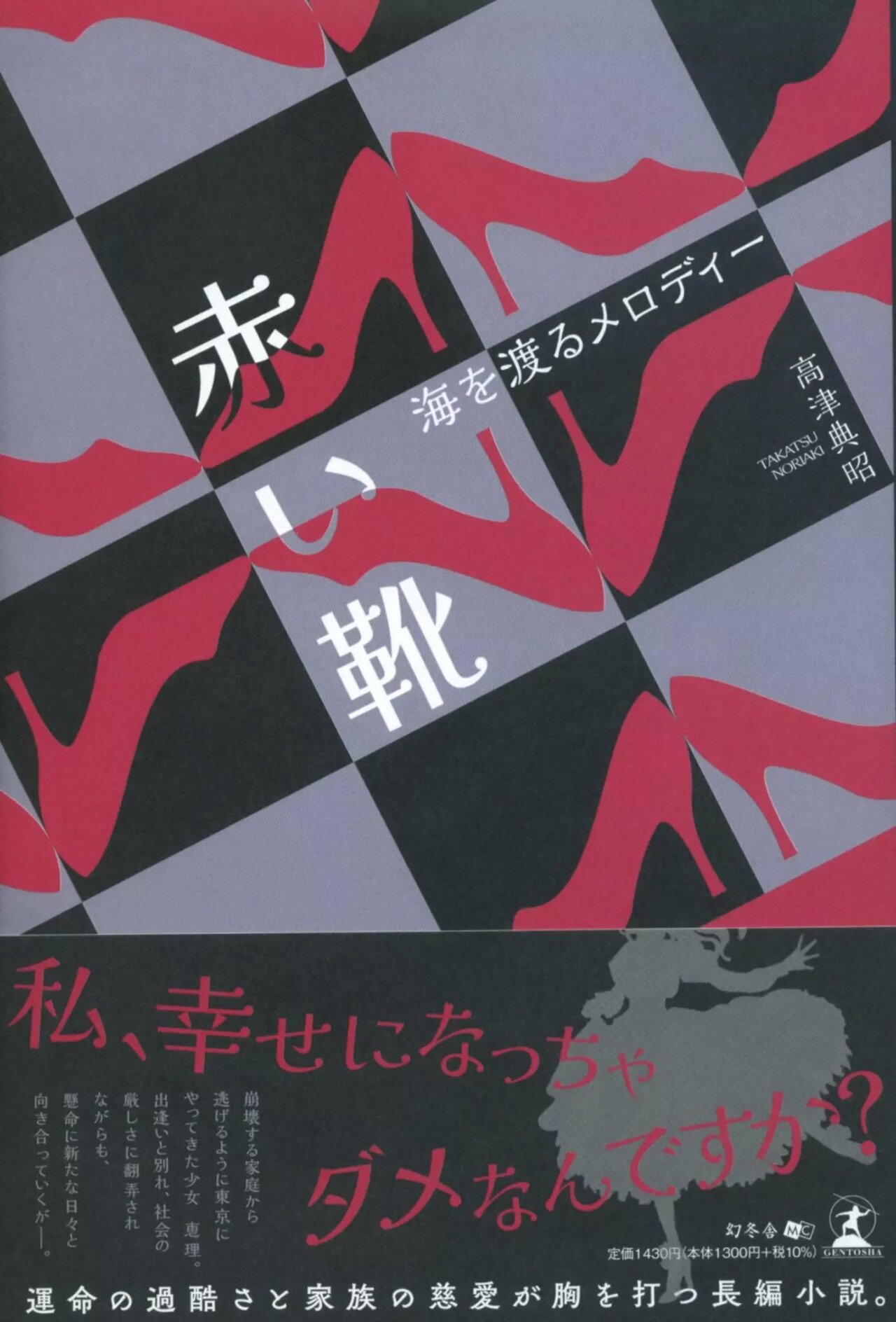第一章 壊れた家族
さて、ここまでの話をしよう。恵理は八丈島から更に南東95キロメートルの位置に浮かぶ絶海の孤島といわれる沖ヶ島で仲の良い両親の長女として生まれた。なお、次女は生まれたものの幼くしてこの世を去ったので、恵理は一人っ子として大切に育てられた。父も母も力を合わせて一家をしっかり作り上げていった。
絶海の孤島沖ヶ島は伊豆諸島の離島によくある火山島である。歴史的に見ると、海底火山が隆起して出来上がった島であり、島の周りは断崖絶壁で、山がちで平野は少ない。ただし、沖ヶ島の西方にあるやはり絶海の孤島といわれる青ヶ島のようなカルデラはない。
1か所僅かに崖から海に下りることができる入り江があったため、この島に人が住むようになって以来、漁業が行われていた。江戸時代からは本格的に漁船を入り江の奥の岩に繋ぐようになり、漁業を生業とする家庭もできた。ただし、小さな入り江なので小さな漁船しか停めることができないため、荒波の太平洋に漕ぎ出せる日は年間100日を少し超えるぐらいで、半農半漁の島であった。
恵理の父親祐一は漁業で、母は僅かばかりの農地で農業をして暮らしてきた。母は体が丈夫ではなかったので寝込むこともあったが、恵理は大切に育てられた。ただ、裕福ではなかったので恵理は、修学旅行で本土に行くまでは八丈島が唯一の家族旅行であった。それでも、孤島の生活の中、八丈島に連れていってもらえることは嬉しくてしょうがなかった。
本土を直接見たことがなかった頃は、恵理にとって沖ヶ島に2軒しかない店が、八丈島に行けばいろんな店があるので都会だと思っていた。しかし、この平穏に暮らしていた一家に暗雲が立ち込めることになった。