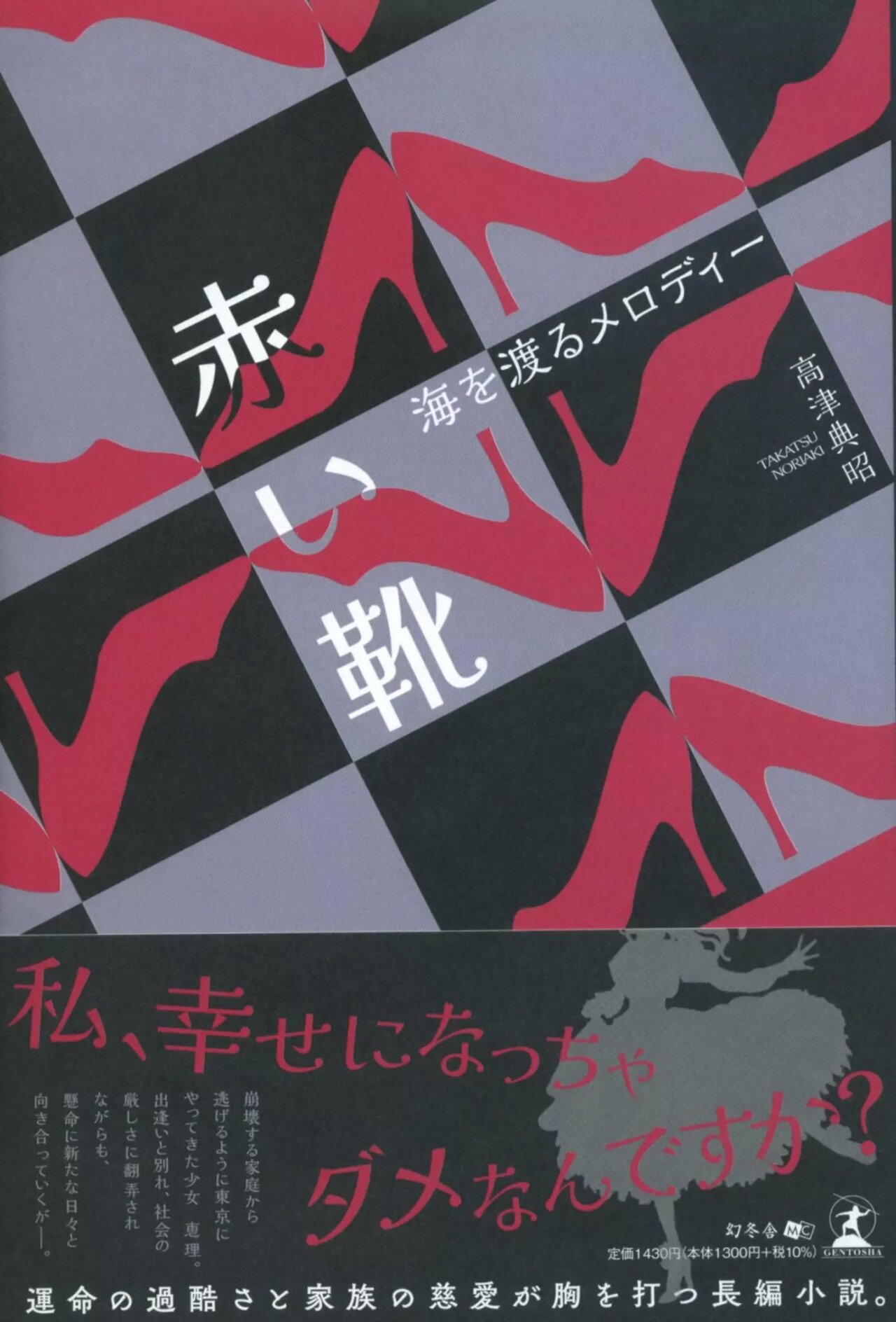父の祐一は、前々から自分が普通の人と違うことで苦しんできた。病院で診てもらったことはないので自己判断になるが、いわゆるパニック障害というものとは違うと思っていた。
祐一は自分が治る可能性のない症状なんだと決め付けていた。更に自分は精神病とは認めたくなかった。認めたくも何も専門の病院に受診したことがないので本来は正式な病名などわかりようもないのだが、この症状を決して他人に悟られないように生きてきたので、誰にもこの症状について話すはずがなかった。
その症状は、中学2年生の時が初めてだった。魂が頭から抜けていくようなというか、何しろたとえようのないほど辛いものだった。もしもこの症状のことを他言すれば、人から人へ伝わり、やがては人類が滅亡することになるから、何とか自分一人でこの症状に耐えてきた。それは辛く孤独な人生になった。
自分が人柱になるんだと思っていた。人類が滅亡するだなんていささか大げさだが、まんざら間違っていない。確かに、この症状を知ってしまった人は間違いなくこの症状になってしまい、耐えられなくて自ら命を絶つかもしれない。それほどひっ迫した症状なのだ。
ひたすら他言しなかったが、他人に知られないでこれまで生きてこれたのには、苦し紛れで自ら見つけた唯一の解決方法があったからだ。この祐一の症状は実際、たとえようがないので、この物語ではこの先、パニック障害とか、パニック発作と表現することとする。