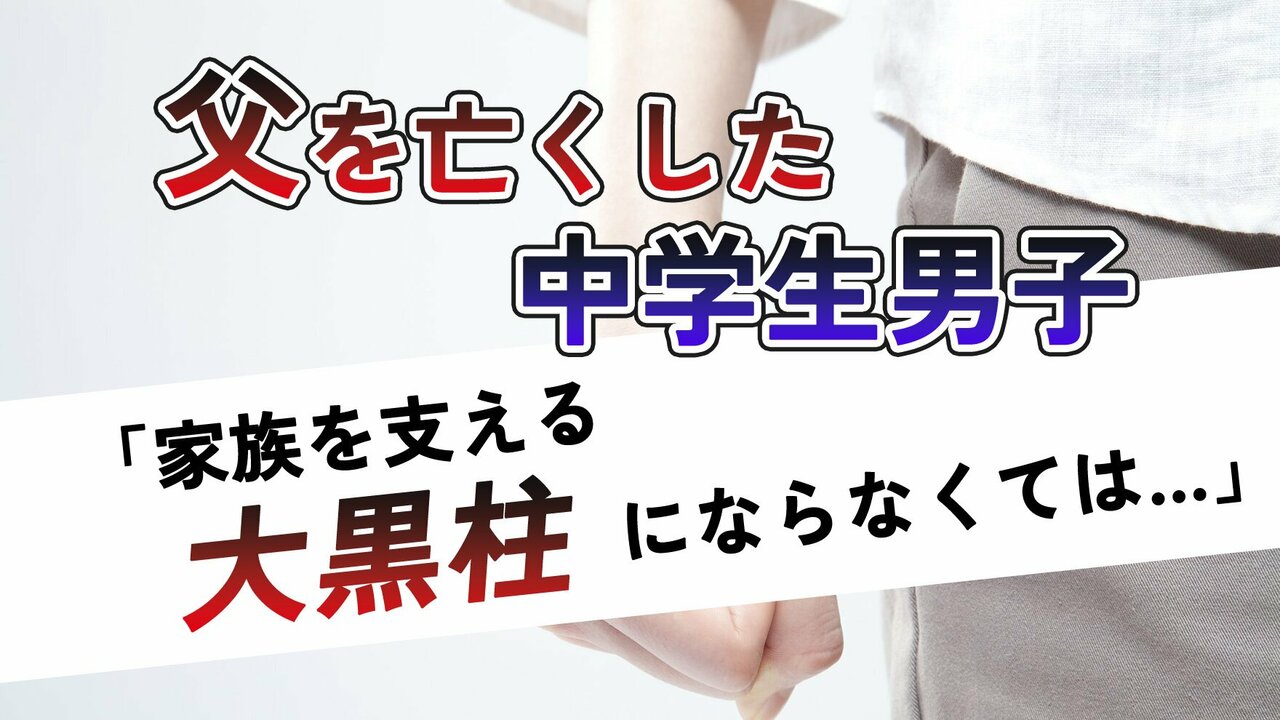第一章 貧しき時代を生き延びて―終戦、そして戦後へ
台湾に生まれ八歳で日本へ
自力で小遣いを稼ぐ中学生
結論を言うと、母の下の妹である「おばさん」が、私の産みの親であった。まだ結婚前、ある男の子どもを孕み、当時のことだからおろすこともできずに、台湾に住む姉を頼って海を渡った。そこで生まれた私を、今の父と母が引き取り、自分たちの子どもとして育ててくれたのだ。だから台湾から戻ってきた私を見て、本当の母であるおばは、あんなにも号泣した。
しかしすでに他の男性と結婚しており、私をここまで育てた両親もいたから、何も言い出すことができなかったのだろう。だからせめてと、お菓子やお小遣いをくれたのだろう。本当の父親の顔を、私は生涯見ることはなかった。
こうした事情は、私が二十歳になったときに母の上の妹であるおばから、もういいだろうと聞かされた。なんとなくそうだろうとは思っていたが、直接身内から話を聞いて、その事情がすべて飲み込めた。産みの母に対して、恨む気持ちはない。しかし特別な愛情が芽生えた、ということもなかった。育ての母をずっと「本当の母」だと思い、感謝をしている。
育ての父に対しては、虐待も受けたし、愛情を与えられたという思いもなかったから、私には父はいないというのが、正直な思いだ。ともかくも、近所の人たちの多くは、うすうすその状況をわかっていたようだから、「もらいっ子」などという陰口を叩かれていたことも不思議ではなかったということだろう。
父の苦しみを思う
さて、話を私の中学時代に戻そう。父は、私が中学三年生のときに亡くなった。中気を患い、最後の一年ほどはほとんど寝たきりであったので、ある程度の覚悟もあった。貧しさもあり、自分たちが生きていくことのほうが大切で、その頃のことはあまり記憶にない。ただ最後は自宅で家族に看取られて、父が息を引き取ったことだけは覚えている。
時代がそうだったと言えばそれまでだが、きちんと病院にもかかれず、突然半身が不随となった父。その後は徐々に残された機能も失われていき、死に向かっていく人生に何を思ったのであろうか。きっと父にとっては台湾での良き時代こそが、大事にしたい思い出であったろう。
しかしそれを抱えすぎて、晩年の不幸があったようにも思う。戦争は多くの人々に不幸をもたらした。そこから這い上がる人もいたけれど、父にはそれができなかったのだろう。貧しい暮らしの中で、中学三年生で父を亡くした長男である私に、高校進学という選択肢は考えられなかった。これから母やまだ幼い妹たちを支える大黒柱にならなくてはならぬと、決意だけは固まっていた。