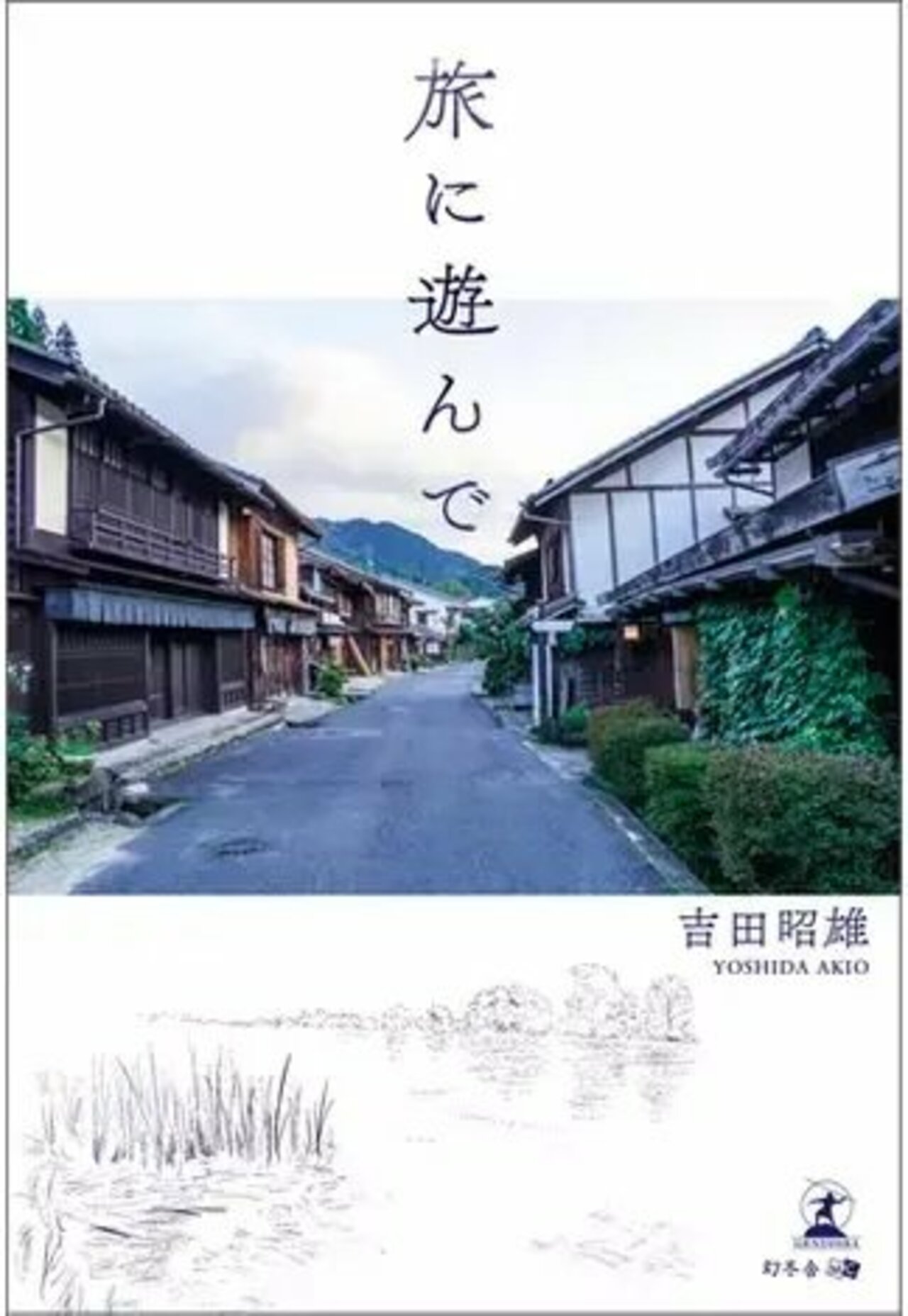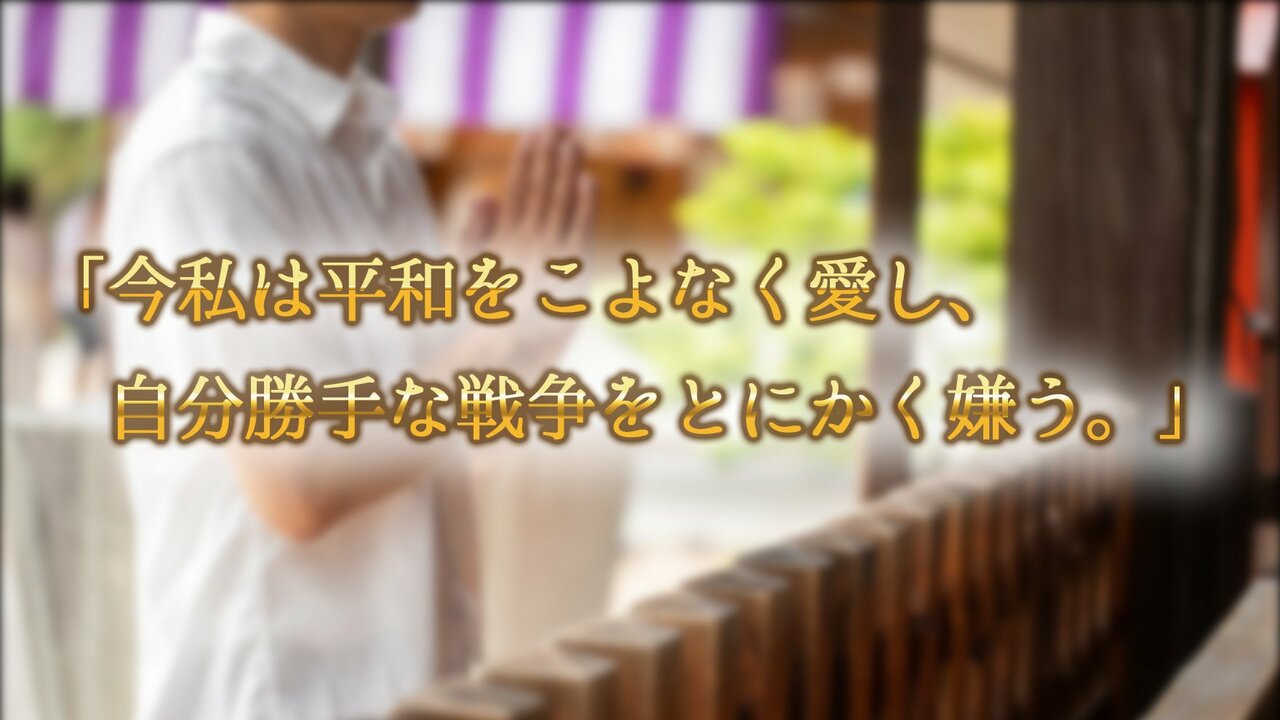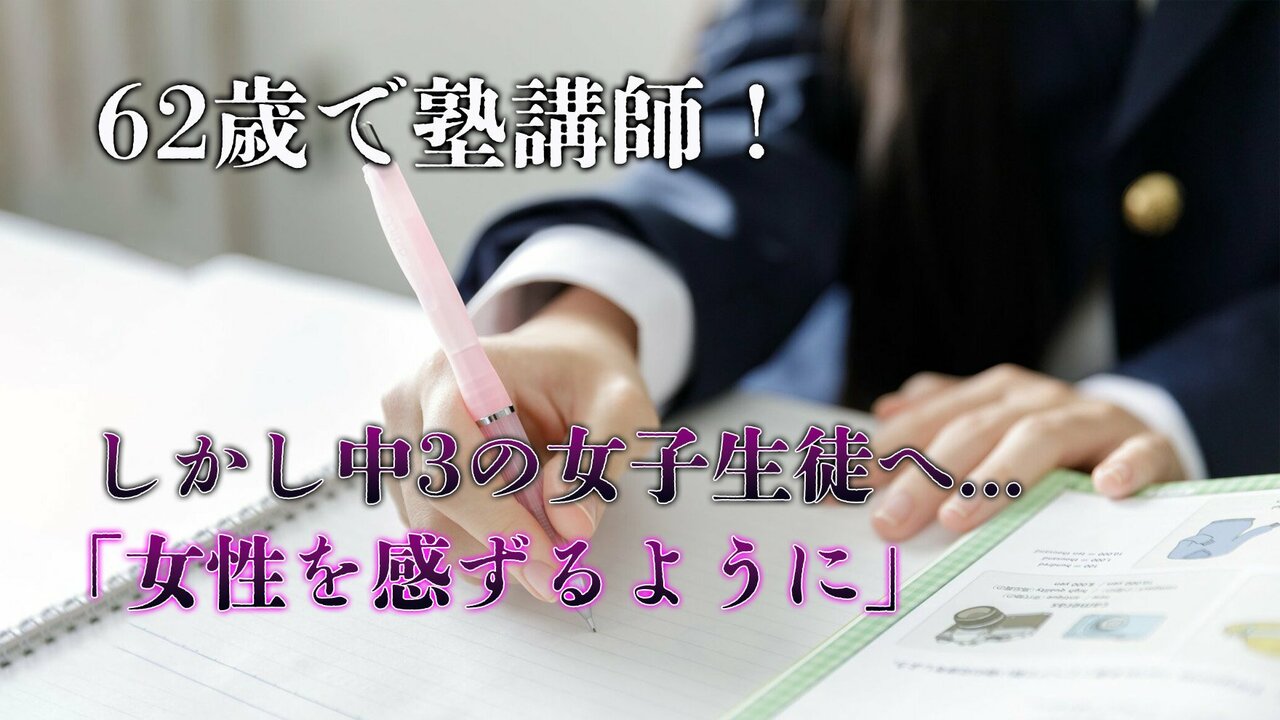第三章 あのころ
香り
「香りゆかしい桐添えて本の字輝る我が章」で始まる私の小学校校歌。今はもう生徒数減で消えてしまった。ただ校歌の石標は残っている。
「桐の香り」とはどんなものか。和風の甘い香りというが中々表現しにくい。桐の花を手に取ると、紫色で真中に薄茶色の膨らみが二つある。平安時代ならきっと小川の流れに身を任せ、恋する人に文と共に流したか。
東伊豆の河津温泉に行けば匂うかもしれない。その近くの熱川温泉に行ったことがある。旅館には桐の木があり、えも言われぬほんのりとした匂いが漂っていた。
「東風吹かばにほひおこせよ梅の花あるじなしとて春な忘れそ」
菅原道真の句が思い出された。露天風呂もある。眼をつむって桐の香りを反芻してみた。
私が何故桐の香りが好きかといえば、祖母の家に青桐の木があり、そこから匂う香りが何とも言えなかった記憶がある。祖母はよくお菓子も出してくれた。幼稚園時代の私はそれが何の香りか判断できなかったし今も不明である。
遠い六十年前の記憶がほんのりと浮かぶ。 梅酢や梅酒の香りも強烈だ。酸っぱいがとても香ばしい。日本人はフランス人と同様に味覚に鋭敏である。こうした幼少期の感性が生涯残るのだろう。これもまた祖母の家での記憶だ。
私は旅が好きで、とりわけ京都はいい。雅な色合いが風景や食物に醸し出されている。旅を求めて春の香ばしい匂いを持っている。春遠しといえども、やがて季節は舞い来る。その日まで家の中で何かの香りを捜そう。
吉田の家紋は花菱である。そして私の数珠は桐の箱に入れてある。いつも良い香りがする。こうして家でも良い香りに夢心地となる。ありがたいことだ。
こういうテーマで香りについて考えてみるのは大変良い機会だ。とても感謝している。