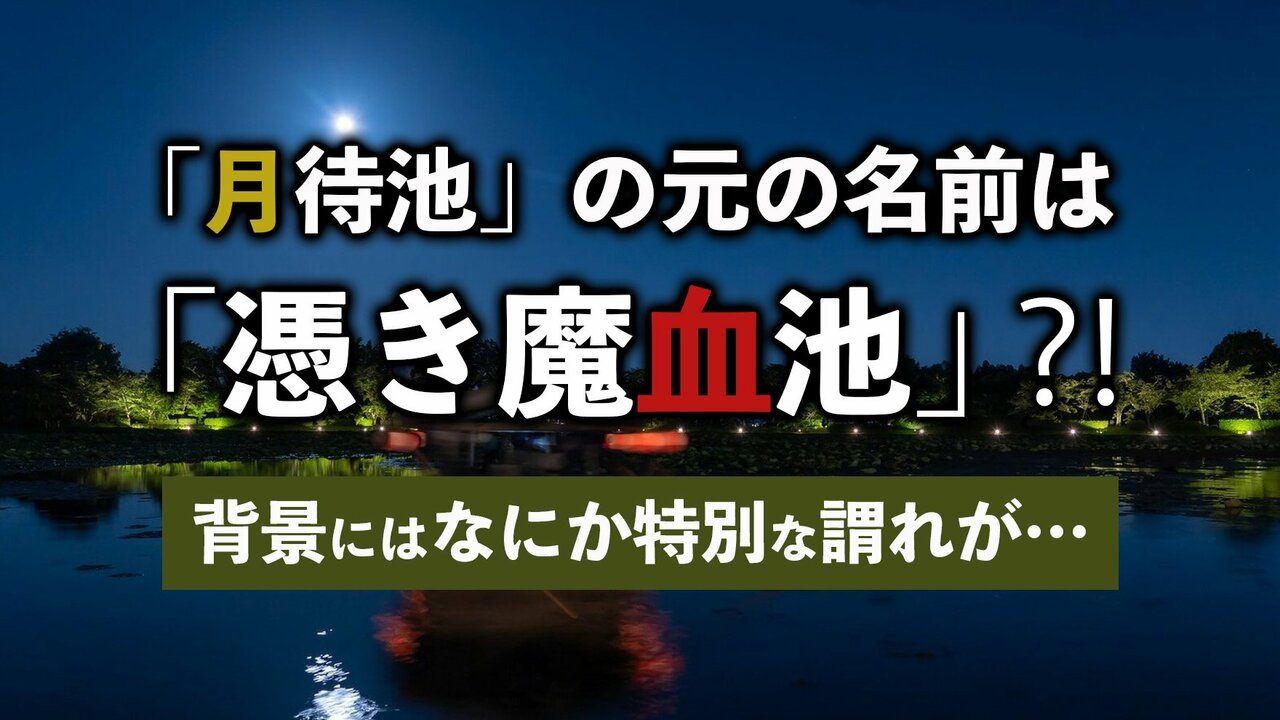第一章 発端
「同人誌というと、たとえアマチュア同士で楽しむためのものではあっても、文字や文章が好きで得意な者たちで構成されているわけですから、校正や原稿チェックはしっかりしているはずですよね。大事な作者の名前が漏れているのを見逃したとはちょっと考えにくいです」
「でしょう? ということは、自分の名前を掲載したくないという作者の意図を、同人誌のメンバーが承諾してあえて伏せたか。あるいは、本当に作者がわからなかったか」
「詠み人知らず、ってことですか」
「そうです。たとえばこの地に昔から伝わっている伝説みたいな詩を、たまたま誰かが見つけてきて載せた」
「何のために?」
「さあ、それはわかりません。ページ数合わせだったり、たまたまその節に詩の投稿がなかったからだったり、理由は案外そんなものかもしれません」
私は次第にこの初対面の老館長と共に、古い書物をめぐる謎に挑戦していく探偵のような気分になってきました。
「それともう一つ。名前の記載がないことにも関連するのですが、佐伯さんは、《聖月夜》の作者は男性と女性どちらだと思われましたか?」
「当然男性だと思いましたが」
私はこの詩を読み、幻想的な月の夜に海の近くの松林に迷い込んで、そこで不思議な少女に遭遇する若い男の姿をごく自然にイメージしていました。作者が女性である可能性など一ミリも考えなかったのです。
「やはり私の見解と一致しています。この詩には作者の名前がなく、そして男性だと明確にわかる言い回しやヒントがどこにも見当たらないにもかかわらず、男性が書いたものだと誰もが容易に解釈できる作りになっているのです」
「そこに何らかの意味があるとおっしゃるのですか」
「それはこれから、あなたと私で解明していこうと思っているのですよ」
硬かった表情をようやく緩めて、浜村さんは悪戯っぽく笑いました。その和やかさに、私は駅で見た例の少女のことも話してみようと思いつきました。
「少女といえば、松林ではありませんが、つい先週、刑部所長と車に乗っている時に、月ノ石駅で中学生くらいの女の子を見かけたのです」
「ほう、あの駅で、ですか?」
浜村さんは意外そうに体を乗り出してきました。
「はい、残念ながら見たのは助手席にいた私だけで、運転中の刑部さんは見ていません。ですが間違いなく月ノ石駅を降り立った少女がいたのです」
「しかしこの駅には中学校も小学校もありませんよ」
刑部所長と同じことを言っていると思った時に、
「ただ昔あった中学が廃校になって、建物だけはまだ残っていますがね。今後その建物と敷地をどうするかが、長年この町の懸案事項になっています」
そうだったのか。やはり資料館を訪れてよかった、と私は思いました。あの少女の正体も、場合によっては《ぱるる》で出会った女性のこともいずれわかるのではないかとの期待に私の気持ちは軽くなっていきました。
「人の乗降はほとんどない無人駅ではありますが、それでも何人かの利用者はいますからね。たまたま佐伯さんが見かけたのがここらでは珍しい年若い女の子だったので、記憶に残っているのではないですか?」
浜村さんにそう言われると、自分がこだわっていたことが実は何でもない日常の出来事のように思えてきました。確かに無人駅から中学生くらいの少女が降りてきたからといって、別に不審なことは何もない、ただそれだけのことですから。