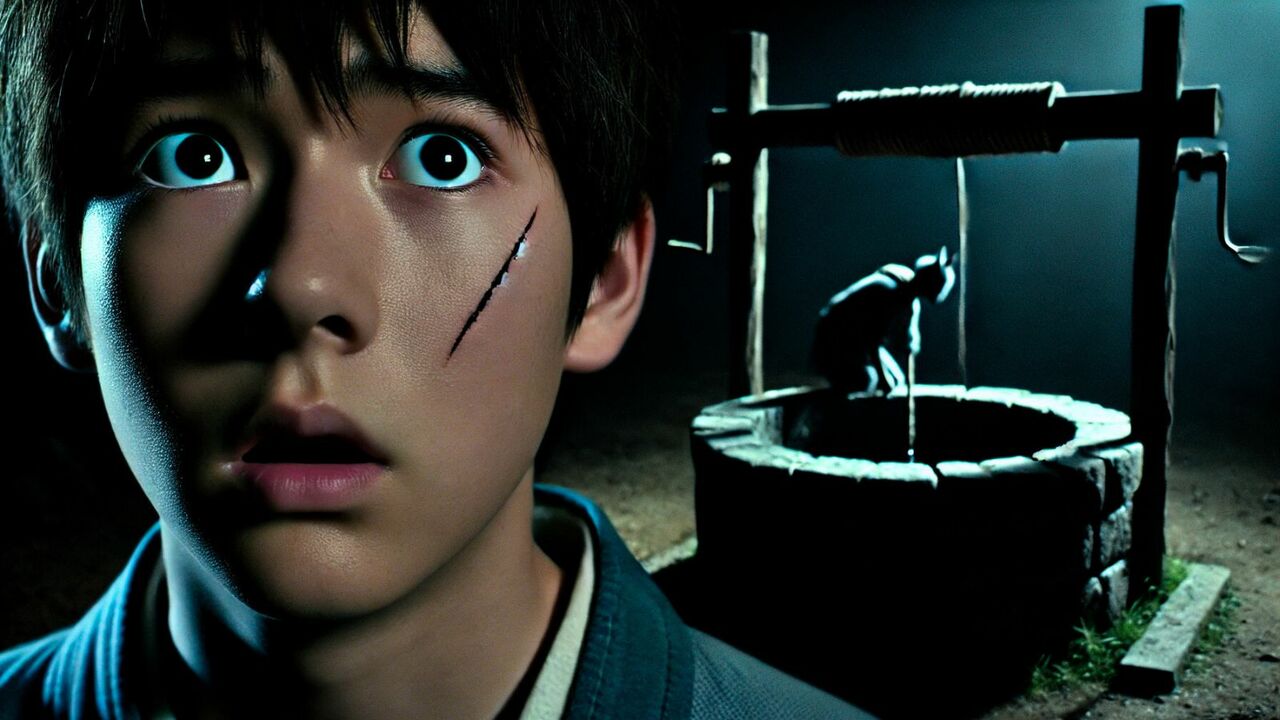そんな中、雪乃は三年ほど前から頭痛や嘔吐に苦しめられる日が多くなった。椚田姫はここぞとばかり体調の悪い母を無理やり歌会に誘ったり、寺社の参拝に付き合わせたりと連れ回し、人の良い雪乃がしきりに遠慮するのを言葉巧みに、時に嫌味まじりに誘い出しては体調を更に悪化させた。
胸の痛みや咳、息切れが酷かった事から、恐らく胚細胞腫瘍であったと思われる。抗癌剤や放射線治療などもちろん無い時代であるから、椚田姫の存在は雪乃の寿命に何ら関係して無かったかもしれないが、苦し気だった母の様子や、それを見て喜んでいる椚田姫を見て、寿命を縮められたと源五郎が激しい怒りを覚えたのも、致し方ないものだったと言えよう。
そしてそのような折も父資頼は他の側室に入れあげていて、雪乃の容態に気を配る事すらなかった。生前、断わり切れない母の代わりに、見るに見かねた源五郎が、
「体調が思わしくないのだから、大概になされよ」
少々きつめに言った事があり、それに腹を立てた椚田姫との間はますます険悪になっていった。天文二年、とうとう母は帰らぬ人となり、それに無関心な父資頼は葬儀に参列する事もなく、家を取り仕切るのが、面倒な……。と言わんばかりに家督を資顕に譲った。
そうなると当主正室の立場から更に源五郎への風当たりが強くなり、謂れのない誹謗中傷を繰り返し、義父資頼と夫資顕の心が、源五郎から離れるように仕向けた。
元より兄弟仲の悪かった資顕は、文武に研鑽を惜しまず、周囲が舌を巻く程の天賦の才、秀でた武芸と恐るべき胆力を垣間見せる弟をやっかみ、恐れと共に妻同様毛嫌いするようになり、当主という座から、源五郎へ嫌がらせをするようになっていった。
法事や祝事の席に源五郎を呼ばず、家臣の前でつまらぬ理由により罵倒を繰り返し、母が死んでからは母親代わりとなって、源五郎の身の周りの世話をしてくれていた侍女の梅を、追放同然に里へ帰してしまうなどという事もした。源五郎が太田の実家で居所を無くし、徐々に荒んでいったのも無理からぬ事であった。
彼はこの湖に浮かぶような浮き城の中で、一人孤独な生活を送っていたのである。