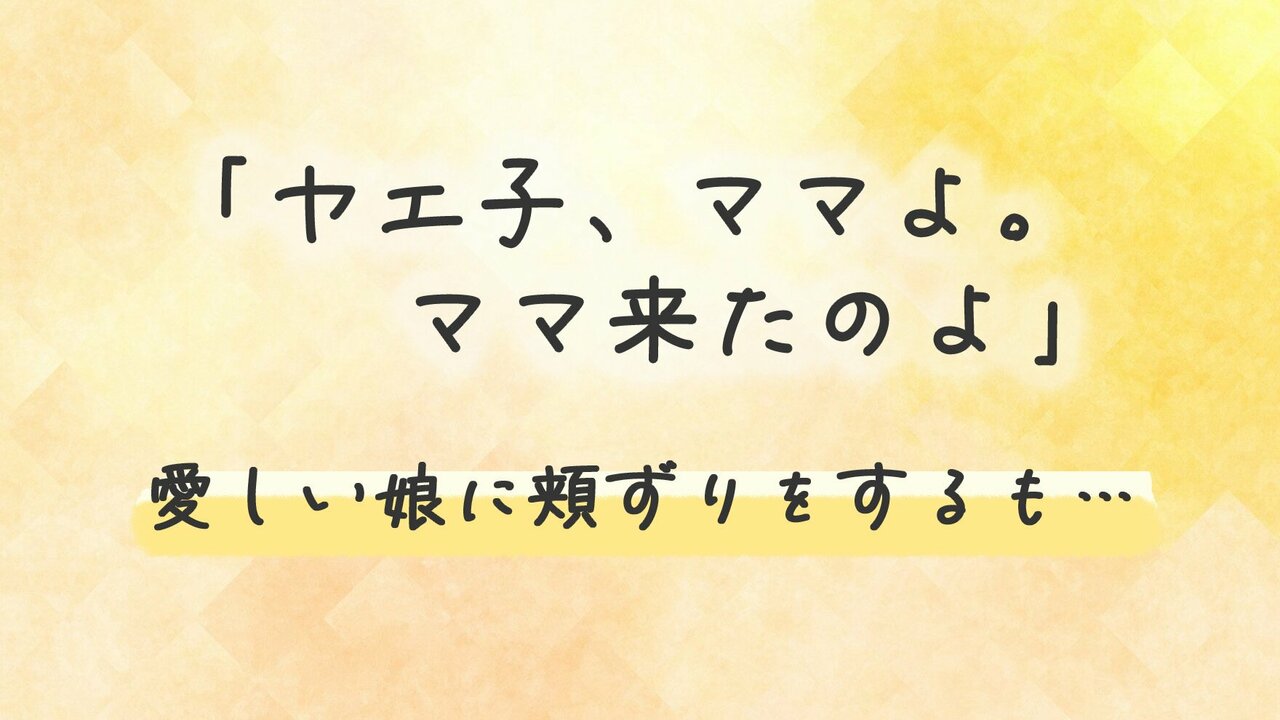花と木沓
九月十日

九月二十日
マリア、クララ、ヤエ子は十才。
メリンスの手まり模様が良く似合う色白の子。
けれど歩む事も、語る事も知らない、歯さえはえていない。
或る日美しい母が泣いて残して行った。
牧場のはて、牛舎のむこうの陽るい小屋に、耳の遠いおばさんの世話で生きている。
野花など摘んでたづねて行くと、おばさんは例の法外な大声で、「ほら見てごらん、あの子があんなによろこんでる…よろこんでる」と云う。
が、ヤエ子はいつものようにベッドの周囲にめぐらされたがん丈な柵をギッシリと、にぎりしめて、壁を凝視している。
手足の引きちぎれた人形が二つ三つ。
あの母が言葉を持たぬ娘の“語り友達”として、あるいは母の身代りとして、想いを、いっぱいに込めて残した人形達であろうけれど、ヤエ子はこれを引きちぎる――。
普段はじっとして、殆んど身動きもしないのに、ひと月に一度程訪れる母が、立ち去った夜は、人形を裂き、柵をへし折り、吠え声を上げて、月の牧場を這いまわる。
「ヤエ子、ママよ。ママ来たのよ」と、何度も頬ずりをしながら「壁をみつめて、……ひとつも動かない……分らないのね」と、涙を流し、子守歌を一日中繰り返して、日暮れ方、娘の腕に人形を抱かせ、細長い影をひきづって帰って行く母に、その夜のヤエ子の咆哮を聴かすべきか。
今日もヤエ子のためにミサが行われる。髪にとき色のリボンをかざり、周囲の人々にささえられ祈る形に合わされた小さな手に、ロザリオがゆれる。