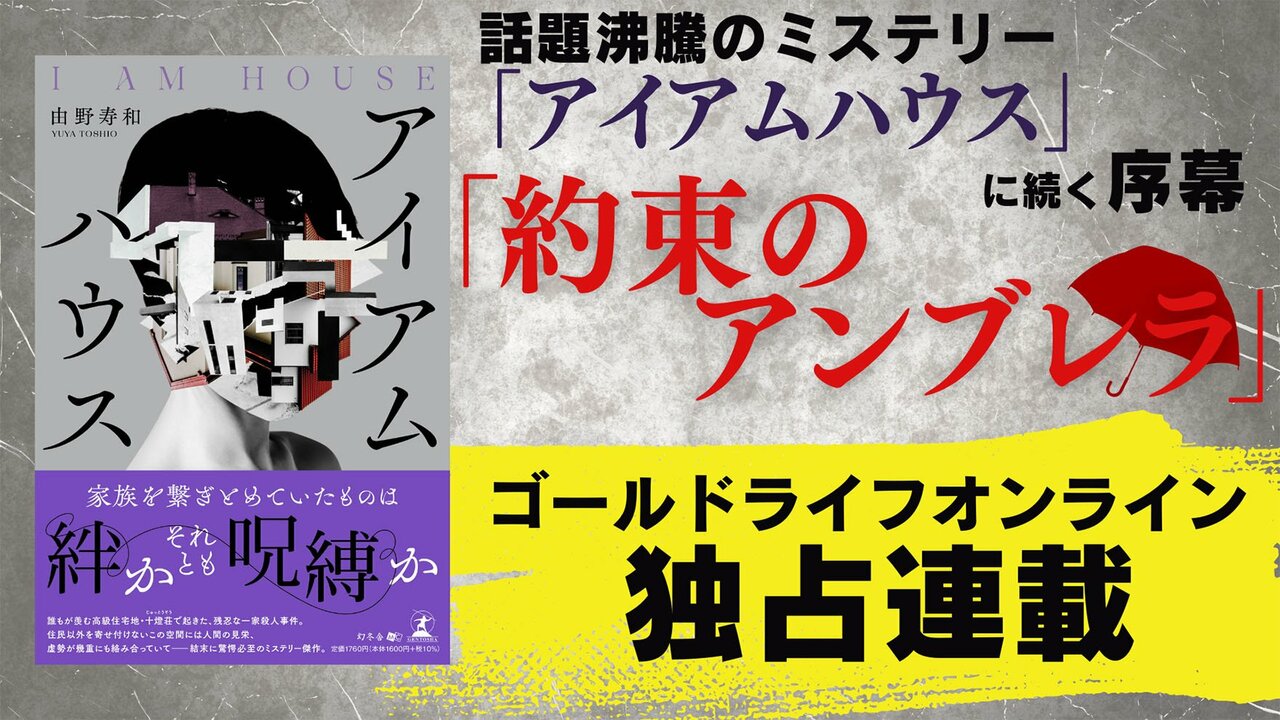二人は窓口でチケットを引き換え、顔写真を撮影し、大きな入場ゲートを抜けた。そこは現実とはかけ離れた夢の国だった。猫だの犬だの個性溢れる着ぐるみキャラクターに、笑顔が形状記憶化しているスタッフ達。古いとはいえ定番のアトラクションの数々に思わず目を奪われる。
仲山はまるで少年に戻ったかのように胸を躍らせた。いや、何よりも娘といられることが嬉しいのだ。
ドリームランドは入ってすぐの正面に大きな噴水があり、その周りをなぞるかのように黄色い水仙の花が並んでいる。その奥には『愛の台地』と呼ばれる場所があり、ランドマークである『ドリームアイ』が圧倒的な優美を見せつけていた。
「凄い、思ったよりずっと広い。それに、海外からのお客さんもいるな」
「そうだよ、夢の国ドリームランドだもん」
「凛も知ってるのか」
「うん!」
「でもな、お父さんも徹夜で勉強してきたんだ。ほら見てみろ、まずこのまま直進して『花の祭壇』に向かって、それから『宝の洞窟』のある地下に潜って、そこから『愛の台地』に出るんだ。そして巨大展望型観覧車『ドリームアイ』に乗る、そこでちょうどお昼の十二時に……」
計画は大事だとばかりに、仲山は調べてきた紙を大きく広げて夢中で話し始めた。計画のこととなると周りに気を配れないのは仲山の欠点だ。ふと気付くと凛の反応がなく、気配を感じなくなっていた。慌てて周りを大きく見渡したが、そこに娘の姿はない。
「凛。……凛?」
何度か名前を呼んだあと、仲山の顔は一気に青ざめた。大きく周りに体を振りながら叫ぶ。
「凛!」
ほんの一瞬気を許してしまった自分を恨みつつ、凛、凛、と何度も大きく声を張り上げる。
「どうかされましたか?」
声をかけてきたのはドリームランド園内のスタッフだ。ハンチング帽を被った大柄の女で、表情は朗らかだった。こんな時に何をへらへらとしているんだと仲山は少しイラついたが冷静に状況を伝える。
「俺の娘がいないんだ、小学三年生の女の子だ。黄色いコートを着ている、えーと、マフラーは」
「つまり迷子ですね、わかりました、すぐに専門のスタッフに伝えますので」
「専門? そんなの待ってられるか、俺の娘だ」
そう言うと仲山は走り出した。まるでかつてのトラウマがよみがえったかのように、体が酷く震える。それでも人ごみを掻き分けて走った。
十二月の東京は気温も一層に低まっていたが、厚手の紺のジャケットをはだけさせ、額に汗を光らせながら走り回った。スニーカーの紐が解けそうだが気にも留めない。その時、アナウンスが耳に飛び込んできた。ドリームランドの園内に電子音が響き渡る。
『東京都からお越しのナカヤマヒデオ様、東京都からお越しのナカヤマヒデオ様。娘様がお待ちです。ドリームアイ正面の搭乗ゲートまでお越しください』
迷子を知らせるアナウンスにハッとした仲山は、ドリームアイの搭乗ゲート方面に進路を変える。