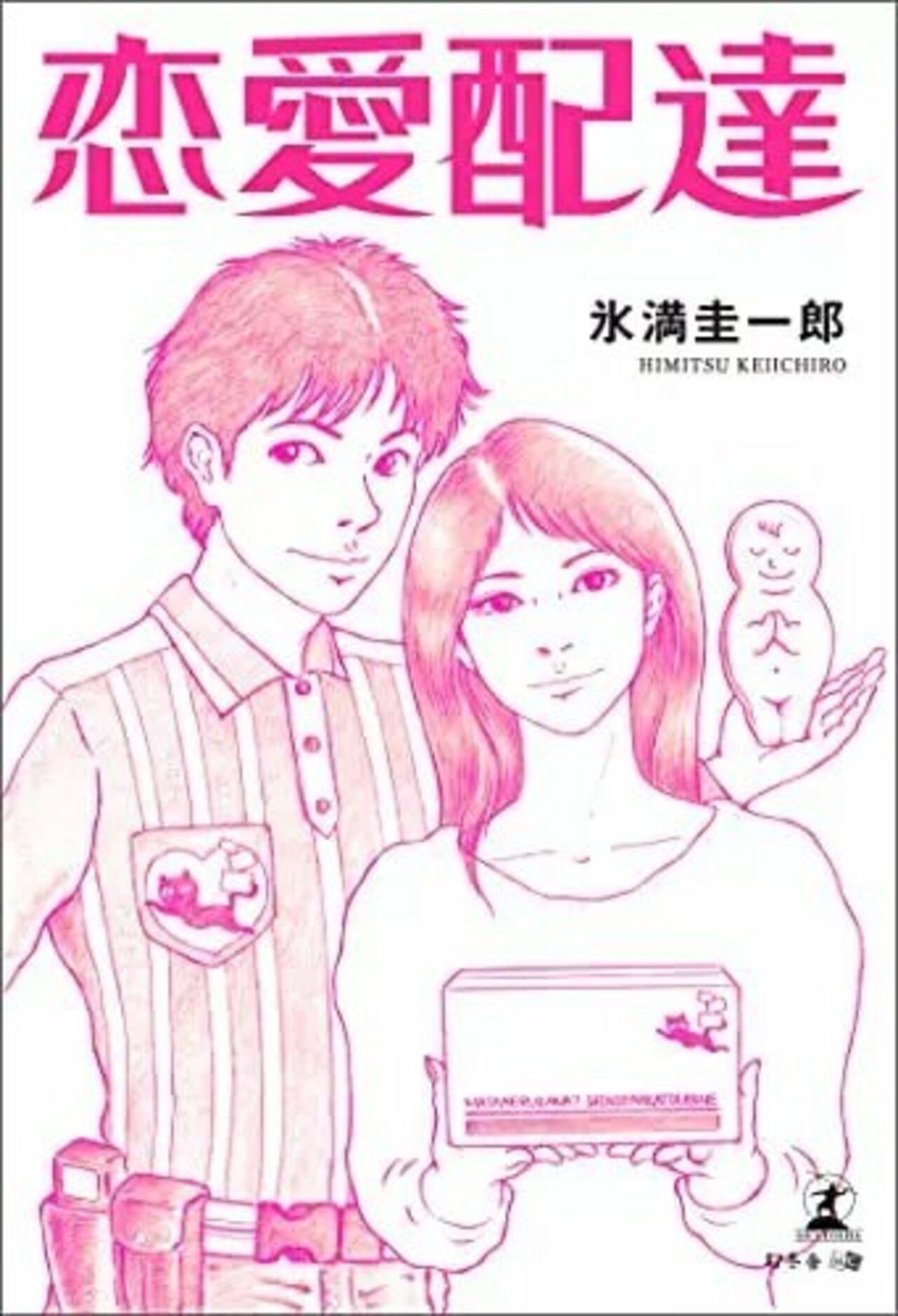定刻になると電車は音もなくホームに滑り込み、静寂の中プシューと大きな音をさせて扉は開いた。雨粒を払った傘をきちんと畳んで車内に入り、携帯の音楽ソフトのボタンを押して閉まったドアに体を預けると電車は動き出す。イヤホン越しに静かな前奏は始まり雨の日に決まって聞く曲が心の奥深くまで浸透し、歌の詞と自分の想いが互いにもつれて絡み合ってゆく。
――もう二度と会えないとしても、話ができないとしても、僕はただ祈り続けるしかない。
それが遠く離れていく二人だとしても、この想いは忘れることはできない。
……たとえ、これが最後の別れの雨だとしても。
うつろな目で遠くに何か探そうとドアガラスの曇りを指でなぞるが、雨粒で霞んで外は見せてもらえない。そのうちに音楽は聞こえなくなり携帯のスイッチを切りポケットにしまう。
駅に着いた電車は彼の心を気遣うように音もさせずに優しくゆっくりと扉を開いた。
ホームに降り傘を差し俯いて歩く彼に別れを告げて電車は次の駅に向かうが、悲しみを湛えた心だけは降りられない。体から遠く離れていく心には探し求めているものがあるから……。
大学に行けば思い弛みはしたが、一人になると彼女が残していった静寂の中に閉じ込められたままで心は漆黒の闇を彷徨い続けていた。
翌日はなぜか急かされる思いに駆られ、店長との会話もそこそこにして足早に駅に向かうと発車時刻をとうに過ぎた電車はホームで自分を待っていた。
発車を知らせるチャイムが鳴り、近くに駆け込むと同時に閉まるドア。
扉の窓ガラスに頭を預け携帯に繋がるイヤホンを耳に差し込み音楽ソフトを起動し曲を選ぶ。
動き出す車窓越しに外を見ようとするとガラスの中にいる人と偶然目が合う。その人は愁いを纏う瞳で自分の心の中を勝手に覗き込む。それが嫌で目を反らすが相変わらず自分を見ているので、仕方なくもう少しガラスに顔を寄せると彼の視線はそこから消えてなくなった。
月明かりが照らした外をぼんやりと眺める。動けない自分をよそにページを捲るように次々と風景は流れ去ってゆく。その景色とともに自分とは逆方向に走り去る列車を見て、あれに乗れば時の流れを遡行し、過ぐる日(過去)に連れて行ってもらえるのではないかと毎日思う。