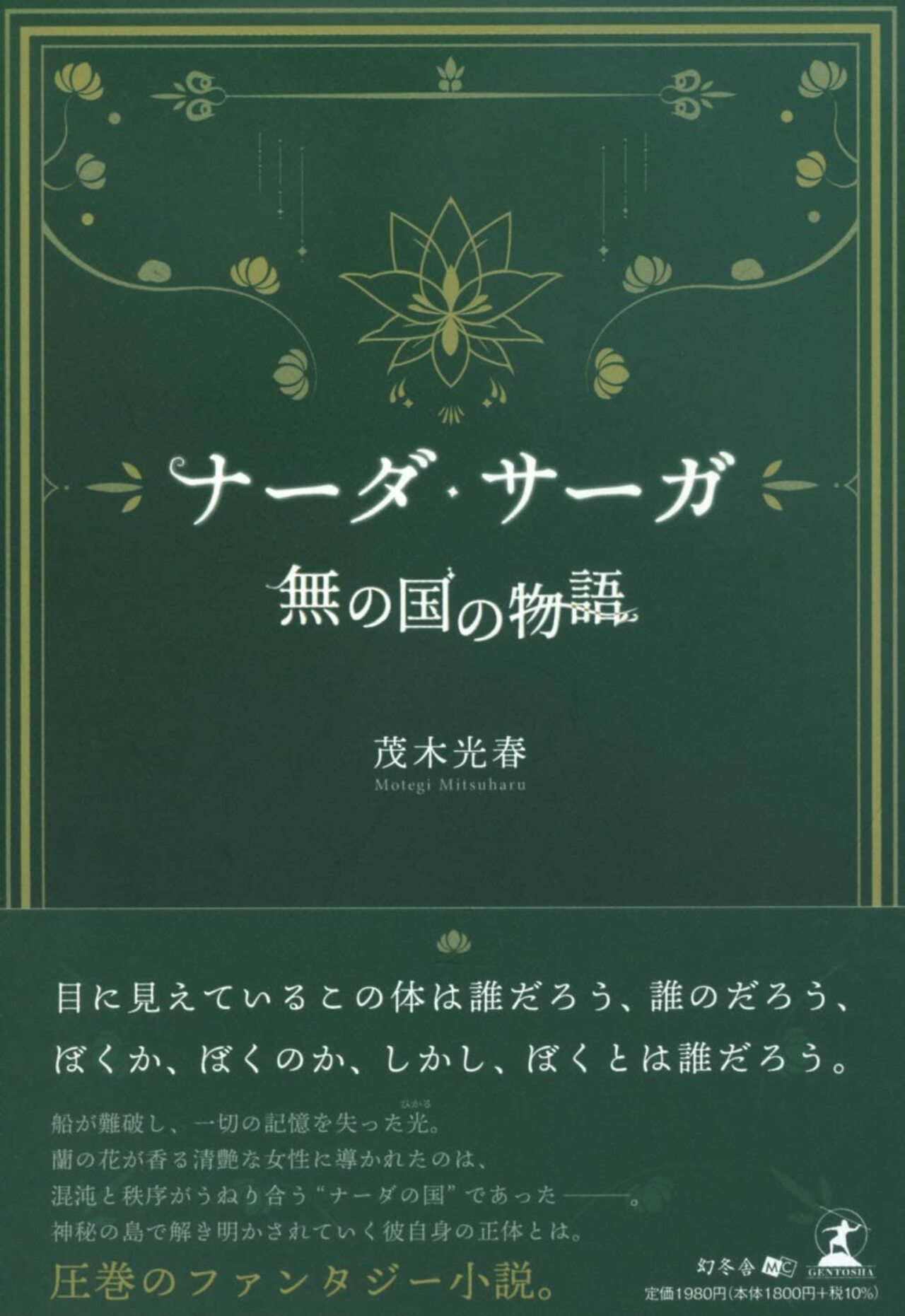目の前には大きな台にさまざまなナン製品が並び置かれてあり、じかに置かれてあるのもあり、ビニールに入ったものもあり、その形からしてメロンナンもあれば、アンパンナンもある。
食パンナンもあれば、カレーナン、イチゴ大福ナン、ロールナン、クリームナン、チョコレートナン、三色ナン、シナモンナン、キャラナン、ナンダナン、ナーダナンなどもあって、数限りもないナン製品が並べて置かれてあった。
中でも不思議なのは、ナンで作られたとおぼしい、十三重、十四重、十六重。いや、もっともっと、総計二十六重にも重なり合った塔、すなわち、二十六重の塔が、高さ二メーターにも達するほどの塔が、さまざまなナン製品の並んだほぼ中央に置かれてあったことだ。しかもそれには名前がついていて、
「nun de babel」と書かれてあった。そのてっぺんはまだ完成されておらず、屋根がなかった。そのナン店にも人々が、白いサーリーを纏った人々が並び始めたのであった。
ぼくは先を急ぐことも、また目的も目標も目当てもなく、またぼくを急き立てる何らの食欲も喉の渇きもなかったから、足の赴くまま、というよりもむしろ、目の前に展開する数限りもない店の賑わいと人々の喧噪に目を奪われ、耳を奪われて、ほとんど上の空で当てどもなく歩いたと言っていい。