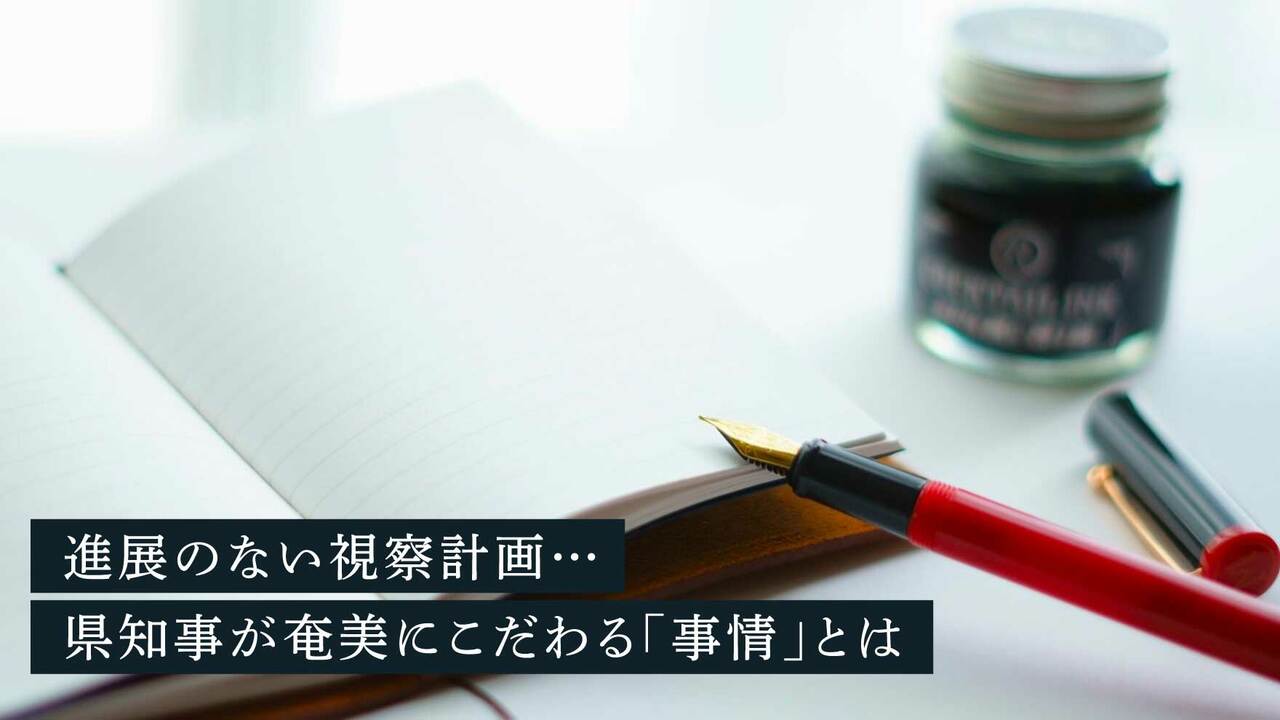第一章 知事就任
光三が知事に就任してから四カ月以上が経ち、南国に春が訪れた。鹿児島市内を流れる甲突川沿いの桜並木が満開の花を誇っている。
日曜日の午後、当地での生活にもすっかり馴れた光三は、美恵子と一緒にソメイヨシノが今を盛りと咲いている河畔に散歩に出た。多くの市民たちが土手に敷いたムシロのうえで花見酒を楽しんでいる。若い女性の中には、洋装の姿も混じっている。今の鹿児島の経済情勢は決して楽ではないが、桜の花の下では、誰もが一時それを忘れられるようだ。
光三がのどかな光景だなあと呟くと、春らしい明るくハイカラな洋装で出てきた美恵子もうっとりした目で誘ってくる。
「ねえ、気持ちがいいから、このまま照国神社まで歩きましょうよ」
「そうしよう。夕方は、官舎で早めのダイヤメ(晩酌)といこう。花見酒のつもりでな」
「お庭に、桜の木がないのが残念ね」
二人は、鹿児島市の総氏神さまである薩摩藩の名君、島津斉彬公を祀る照国神社まで、年季の入った木造の建物も多い道をゆっくりと散策する。行き交う着物姿の女性はショールをまとい、洋服姿の男性の多くはソフト帽をかぶっている。
「彼らは歓楽街の天文館に繰り出すんだろうな。カフェやダンスホールがはやっているらしいから」
「東京銀座の銀ブラを真似て、天文館通りをブラつくのを天ブラって言うようよ」
神社に着いて見事な大鳥居を見上げながら、光三はこれまでのところ知事職を順調に務めてきて、気分的にも生活面でも大分余裕が生まれてきたなと感じていた。美恵子も新しい土地の生活にすっかり馴れ、薩摩焼の手習いなどを始めていた。それに触発されて光三の方も、かねてからの趣味である色鉛筆画を再開していた。
休日のフリーな時間に絵を描くのに没頭していると、仕事のことを忘れられる。好んで描くのは、桜島や錦江湾の夕日である。美恵子が描き上げたばかりの作品をのぞき込んで、不思議そうに言う。
「どうして、いつも落日や夕日ばかりなの? 日の出も描いたらいいのに。勢いのある朝日の方がアナタの性格にむいていないかしら」
「いや、ワシは夕日の方が好きなんだ。赤味が朝日よりはっきりしているのがいい。それだけじゃないが」
「ほかに何が違うの?」
「ああ、朝日ってすぐに昼の明るさの中に溶け込んでしまうだろ。だけど、夕日は最後に強烈に輝いて、燃えるようにして沈んでいく。そこんところに、ワシはロマンを感じるんだよ」
「そういうロマンを求める気持ちが、アナタのどこかにあるのね」