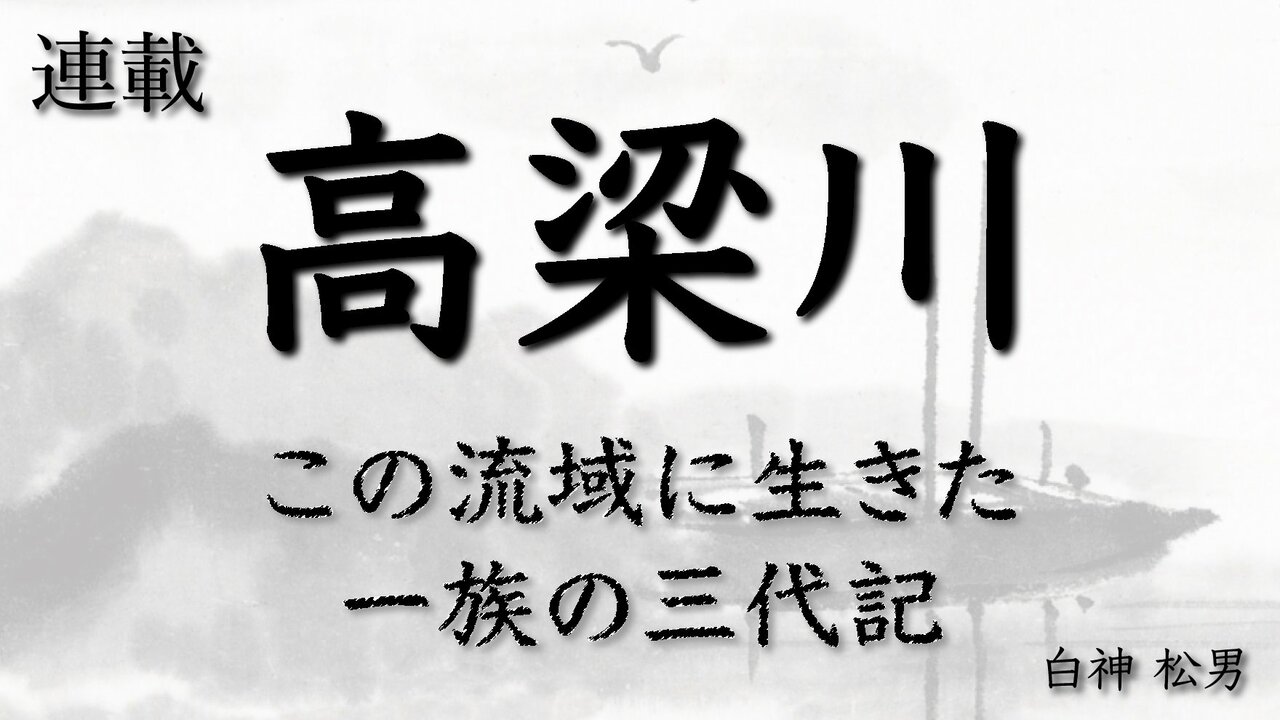第一部
七
このように、母娘の立場が逆になったような日々が続いていく中で、時間は確実に過ぎていき、半のお腹は益々大きく膨らんできた。やがて、その年も秋を迎え、周りの山々も錦をまとったように華やぐ季節となった。
もう妊娠八か月を越して下手をすれば早産するかもしれない時期である。この頃になると、妊婦中の半は、これまでにない重苦しさを感じ始めていた。
「民ちゃん、今度のやや児は大きいし、よく動くわ。多分、男の児に違いないじゃろな。それにしても、しんどいわ。あと二月もお腹にいるなんて大変よ」
いつも身の回りにいて世話をしてくれている娘の民に愚痴をこぼすが、そんな愚痴を聞きながら、民はこれまでと何か違う母親を感じるのであった。
「お母ちゃん、今度はな、久しぶりに児ができたんだし、何より、年取っているから、身体にも負担が大きいんじゃない。つらいけど、我慢してな」
ほんとは順番からすれば、自分が母親の立場にいてもおかしくない。母は私の身代わりになってがんばっていてくれているのだ。そう思うからこそ、民もわがことのように懸命に母親の世話をしている。一方の母親の方も、懸命に尽くしてくれる民の態度から、そんな娘の心情を感じているようだった。
「民ちゃん、ありがとうな。あんたがそばにいてくれてどれだけ心強いことか。これからも頼むな。母さん、一生懸命がんばるから」
そう言いながら、半は娘の手を改めてぎゅっと握りしめたのだった。二人の立場が逆転していても、こうなれば、母娘一丸となった共同作戦みたいなものである。
この頃には、いまと違って、病院でお産をするなんてことはなかった。特別な立場にいる人や大金持ちは、産科の病院に入院して出産していただろうが、普通はみんな自宅でしていたのである。もっとも自宅での出産が当たり前というのも、昭和になっても続いていたし、みんなが病院で分娩するようになったのは、昭和二十年代になってからではないだろうか。
やがて、年もつまってきた十二月、半は臨月を迎えた。早産の恐れはあったものの何とかここまで持ちこたえたのである。しかし、それが皮肉にも難産の原因にもなった。
今回のお産は、高齢でもあり、いつもお願いしている産婆さんにも、いままでになく頻繁にきてもらい用心していたのである。この村には、小倉助産婦さんという産婆さんがいて、数人いる中でももっとも評判のいい人だった。半もいつもお願いをしていたのである。
ちなみに、「産婆」というのは俗な言い方で、正式には助産婦という資格である。しかし、みんな親しみを込めてか産婆さんというのが普通だった。
「今度のお児さんは、大きな児だよ。もう男の児にまちがいないね」
産婆さんからもそう言われて、少し早めに出産した方がいいからと、あれこれと手を尽くすが、一向に出る気配がない。しかし、そこは、母親の半はすでに何回か出産を経験しており割と冷静である。
そうこうしている内に、予定日が近くなった。何となく陣痛みたいな重苦しさや周期的な痛みが起こり始めたのである。
「民ちゃん、先生を呼んで来て」
陣痛らしきものが徐々に強くなり始めたある日の朝、半は民に急ぐようにとせかした。