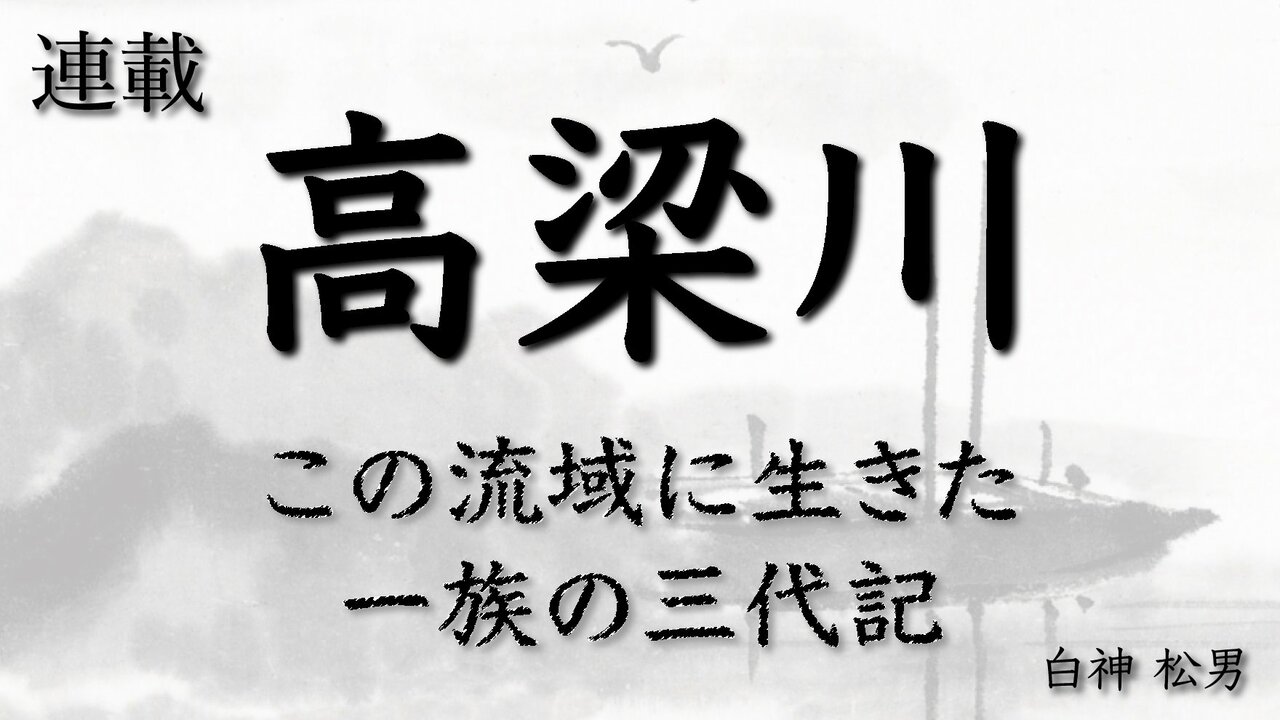第一部
七
産婆さんの自宅はあまり遠くなかったから、民は小走りに産婆さん宅へと向かった。着くなり、民はすぐ来てほしいという母の言葉を伝えたのである。
「陣痛が始まったって……、そりゃ、まだ行くの早いよ。でも、いよいよだな。頃合いを見て、いくからそう伝えておいて」
産婆さんの返事はすこぶる不愛想だった。
「でも、お母ちゃん、しんどそうにしているんだけど。大丈夫でしょうか」
民は不満気に返事をした。
「あんた、私ゃね、取り上げた児は千人は下らないよ。経験で分かるんだ。まだまだがんばらなきゃ産まれないよ。母さんに、今日の内にぜひ行くからと、伝えておいて…」
そう言って奥へと行ってしまったのである。民は、しぶしぶと帰るしかなかった。
「お母ちゃん、産まれるのまだまだ時間がかかると小倉先生が言っていたよ。今日の内に行くから、そう伝えておいてと言われたわ」
それを、そばで聞いていた夫の佐治衛門は、すでに周期的にはじまった陣痛で苦しんでいる妻の半を前にして激怒した。
「あの産婆さん、何を考えているんだ。もう産まれそうなのに、まだまだ先だなんて。わしが行って無理にでもつれてくるよ」
そう言って駆け出して行ったのである。ところが、しばらくしてぶぜんとした表情で帰ってきた。
「あら、父さん、どうしたの。先生はいっしょじゃないん?」
娘の民は、すぐに帰ってきた父親にけげんな顔をしながら言った。
「うん、やっぱり、わしにも、まだ行くのは早いと同じこと言われた。それでも、まだ食ってかかっていたら、『男の出る幕じゃない!』と一喝されたよ。あの産婆さん、相当がんこだな。もう任すしかない」
佐治衛門もあきらめ顔である。ところが、産婆さんの予測はほんとだった。半の陣痛は次第におさまり出し、小康状態を保ちだしたのである。
「やっぱり、先生の言う通りだわ。お母ちゃん、もうひとがんばりよ」
民は、母の手を握り励ますように言った。半は、首を縦に振ってうなずくだけだった。そして、その日も午後となり、夕方五時頃になってやっと産婆さんは姿を現したのである。
「どう、お腹の痛みぐあいは…」
来るなり、半のお腹を触りながら尋ねた。
「はい、やはり夕方になって、次第にお腹が張って痛みが強くなってきました」
「そう、どれどれ、どれだけ降りてきたかな…」と言いながら、内診を始めた産婆さんは、真顔になってそばにいる民に指図し始めたのである。
「破水が始まっているよ。多分、これからお産が始まるから、湯を沸かしてたらいに張ってちょうだい。それから、持ってきた油がみを広げて…」
「お産は今夜だね。今夜はここにお泊りだ。私ゃ、そう予測していたから、二時間ほど仮眠を取ってきたよ。だから、明日朝までかかっても、私ゃ大丈夫」
あたかも、妊婦の半を安心させるかのように、小倉先生は自信たっぷりな口調で言いはなったのである。
「先生、お願いします」
半と民は深々と頭を下げた。