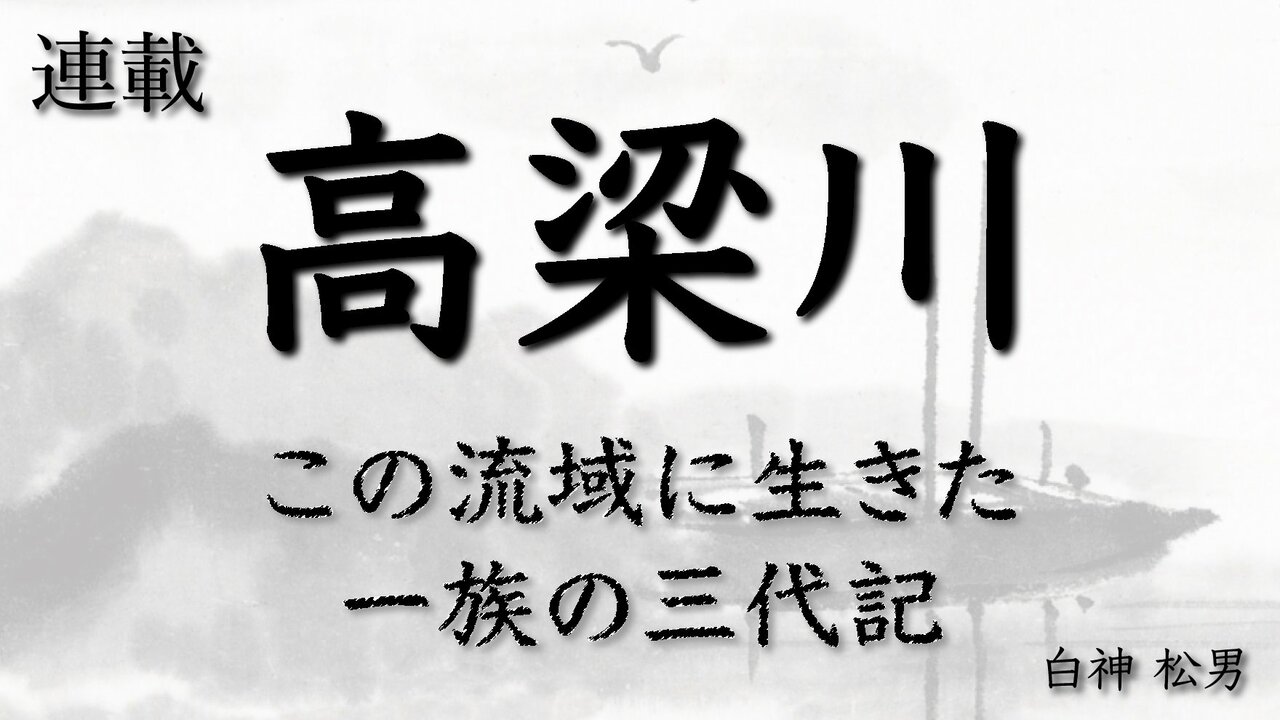第一部
六
いつものように夫と度助が仕事で外出し、二人だけになった昼食時、半は民に向かって切り出した。
「民ちゃん、驚かないでね。母さんな。児ができたらしいのよ」
「えっ!」
びっくりした民は、目を皿のように丸くして半を見た。一瞬、言葉を失った民は軽い衝撃を受けたようだった。
「お母ちゃん、おめでとう」
震える小声で言いながら、民はボロボロと涙をこぼし出した。しばらく、言葉にならない沈黙が続く。ところが、なぜか民はまもなく気を取り戻したように、「お母ちゃん、ほんとにおめでとうな。これでこの家も安泰よ」と返してきた。
病弱な上に夫との仲も表面上だけの夫婦。児ができることは期待できそうにない。そんな自分の立場を知っている民にとっては、まだ能力のある母親に児ができることを密かに期待していたのも事実だった。その夜、民は度助に母に児ができたことを告げたようだった。
翌朝、離れに住んでいる二人は母屋にやってきた。特に用事でもなければ、親子四人揃って朝食を取るのが普通だったからだ。その席で、座るなり度助はいつもと変わらない表情で言った。
「母さん、児ができたというの、ほんとなん」
「ええ、どうもそうらしいのよ。近い内に先生の所に行ってみようと思っているから、その時はっきりしたことが分かると思うわ」
やや顔を赤らめて笑った。
「あんたたちにできないから、母さん、がんばったんよ」
照れ隠しのつもりでとっさに出た母親の言い訳がましい言い分だが、若い二人にはグサッとささる言葉だった。でも、度助は平静を保ちながら言った。
「家族が増えるんだから、おめでたいことだよ」
ほんとうは、自分は世継ぎを産むために婿入りしてきたはずだ。「俺は、一体何のためにこの家に入ったんだ」表面上は平静を保っても、内心は、中々児ができない自分がもどかしく悔しかった。
ところが、もう一方の民は、自分の代わりに母が産んでくれるという思いから安堵感の方が強く、それに妹か弟かがもう一人できることの喜びを感じているようだった。そして、「お母ちゃん、身体大事にしてな」母をいたわるように言葉をかけた。
それからまもなくして母親の半は、児ができた時にかかるいつもの先生に診てもらい、正式に妊娠と告げられた。やがて、日が経つにつれて少しずつ下腹部が膨らみ、五か月ぐらいになると一見して分かるほど大きくなってきた。その頃には、娘の民の方が母親を気遣って、食事や洗濯などの家事を積極的に手伝うようになり、普通であれば、妊娠した娘のために母親があれこれと世話をするのだろうが、これでは母娘が逆転したような光景である。