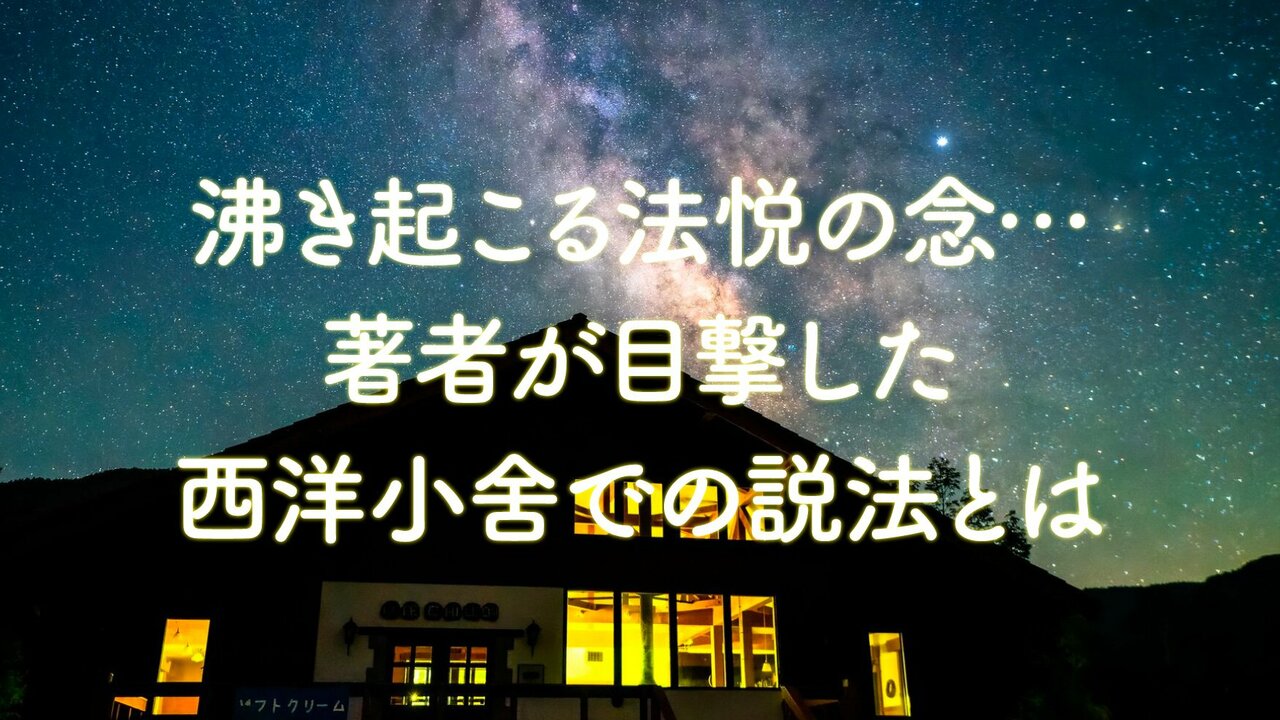食事が終わった頃、近くに建てられた小舎から老夫婦に雇われている邦人、十数名がやって来て一緒になり、開教師の説法が始まろうとしていた。部屋の隅に安置されている小さな仏壇の扉を開教師が開き、その中から経典を取り出して20分余り悠々朗々とお経を唱え始めた。
開教師の後方には老夫婦と息子達、雇人達が正座をして南無阿弥陀仏を繰り返している。お経が終わると、引き続き説法が始まった。テーマは現実の地獄と未知の地獄である。その説教の折にふれ、老夫婦はじめ雇人は何か心の琴線にふれるものがあるのだろうか、胸に迫りくる思いがこらえられなくなるのであろうか、南無阿弥陀仏を繰り返している。
「異国の田舎で出会った仏教、そこには因循な一面がかえって有難く何とも言えぬ法悦の念が沸き起こった」と与作は書き綴っている。
お寺の本堂や自宅の仏壇を見ていると、装飾された仏具に、ある種の怖さや恐ろしさを感じたことがないだろうか。そのような環境の中で、布教や法事が執り行われると与作は思っていたに違いない。開教師と共に訪ねた先。ここは荒涼とした大地と、農作業のみの世界である。命あるものは精一杯生きなさい、と自然界から突きつけられたような環境がそこにあるのだろう。
小舎の広間に集まり、そこで執り行われた仏教行事は極めて簡素なものだったようだが、正座し手を合わせる者、南無阿弥陀仏を口にする者など法悦の念を求めて集まる邦人達の姿からは何かに縋るような気持ちが伝わってくる。現実の辛さから逃げるのではなく、天と地が同化するくらい行動しろと大地が囁いているようだ。
どんなに立派なお御堂より過酷なまでに厳しい自然が真実を示唆してくれるのではないか。この時期の与作は留学による生活環境の違いから精神的に疲弊していた。この貴重な経験を通して自分の心の弱さに気づかされ、みずからを叱咤激励していたに違いない。