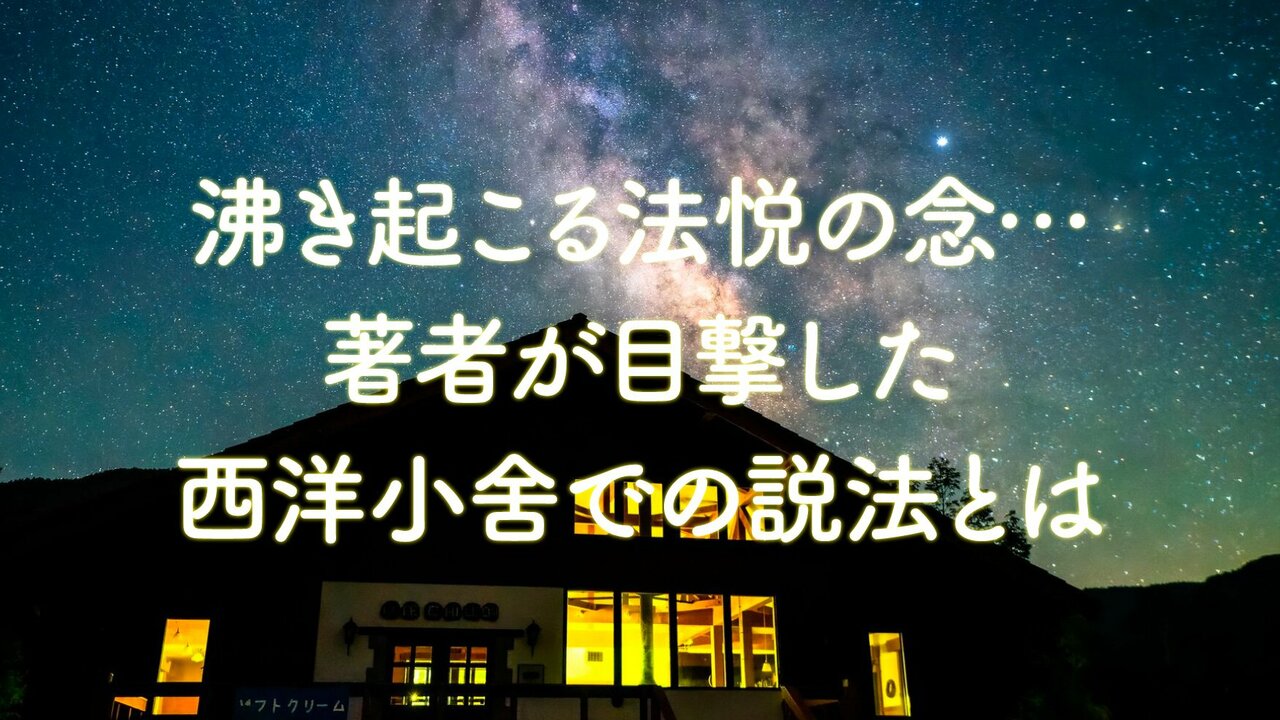【前回の記事を読む】沸き起こる法悦の念…著者が目撃した西洋小舍での説法とは
學士のスクール・ボーイ
サマリー
母親一人で育て上げられた与作は、富山県立高岡工芸高等学校まで行かせてもらったが、東京美術学校時代は親戚のお世話になって卒業している。また、この度の単身渡米も1年前から生まれ故郷の方々から支援を得て実現している。出来ることなら自分の力で目的を達成したいと常々思っていたせいか、米国の苦学制度がたまらなく羨ましく思ったようである。
与作が生まれ育った1900(明治30)年代は、多くの人が苦学や遊学のため上京するブームがあったという。しかし現実には学びと自活が両立せず、志半ばで断念する人がほとんどのようであった。そんな状況を目の辺りにしていた与作であったから、米国の苦学制度に興味を持って当然かもしれない。
米国では当時から産学連携が行われ、社会で生かせる勉強を学生にさせていたようだ。また大学を卒業したエリートに対する企業の扱い方は公平で、正しい意味で能力主義が徹底されていた。ことに米国の将来に対する可能性を大いに評価していたようである。
本文
苦學生の種類にも幾多あるが、白人などの苦學生は大抵單に肉體的の勞働は少ない、彼等は商店のブツクキーパーとか、諸會社の代用事務員などが最も多い、是に反して邦人の苦學生、卽ちユニバシテイ、ハイスクール、グランマスクール等に通學する多數の學生は殆ど勞働苦學生である、其內の主なる勞働はスクールボーイと學校寄宿倶樂部のウエタ等である。
スクールボーイと云ふのは所謂學僕で、この學僕を使用する白人の家庭は如何かと云ふと上流の家庭などは少なく、主に中流程度の階級に属する家庭で、終日働くコツクを使用すると勞働賃金が非常に髙いので、其代りに必要な時刻に時間的に使用するのは即ち學僕である、
それは朝六時に起床して直ぐケツチンに行き朝餐のブレツドを燒き、カフエーを沸し卵を燒く位なもので、其後は朝餐後の皿を洗ひ終り辨當を貰ひ八時の學校に急ぐのである、而して午後四時迄は學校に勉强して放課後は自分の時間なので近くの公園などを散歩して歸宅すると丁度午後五時になるので、再びケツチンに行き約二時間程御上さんの手助をする位なもので、其外に土曜日は學校も半日で終るから歸宅して三四時間、庭やケツチンを掃除する、
其代り翌日の日曜日には朝から晩迄で一日自分の自由時間である、恁な樂な學僕にも一週間四五弗の報酬を支給されるのだから實に歡待された學僕と云はねばならぬ。