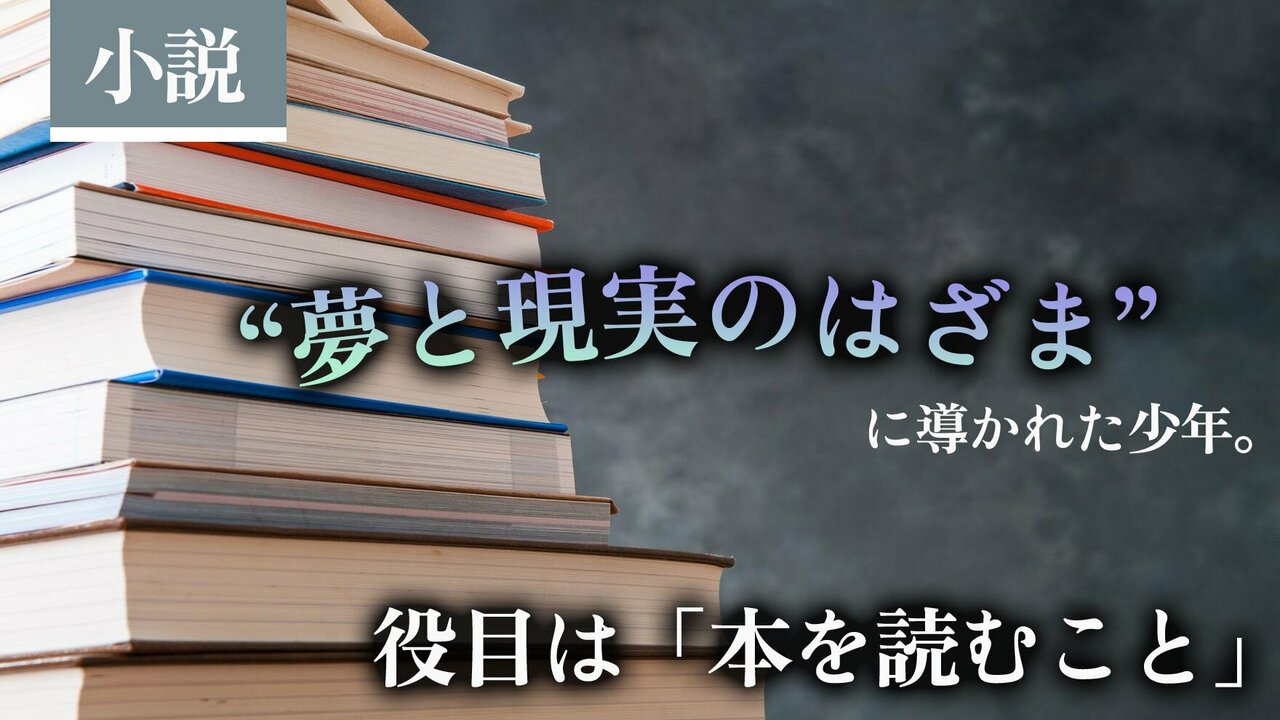Chapter・2 溶けきれない氷
目が覚めると、いつもの風景に戻っていた。いつもと変わらない、いつもの部屋。寝過ぎたせいか、頭痛と倦怠感と喉の渇きを感じる。あれだけリアルな夢だったからかもしれない。
水を飲もうと、右手をついて立ち上がる。ふと見ると、手の小指側の側面が鉛筆を使った後のように黒ずんでいた。
「うわっ、真っ黒……」
鉛筆なんて、久しく使っていない。さっきの夢以外では。
「あれが、まさかの現実? そんな馬鹿な……」
しかし、他に思い当たる節もない。家に鉛筆自体がないのだから。置いてあるシャープペンシルすらほとんど使わない。不思議に思うが、落ち着くためにも水を飲もう。寝ぼけているだけかもしれない。
コップに水を入れて飲む。水が身体を冷やしていく感覚で、視界もはっきりしていく。
恐る恐る右手を見た。黒ずんでいた。
「夢ではない? じゃあ私は、眠る一瞬の間にどこへ移動したの? あんな絵画でしか見られそうにない景色の場所は近所にないはず……」
一人で思案してみたところで、考えがまとまるわけでもなく……。夢の中にしては、何もかもがリアルだった。感触も、視界も、匂いも。
「そういやあの黒猫ちゃん、えらく毛並みが良かったなぁ……」
人馴れしているようだった。逃げもせず、鉛筆の動きを目で追っていた。しかし、いくら考えたところで、答えにたどり着くわけもなく。だからといって、やめられるわけでもない。
「んーっ! 頭が混乱する……!」
結局、答えは“不思議な夢”のままで止まっている。夢遊病なら、部屋のどこかに鉛筆や、スケッチブックがありそうだが、それがないのだから不思議だ。その辺は医師なら何かわかるかもしれないが、そこまで調べる気にはなれない。
思考回路が慌ただし過ぎるから、読書にでも逃げようか。それもある種の夢の世界か……。