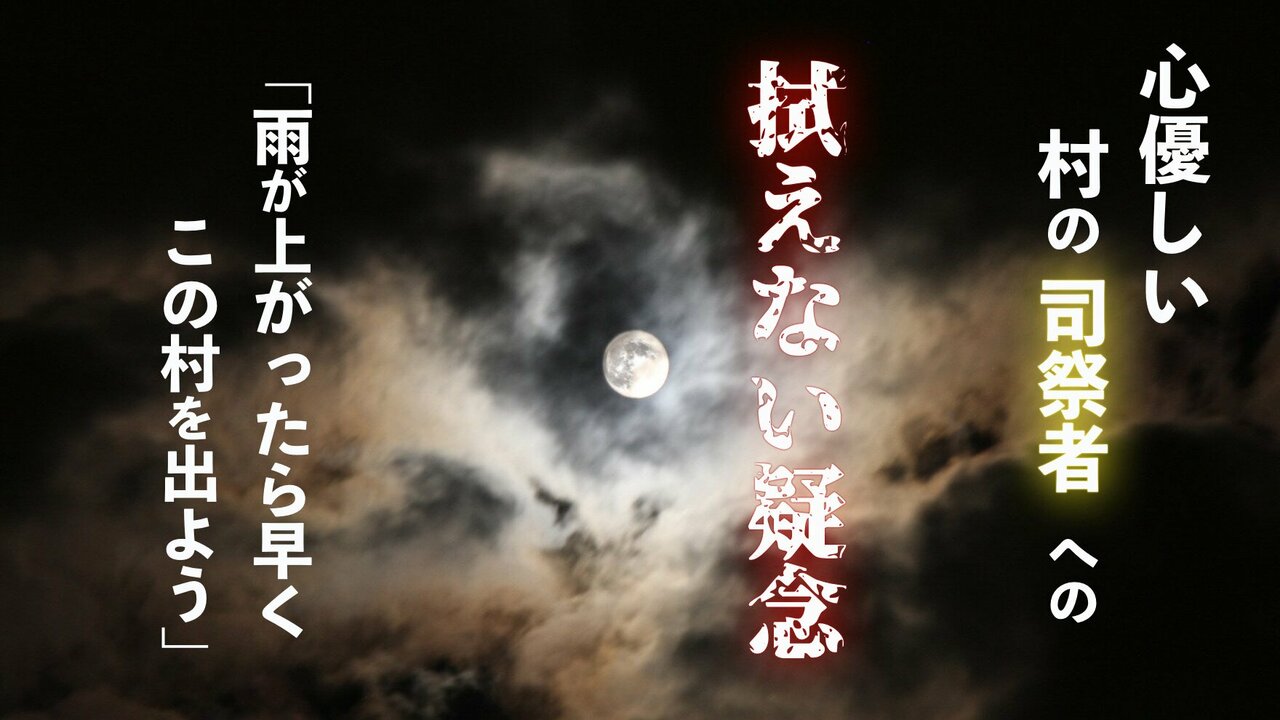「カズマ」
「はいよ」
サヤは空読の際にあらかじめ預けておいたものをカズマから受け取った。民俗的な装飾がなされた、八つの角の赤い珠の首飾りである。それを身につけるとサヤは呟いた。
「地を治めまします山神よ、我とその村を護りて導きたまえ」
それで特になにか起こるわけではない。サヤがこの首飾りを身につける際唱えるよう決めている合言葉だ。鎖骨の下で飾りは大きく揺れる。サヤの小さな胸元にはやや不釣り合いのサイズだが、サヤがこの村で自分を自分たらしめるには欠かせない要素の一つだ。
すっと気が引き締まってゆく。カズマに目配せをし、頷きが返ってきたのを確認すると民家の影から自分を周囲にさらけ出した。
「サヤ様の御成り」
カズマが後ろに続いてそう言った。声を聞いた村人達は一斉にサヤのいる方へ振り向いた。
「サヤ様だ!」
「ほんとだ、サヤ様がいらしたぞ!」
「サヤ様の前だぞ、皆の衆控えい、控えい!」
誰かがそう言うと村人は鶴の一声がかかったように地面にひざまずき頭を垂れた。すべてサヤを向いている。
「顔を上げてください、皆さん」
慌てるでもなくゆっくりと人々を見渡す。誰もが自分を神妙な顔で見つめている。
それとは別に、正面の男達に目を送った。
「斬らないのですか?」
そしてそう投げかけた。
「えっ、斬る? 誰を?」
赤毛の青年は面食らった顔で尋ね返してきた。
「あなた達は食糧の調達のためここを訪れた。それを拒んだ村人は、今はこの通り隙だらけ。あなたが腰に提げているのは飾りではないのでしょう?」
青年は直剣を腰に帯びていた。柄の巻布は擦れきって鞘もかなり使い込まれている。それに身振りをしている時に見せた右の手の平、農作業を日ごと夜ごといそしむ村民ですら比にならぬほど皮膚が硬化していた。一度抜けばこの男、おそらく相当の使い手と見える。
アオキ村に危害を加える意思の有無、それを確認しなければならなかった。
「いやだから何度も言ってるんですよ、俺達は安全な……」
「あなたは斬られたいの?」
青年の言葉を遮ったのはもう一人のケープマントの人間だった。フードで顔を覆ったまま一言も喋らず、ずっと青年の後ろで押し黙っていた。
女の声だ―サヤは意外に思った。透き通った音の中に根強い芯のようなものが通っている。
その声は自分に向けられた問いだと、サヤは一瞬の間を空けて理解した。
「ちょっとエリサ、小さい子どもになんてことを!」
「命の値段に年齢は関係ない」
青年から呼ばれたエリサという女は、そう言い切った。鋭く刺すような言葉に、サヤの喉元は息を留める。「答えによってはこの場で斬る」と言われているのだ。おそらくこの女は、本気で言っている。どう答えるべきか、サヤには言葉の選択肢などなかった。ゆえに、次の言葉を口にするのは何の躊躇いもなかった。
「私はこの村で最も尊い命です」
「……なるほど」