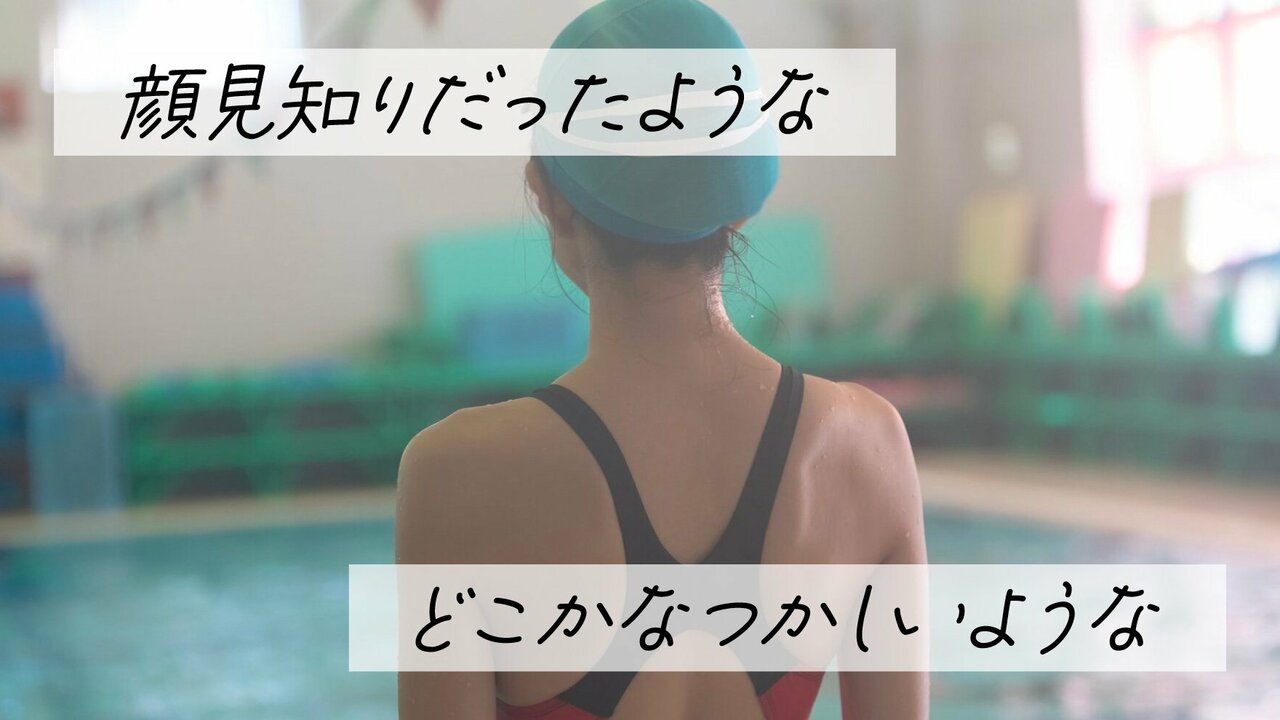真梨邑蘭子に指定されたホテルに向かう。黒いパンツスーツは万里絵の仕事着で、優雅な織地の薔薇色のワンピースを着た真梨邑を引き立てる黒子の役を兼ねている。
あこがれの真梨邑先生に会うファンのために、ホテルのラウンジからアフタヌーンティーセットを運んでもらい、会費の受け取り係や進行役まで一人で引き受ける。サイン即売会も好評のうちにそつなくこなした後、万里絵は残った本の入ったスーツケースを引きずって、フロントで経費の精算をした。
右の鼓膜に聞き覚えのある低いやわらかい声が響いた。右を向くと、キーを引き取る宿泊らしい男と目が合った。「ああっ」万里絵は思わず大声を出して凝視した。その男の方も、見惚れて言葉を失っていた万里絵を見つめた。
「えぇっと、どこかで、お会いした方ですよね?」
過ぎた暦をめくるみたいに、しきりに面影の記憶をたどっている様子だったが、万里絵が待てるほどの時間内に思い出せなかった。
「十一月二十二日、午前十一時頃、丸の内の書店、七階のお手洗いの前」
男の眼が上向きになった。
「その時は赤のネクタイをしていましたよね。わたしをどなたかと間違えたようで話しかけられました。先月までSPをなさっていた方ですよね」
万里絵は要人の名前を言った。男の顔色にはさっとした緊張が走った。
「あなたは何者かに依頼されてわたしを調査している?」
険しい目の動きには覚えがある。まさかそんな目つきで自分を見られるとは思わなかったので、万里絵は吹き出してしまった。
「だって、献金スキャンダルで、毎日、毎日、テレビのワイドショーに映っていましたよ。調査なんかしなくても誰でもこんなことはわかります」
「ああ、そうか」
男の顔に安堵の色が浮かぶ。
「あの時は、応援の四課の女性だと思って声をかけてしまった。黒いスーツ姿だったので同業者に見えました。ああ、今もそうですね」
男の態度がやわらかくなっていくのを万里絵は感じた。
「テレビに出なくなったから、残念だと思っていました。こんなところで本物のSPに会えるなんて思いませんでした」
男は笑い出した。
「テレビに出るような商売じゃありませんよ。それにしても報道の過熱ぶりが凄まじい事件でしたが。わたしを見たってなにも面白くないじゃないですか」
プラス五点、万里絵は男の人が自分のことを「わたし」と言うのがとても好きだ。静かで潤った声がとてもいい。会ったのは二度目だが、テレビの見過ぎのせいか、もうずっと前からの知り合いのように思えた。