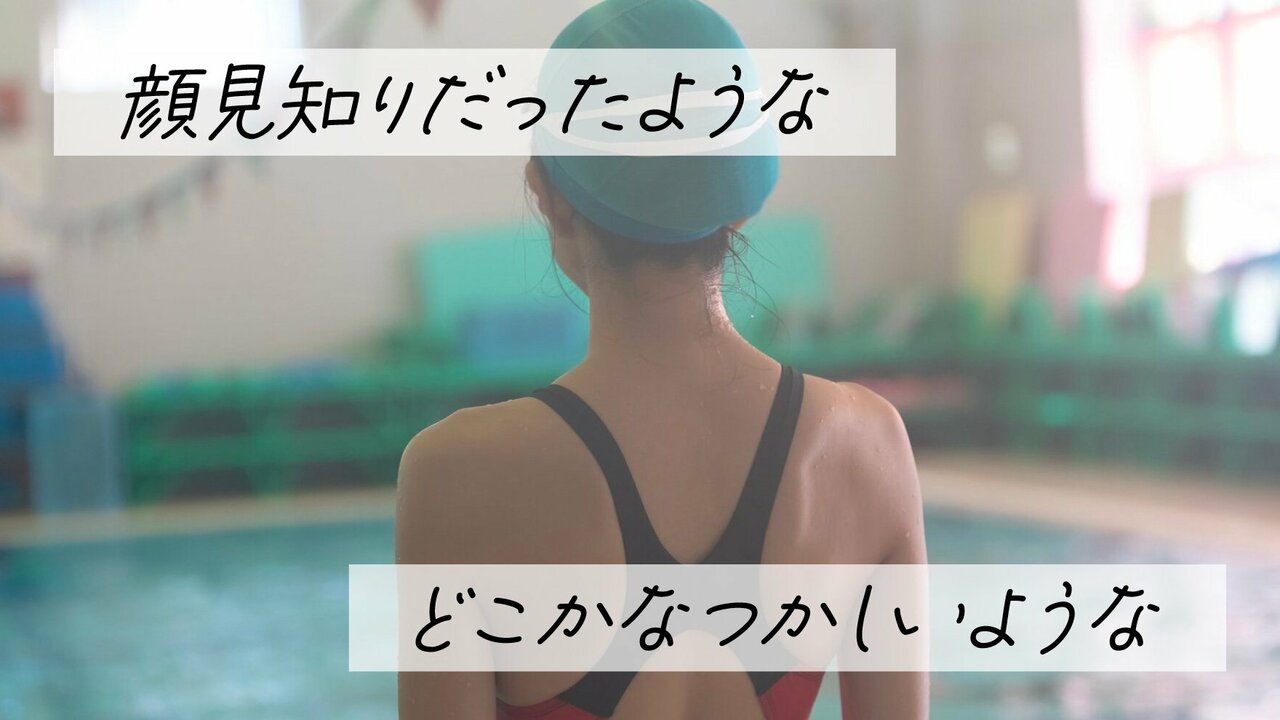自分史の「力強さ」
万里絵も二十四歳の若い女性だ。山崎が親しくなる目的も(・)持って、本の製作を依頼したことは感じ取っていた。
「スキーはしますか?」
山崎は思いつめたように口を開いた。突然の質問に万里絵は額に手を当てた。雪国生まれだ。小学校では近くの志戸平スキー場で毎年スキー教室があったし、子供会のレクレーションで安比とか夏油のスキー場にも良く行った。ボーゲンとかの技はできなくても、とりあえず直滑降くらいのことなら、今でもできると思う。
「子供の頃はしましたけれど」
この返事が次に、なにに結びつくのだろうと想像できなくて緊張した。これはお誘いだろうか。
「東京からでもけっこう日帰りで行けるスキー場はありますよ。一緒に行きませんか?」
何年も滑っていない。万が一、怪我でもしたら大変だ。これがデートの誘いなら、初めてのデートがスキーなのは、ハードルが高過ぎる。
「あまり、体育系が得意ではないので」
「自分が教えてあげましょう。長野の生まれですからね、こんなガタイでも、スキーは指導者の免許を持っています」
意外なセールスポイントまで披露されてしまって、万里絵は沈黙した。
「じゃ、スケートはどうです?」
理由を持って会えるのが最後になると思ったのか、山崎の押しは続いた。
「スケートなら、できそうな気はします」
万里絵の返事に、山崎はいきなりうつむき、床を見ながらなにかに耐えているようだった。泣いているのではないかと思ったほどだった。
「今度の土曜日が非番でしてね。どうですか? 連絡しますよ」
「会社に私用連絡は困ります」
万里絵は携帯電話の番号を教えた。
一緒に行ったスケートリンクで、山崎の運動神経の良さに感心した。がっしりした体型だったが、氷上を滑るステップはなめらかだった。手すりを磨いていた万里絵が、転んだはずみに手首をひねってしまう醜態となった。軽いねんざだったが連日山崎のお見舞い攻めに合い、完治した時にはプロポーズとなった。
山崎は万里絵よりも八歳年上で仕事柄早く身を固めたいと言っていた。万里絵も自分の年齢をまだ早いとは思っていたが、熱烈に望まれていることに悪い気はしなかった。