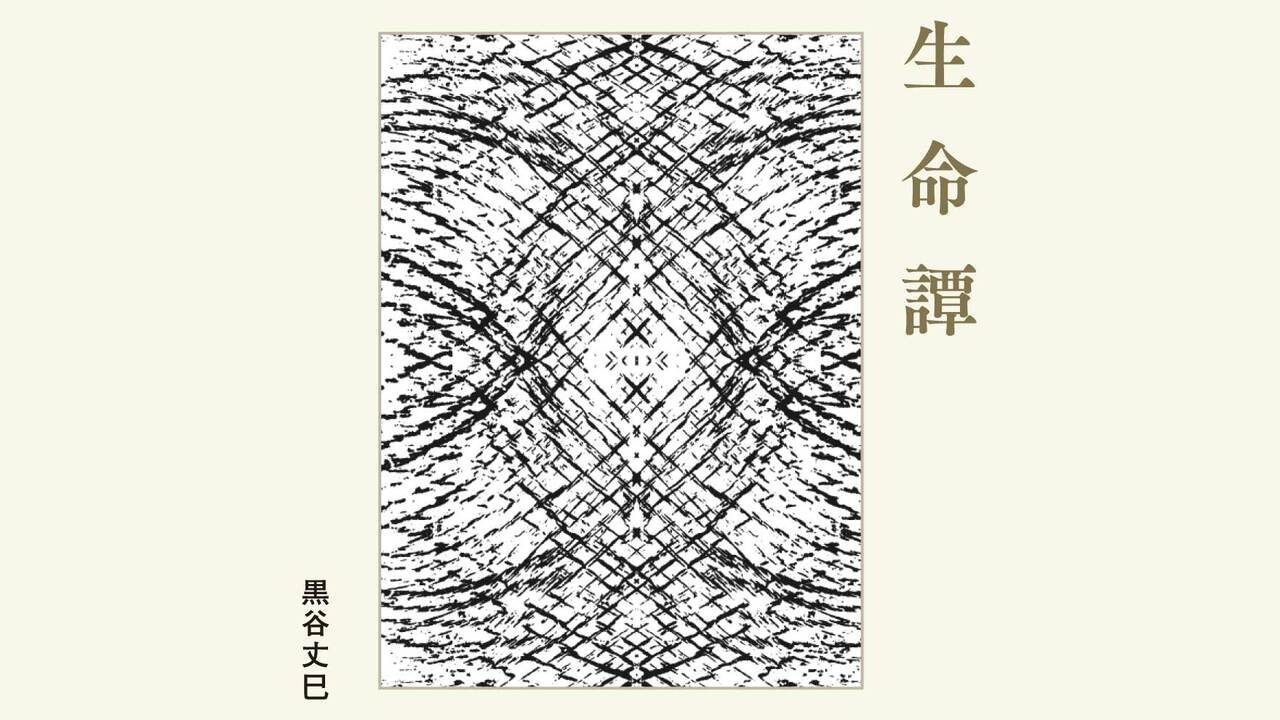「じゃあ父さん、夕べからずっと病院におるんか。それやったらあんまり寝ちょらんのやろ。俺が着いたんやけん、いっぺん家に帰って寝たらどうや」
七十六歳の修治は、疲れた顔で、それでもしっかりと純平を見つめて答えた。
「大丈夫や。昨日は看護師さんがこの部屋に簡易ベッド持ってきてくれたけん、ちゃんと寝た。お前にもはっきり言うちょくが、母さん、もう覚悟しちょったほうがいいかも知れん状態やそうや。そげな時に、家にやら帰っちゃおれんわい」
「……もうそんな具合なんか。どうする? 姉貴から、状態知らせてくれち言われちょるんやけど」
「お義兄さん、まさちゃんにも帰るように言うたほうがいいんと違うやろうか」
修治が右手を伸ばし、淑子の頬にそっと触れた。
「ドイツは遠いけんのう。生きちょるうちに会わせてやりてえけど、母さんが目を覚ますかどうかもわからんけん、あんまり早うに知らせてものう……」
「もう目を覚まさんでこんままかも知れんのやな。それやったら、やっぱ姉貴に帰っちくるように言おう。間に合わんかったらしょうがねえし、母さんが生きちょるうちに会えるんやったら、それに越したことはないやろ」
「うん、純ちゃん、それがいい。そうしてあげちょくれ」
純平はスマホを取り出し、姉に向けてメールを送るべく、キー操作を始めた。おそらく姉貴は、もう航空券の手配をしてはいるだろう。それでも大分に着くのは早くて明後日ってことか。
姉貴に連絡した後は、東京に残している妻の幸恵にもメールを送っておかなきゃならない。一応、幸恵は勤務先の保育園を休む段取りをつけて、明日にも大分に来る予定になっている。健太と美咲は、祖母が危篤だということで会社を休ませるわけにはいかないだろう。
母さんには申し訳ない気もするが、社会人になって間もない孫たちは葬式に参列するのが精一杯だ。デュッセルドルフほどではないにせよ、東京も遠いんだ。母さん、ごめんよ。
「婆さんの時はのう、真砂子もお前も死に目に会えんかったけど、今回はお前だけでも間に合うて良かったわい」
婆さんとは、淑子の母親、純平の祖母であるトヨのことである。トヨは夫の竜造と国東半島にある海沿いの町で雑貨を扱う小さな商店を営んでいたが、純平を可愛がってくれた竜造が亡くなった後は、娘の淑子夫婦が大分の家に引き取った。既に自分の両親が他界していた修治はトヨに対して実の息子のように接し、トヨは平和な老後を送ることができたのである。