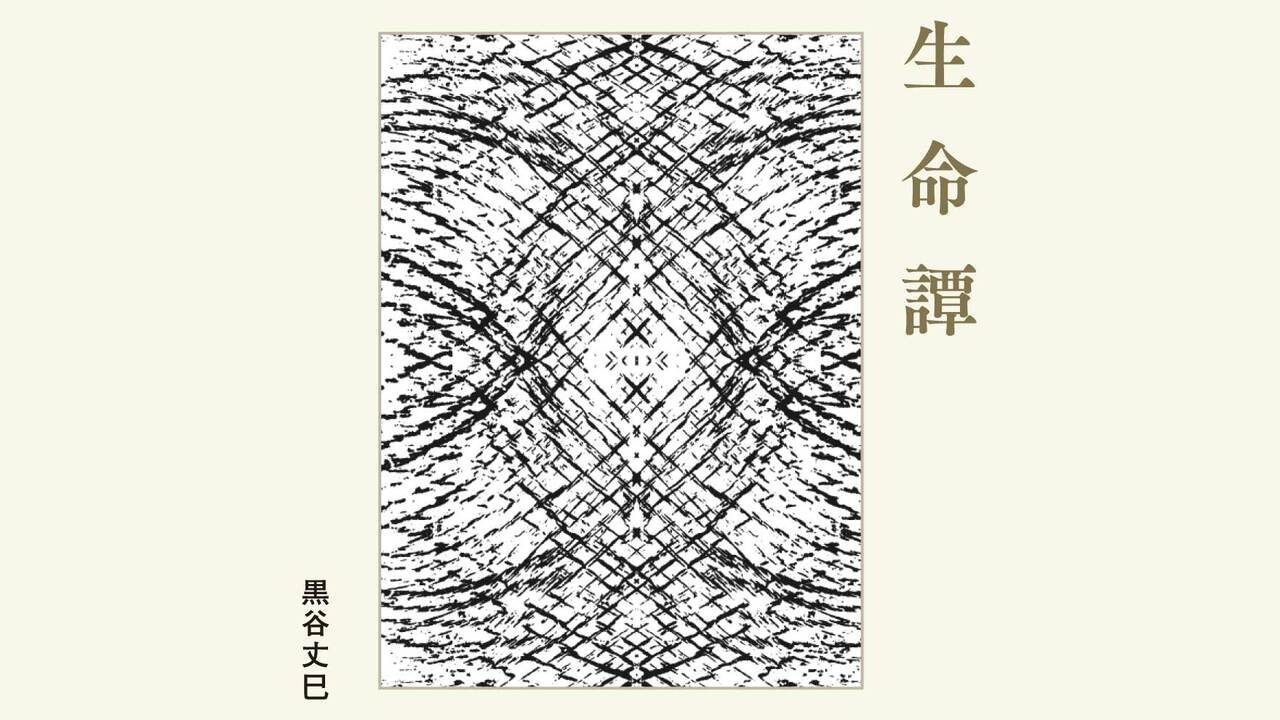二〇一六年 秋 ─大分─
いや、平和に見えつつ、祖母は実際には「一日でも早く娘よりも先に死なねばならない」というプレッシャーを感じていたのだろうと、純平は思っている。修治も淑子も思いは同じだっただろう。
トヨの葬儀の席で、淑子が参列してくれた友達に「うん、私はなあ、幸せ者やと思うちょる。七十になるまで、お母さんと一緒に暮らせて、ほんで送ってあげられたんやけんねえ」と話していたことを純平は覚えている。淑子も、何度も入院したけれど、自分が回復してトヨの葬式を出すことができたことを安堵していたのだろうと思う。それから僅か二年で、淑子が臨終を迎えている。
母親との別れが近づいている悲しみを深く感じつつ、純平はふと「ばあちゃん、たった二年やけど、母さんよりも先にそっちに逝くことができて、良かったな」と思った。そして、まだまだ別れてしまいたくないのに、既に母親が亡くなる覚悟を決めつつある自分に、ちょっと驚きを感じた。
母親が何度も入退院を繰り返すうちに、純平にも「母さんはあんまり長生きしないかも知れないな」と考えるようになっていた結果なのだろう。純平が子供の頃から、確かに体の弱い母親ではあった。学校から帰ると、蒲団の中から淑子が「お帰り」と声を掛けてくれるのは珍しいことではなかった。だが、誰にとっても同じなのだろうが、純平はお母さんが大好きだった。
幼稚園の頃、友達と、「ぼくのおかあさんのほうがきれいや」「いいや、ぼくのおかあさんのほうがびじんや」と言い合って喧嘩になったこともある。決して丈夫な子供ではなかった純平が、成長するにつれて逞しくなり、運動好きな子供になったのは、淑子の育て方によるところも大きい。