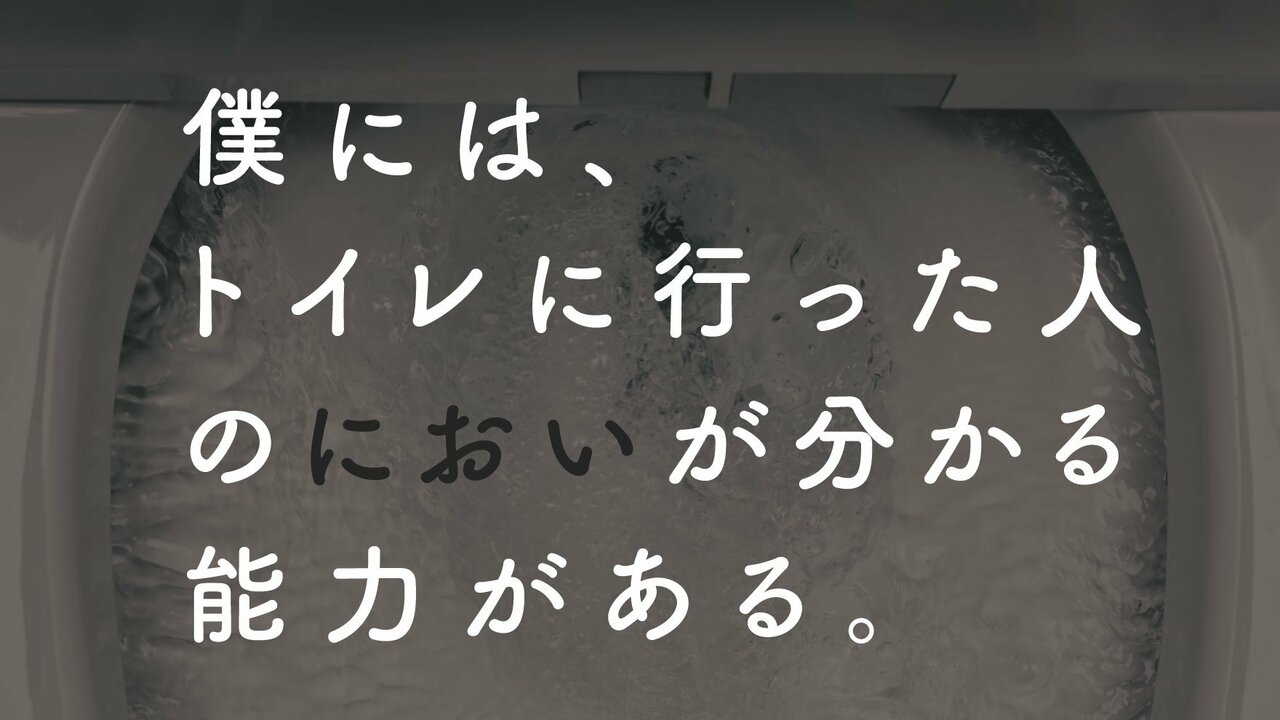序章
原田中(はらだあたる)は、いつものように通勤のために家を出た。まずバスで渋谷に出て、そこから会社まで地下鉄に乗るのである。いつものバスに乗っていると、次の停留所から乗ってきた男性のにおいに気づいた。
「この人、トイレに行ってからすぐに家を出てきたんだ」
原田は、すぐに分かったが、もちろん、何も言わないし、別に気にすることもない。次の停留所で乗ってきた若い女性も同じにおいがした。
「えっ、この人も、トイレに行ってすぐに家を出てきたんだ」
原田は、今度は、とてもきれいな人なのに、とついついその女性を見てしまう。原田には、トイレに行った人のにおいが分かる能力があった。大か小かも分かる。原田がこの能力を知ったのは、高校生の時であり、その時の悲しい思い出がある。
好きな娘ができて、ようやく告白してから迎えた初めてのデート。駅前のきれいな喫茶店に行った時のことである。とてもかわいい女の子で、まさか、告白を受け入れてくれるとは夢にも思わず、OKの返事をもらった時は天にも昇る気持ちであった。その時、その娘の頬が少し赤らむのに気づき、その娘がとても純情であることにも気づいた。思えば、そんな純情な娘であったがゆえの悲劇であったことに、原田は後に気づくことになる。
喫茶店で二人で楽しく会話していると、相手の娘の顔色が変わってきて、口数が少なくなってきた。原田は何か気に障ったのではないかと思い、焦りすら覚えていた。そして、とうとうその娘も意を決して原田に告げた。
「ちょっと、いいかしら」
原田は何がいいのか、何を言いたいのか分からず、ポカンとしてしまう。何か、いけないことをしたのだろうかと、いろいろ頭を巡らせていた。すると、その娘は席を立って、店の奥へと歩き去った。あ、そうか、トイレに行きたかったのか。恥ずかしくて、言えなかったのか、と気づき、鈍感な自分を反省していた。
原田は「少し、時間が掛かっているな。あの娘も緊張していたのかな? やっぱり女の子だから、お化粧直しとか、時間が掛かるのかな?」などと思いを巡らせていると、待つ時間も楽しかった。
ようやくその娘が席に戻ってきた時、原田は、そのにおいに気がついた。初めて嗅ぐ独特のにおい。決していいにおいとは言えないが、トイレのにおいというわけでもない。そこで、その娘に何か焦っている様子があることに気がついた。なぜか目がうつろで、トイレの方を気にしているようでもあるが、話が上の空なのである。