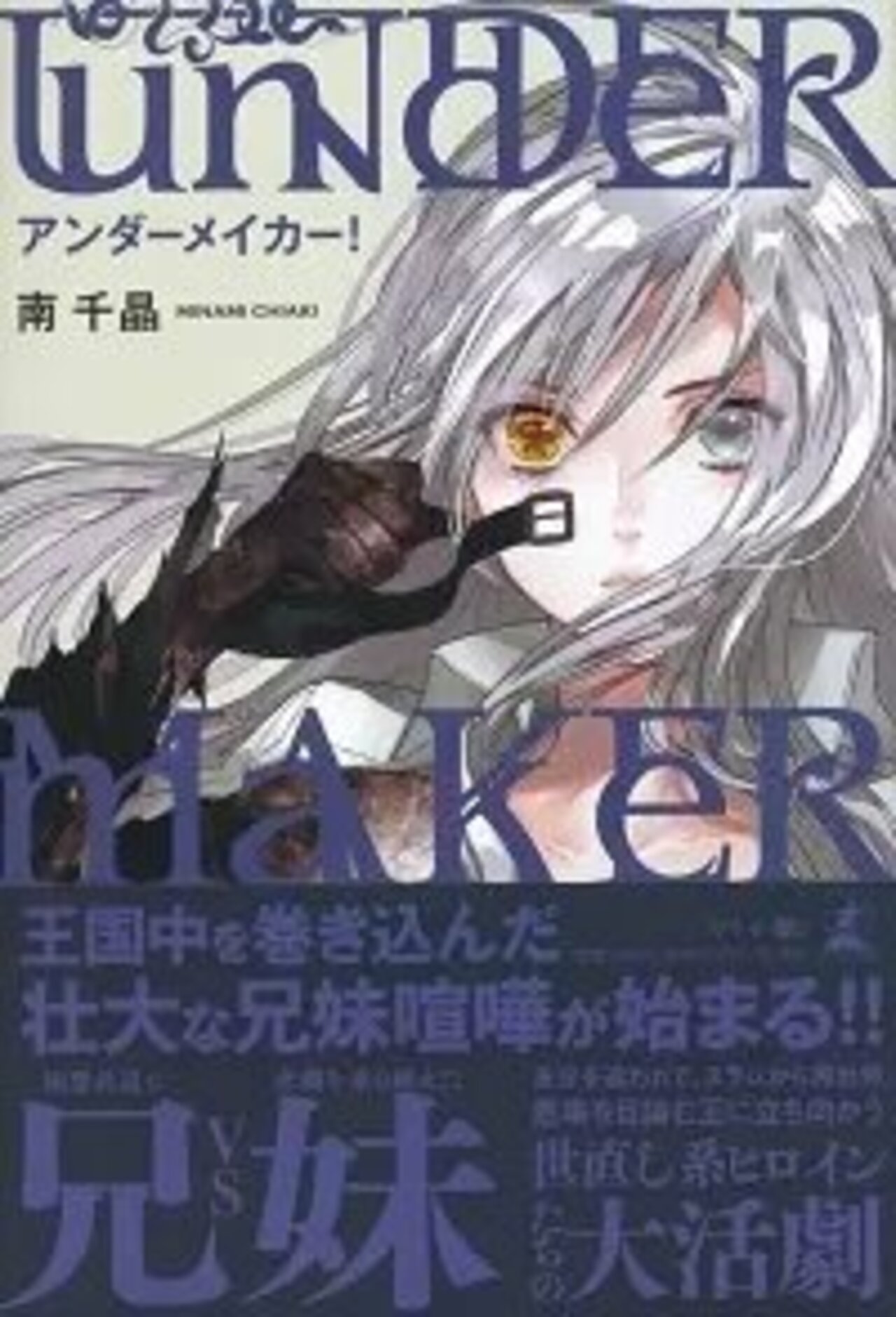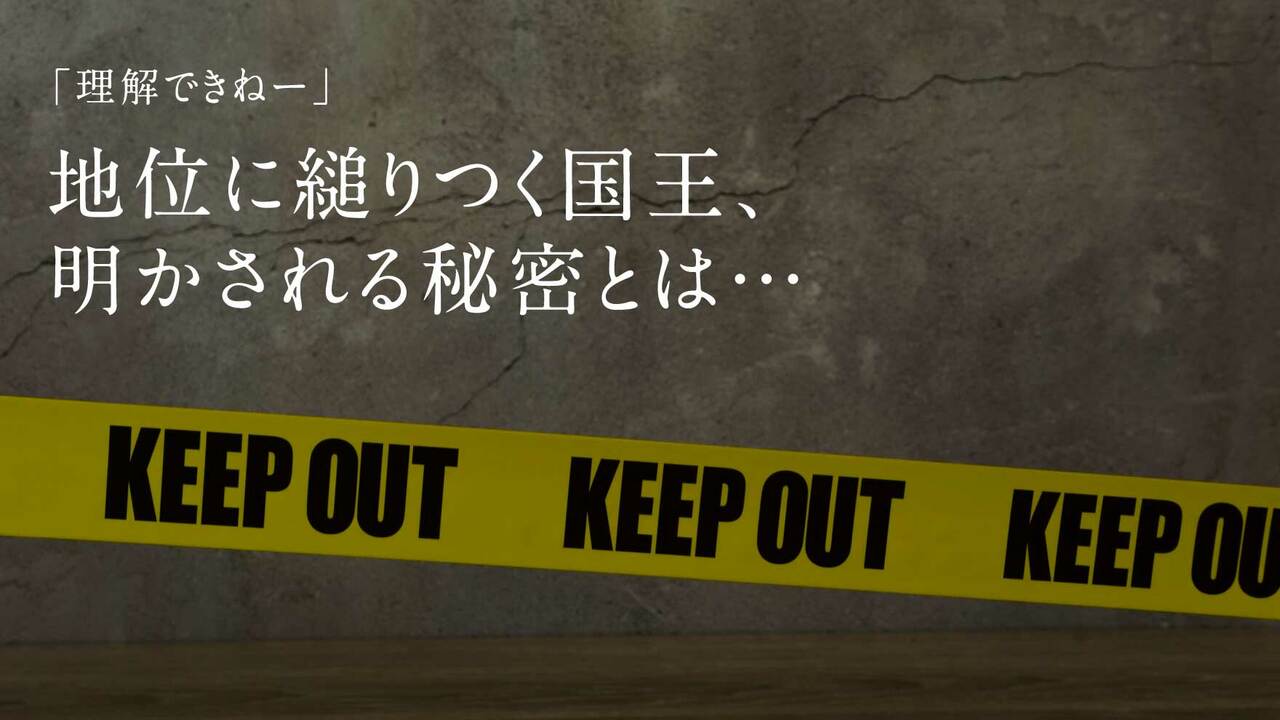ああ、そうだった―そう思い直したのか、立ったまま彼は蘭軍曹に重要なモノでも入っていそうな黒い皮でできた正方形の鞄を開けさせた。中には数枚の書類。
「土地の権利書だ」
渡され、彼女は目を通していく。下部のサイン部分には、懐かしい名前が達筆な文字で書かれていた。
「土地の権利書? なんでそんな」
「ただのコレクションだ」
「はぁ?」
父親の持っていた、この国に散らばる数々の土地や建物の権利書。彼女は、それらを見返りに軍からの仕事を請け負っている。父の残した土地の権利書、それはスラム世界に限らず、貴族世界や華族世界のものもあった。今回渡されたのは貴族世界のものだったようだ。
「ま、チンピラだったしこんなもんで許してやるよ」
「やれやれ。では、死体検分と屋敷の捜査に加わってくれるな?」
「留守番を頼みたいところだけど、浩輔も必要みてーだし。どうすっかな」
「ちょ、お前待てよ! こんな小さな子供も連れていくのかよ!?」
小さな子供―獣耳の生えた幼女、殺女の事を言っているのだろう。
「殺女はただの子供じゃねぇよ。立派な葬儀屋の一員だ」
ゆっくりと立ち上がって伸びをし、壁にかけていた白いロングコートを羽織る。腰に刀を二本差し、揃って部屋を出て、事務所の入り口に“外出中”の看板を立てかけた。
「栗栖」
「御意。電話の外線は通信機に取りつけておりますので対処は可能です」
「なら、問題ねぇな。あとは、スラム世界の連中が食料欲しさに来ない事を祈るだけだ」
「先日配布したばかりでしょう。暫くは大丈夫だと思いますが」
「大事に食ってくれてる事を願うばかりだな。どんなに貧しくても、心まで貧しくなってほしくねぇんだ」
「立派な騎士道精神だな」
「それは違うだろ」
くっくと笑う桐弥に彼女のツッコミが入る。なんとも和やかな雰囲気だが、浩輔だけは落ち着く事ができなかった。