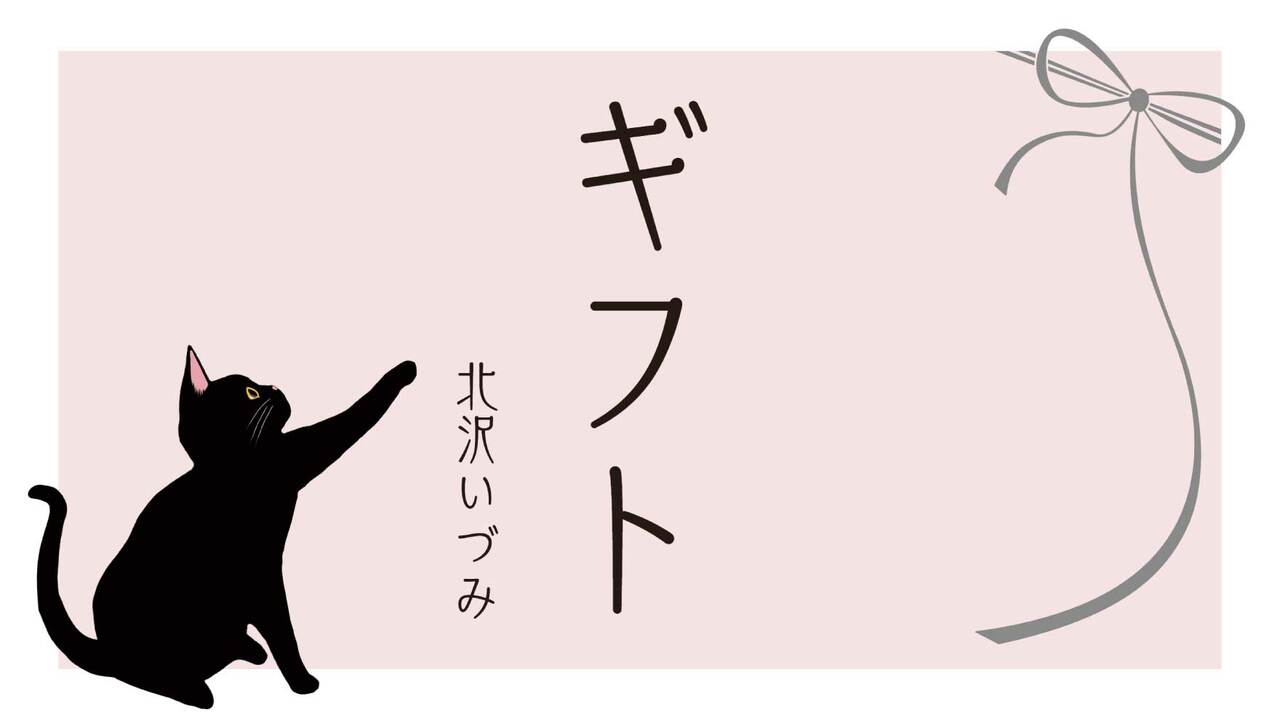神様からのおくりもの
駅まで母に送ってもらい、右も左も分からないまま、心許ない僕の一人旅が始まった。本州から四国に入る列車の窓からの景色は、いつも母が言うように確かに綺麗だった。座席のすぐ横の窓から見える景色は、窓枠に収まりきらないほどの傾斜の山々が見える。ガラスに顔を擦り付けるくらい近づけて見上げないと、山の上の方が見えない。これがみかん山なのだろう。
反対側は瀬戸内の海が、車窓を青くする。太陽がガンガンに差し込む真夏日は、波が光に反射して海面が銀色になるらしい。巨大な鏡を一枚敷いたようになり、海の青色が消えて砂浜と一体化して、まるで海水が抜き取られたかと見間違うほどだと母が言っていた。僕は列車の窓の向こうの景色と、窓ガラスに映る自分の不安そうな顔を、交互に眺めていた。
列車のスピードがだんだん遅くなり、いよいよ松山駅に着いた。改札を出ると祖母のキヨ子おばあちゃんと一緒に、近所の石田さんというおじさんが迎えに来てくれていた。
少し着飾っている祖母に比べ、真っ黒に日焼けした石田さんは作業着のような、太腿の横に沢山ポケットが付いたズボンを穿き、書道家の誰かが書いたような書体で【愛媛産には愛がある】とプリントされた、もう何年も着古した感じの色褪せた黒いTシャツを着ていた。その飾らない雰囲気に何だか好感が持てて、多分僕はこの人と仲良くなるんだろうな、という予感がした。
「よう来たね〜、疲れとらんかね?」
祖母の背丈が、かなり大きいので僕はびっくりした。おばあちゃんと呼ぶには失礼なほどシャキシャキしている。
「あ、はい、大丈夫です。お迎えありがとうございます」
バックパックの肩紐を両手で握りながら、僕はお辞儀をしてお礼を言った。松山には数回来た事はあるけど、もっと小さい頃で殆ど覚えていない。祖母への挨拶も初対面のように言葉を選んでしまう。
「この子が将太君かぁ。おっとこまえやなぁ」と、石田さんがその場を和ませようとして豪快に笑いながら言ったけど、メガネに天然パーマの僕にはお世辞にしか聞こえない。恥ずかしくて、照れ隠しみたいにメガネの位置を直すフリをして片手で顔を覆った。駅のすぐ横の駐輪場で、飛び出した自転車の列を綺麗に直している女子学生が、僕達の会話を聞いてクスッと笑ったように見えて、僕は更に恥ずかしくなって下を向いた。
「忘れもん無いか?」
号令ともいえる石田さんの一言で二人が歩き出した。僕もバックパックをジャンプしながら背負い直して後ろについて行った。すると、「あ、そうそう、この松山駅からこっちに行くと、よくドラマや映画で使われる【下灘】っていう駅があって、夕陽や景色が本当に綺麗なんよ」と、石田さんがクルッと振り返り、駅を正面に見て左に指を差しながら言った。
そういえばドラマでその駅が出た時、母が飛び上がって喜んでいた。学生の頃にデートでよく行ったと、僕が聞いてもいないのに母は一人でニヤニヤしながら話していた。