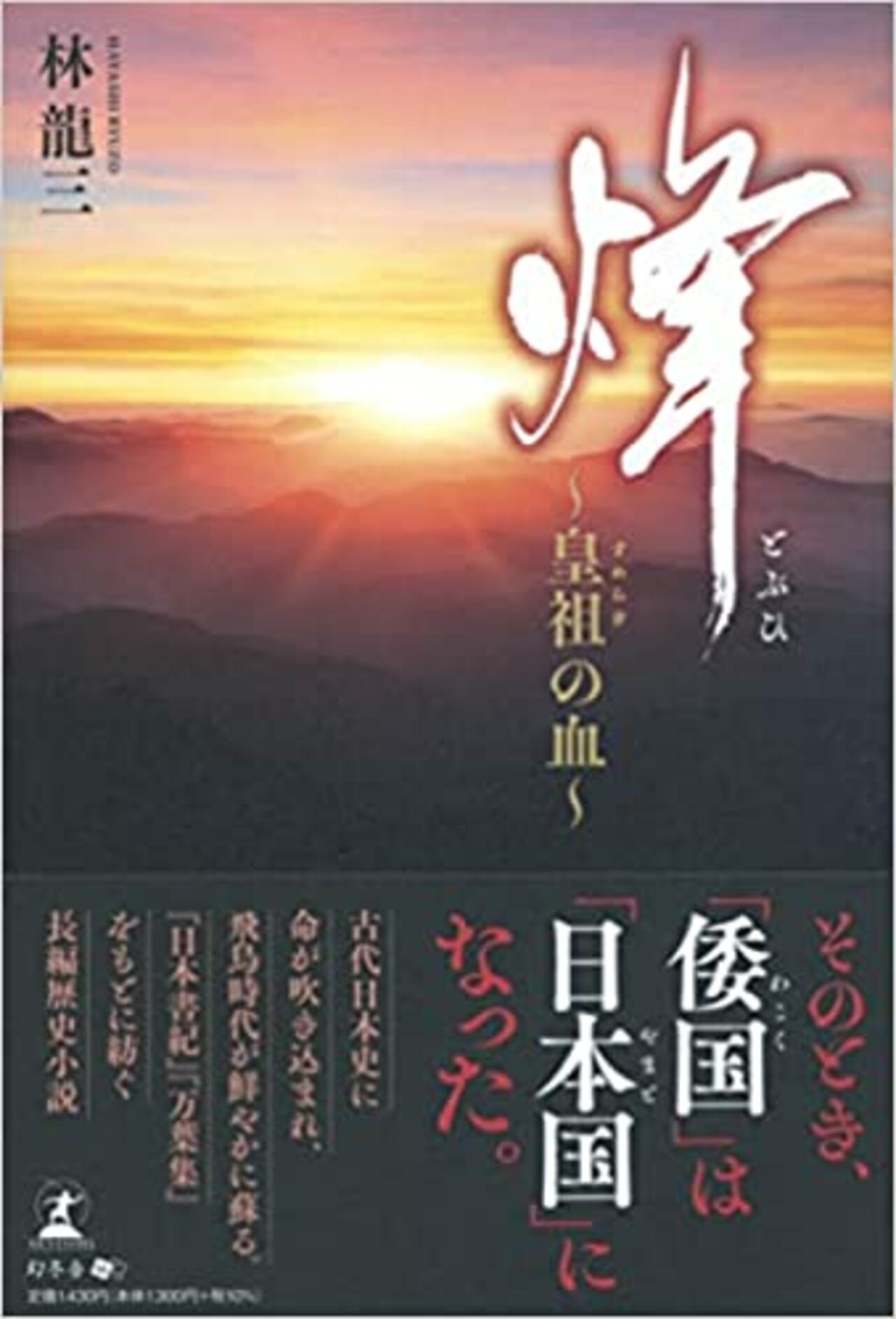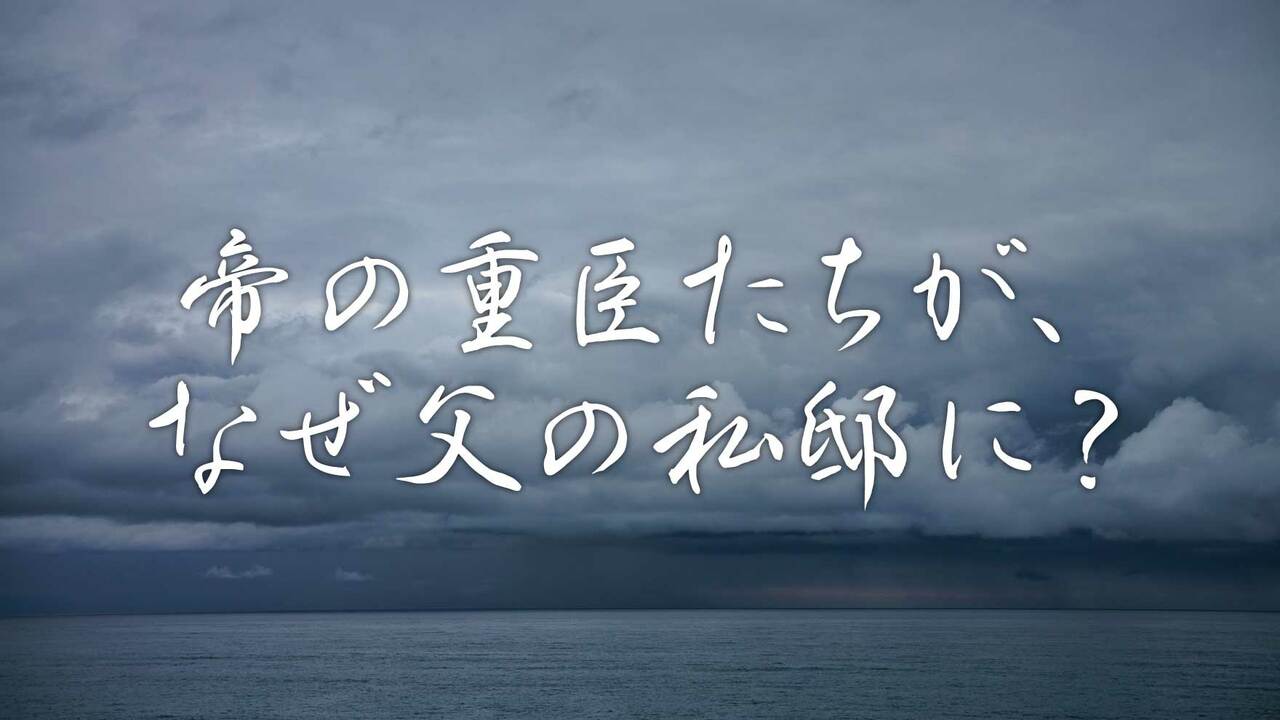【前回の記事を読む】古代日本史を紐解く「この物語は持統天皇が産声を上げた645年から始まる」
第一章 大化
皇極女王
六四五(皇極在位四)年正月。飛鳥板蓋宮で行われた元日朝賀儀が滞りなく終わると、左右に控えた奉翳女孺らが翳をかざし、高御座から降りる大王(皇極女王)の玉体を隠した。そのまま大王の姿が大極殿から消えると、朝堂に参列した群臣も三々五々退出してゆく。厳かに歩んでいた大王が廊下に出て、群臣から見えなくなると急に少女が弾むような早足になった。
普段の住まいである内裏には娘の間人王女が待っているのだ。まもなく朝賀儀に参列していた中大兄王子と大海人王子の兄弟も入ってきて、やっと母子水入らずの時を過ごすことができる。久々に家族四人が顔を揃えたのである。
中大兄王子はこの年二十歳、間人王女は一つ違いの妹である。さらに二つ年下の大海人王子は、海部という航海や海産物を献納する集団を統括する大海連に養育されてきたためこの名がある。傅役は付けられていたものの、宮中で育てられた二人とは違い、勝手気ままに都の中で遊び回り、町の子供たちと相撲をとったり、長じては賭けごとに興じたりしていた。
屋敷に帰っては自ら興味をもって武術にも励んだ。そんな生活が長く続いていたため、いかにも宮人然とした中大兄とは対照的に、肌はいつも日に焼けて、百姓と見紛うほどに浅黒い。宮中で育った中大兄や間人王女にとっては、そんな大海人の話はいつも新鮮で面白かった。
「お疲れ様でございました」
と、中大兄が母を労った。
「毎年のこととはいえ、ほんに疲れることよ。しかし大海人、お前はいつも落ち着かぬな。朝賀儀の間、右を見、左を見、まったくじっとしておらぬ。退屈なのか」
「母上、御簾の中から我を見ておられましたか」
「これ、大海人、母上ではない。大王と呼ばねばならぬと幾度も言うておるに」
と、中大兄がたしなめた。
「よいよい。余人のおらぬところで、大王などと堅苦しい呼び方をせずとも」
家族でいるときは大王からただの母親に帰ることができるのだ。三人は新年の挨拶を終えると、それぞれに近況を話し出す。大王も大きな口を開けて笑いながら子供たちの話に耳を傾けていた。