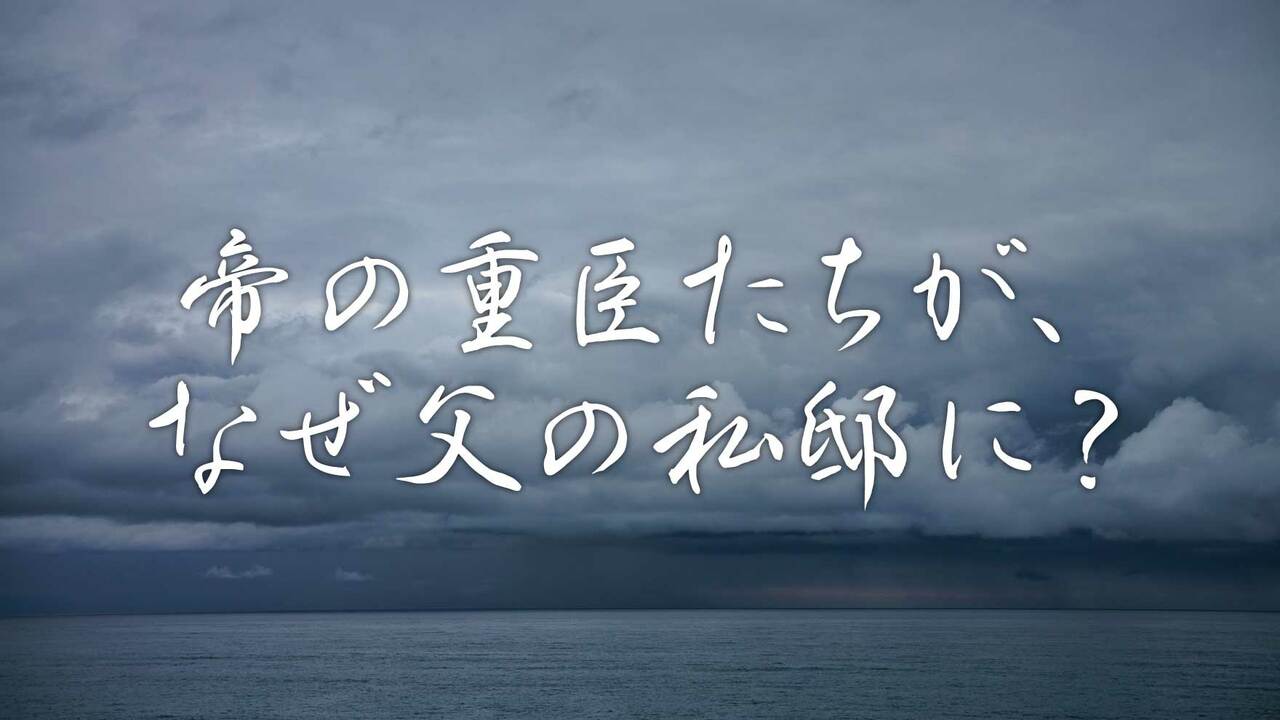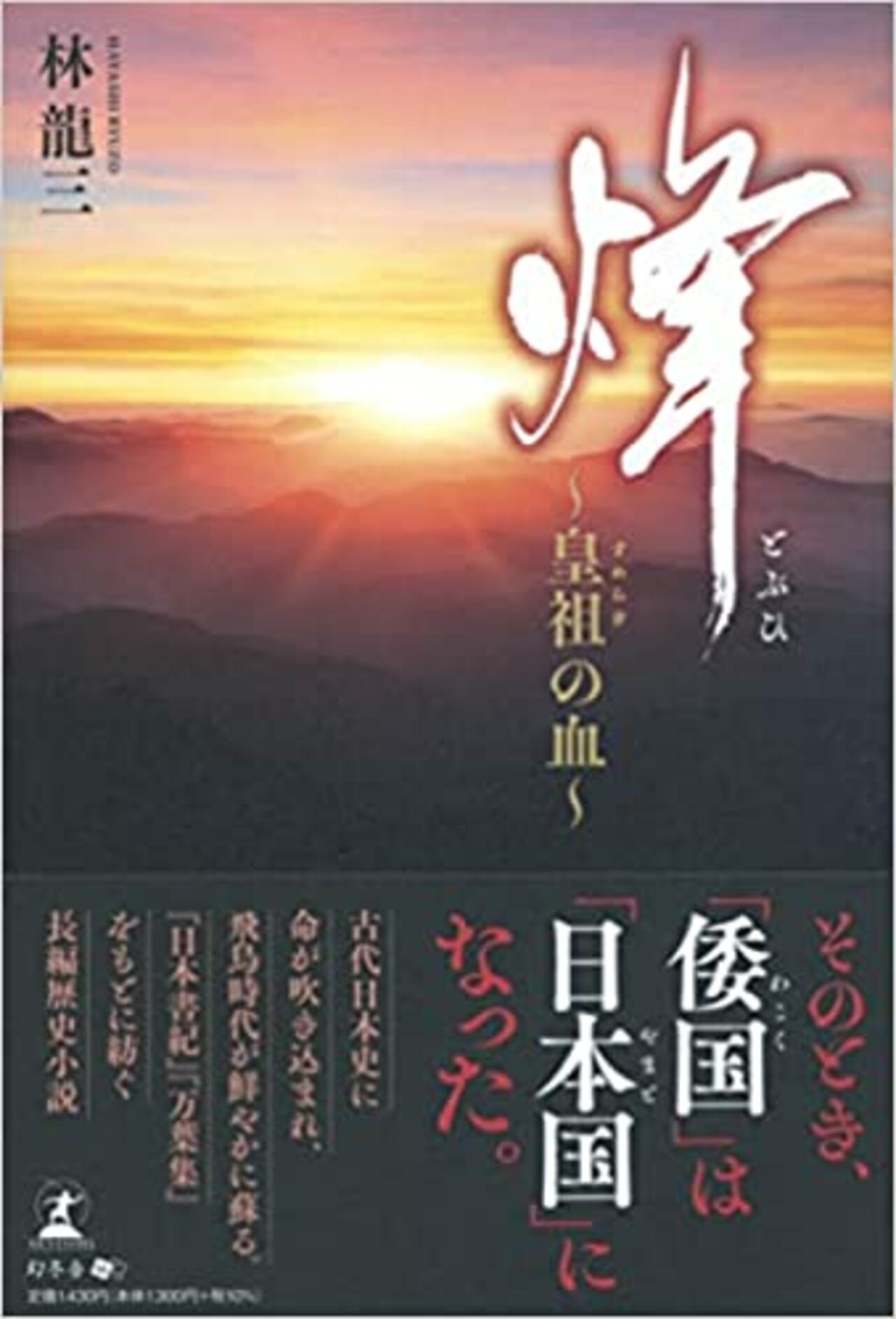第一章 大化
入鹿の剣
その年の六月、中大兄王子の子を宿した遠智娘は、前年に生まれた大田王女を連れ、父、蘇我倉山田石川麻呂の屋敷に身を寄せていた。もう二ヶ月になる。今年は梅雨の明けが遅い。空気がじっとりと肌に纏いつくようで、臨月を迎えた身重の体にはこたえる。
そんな日の午後、父を訪ねて夫、中大兄王子が大海人王子と数人の客を伴ってやって来た。一人は中臣鎌子、そして海犬養勝麻呂、佐伯子麻呂と葛城稚犬養網田。この四人の姓はいずれも「連」。石川麻呂の「臣」に次ぐ重臣たちである。
父の私邸を訪れることなど滅多にない顔ぶれだった。さらに遠智が驚いたのは少し遅れて軽王子が阿倍臣内麻呂を伴って訪ねてきたことである。軽王子は今年五十歳。今の大王、皇極女王の弟である。従って中大兄王子や大海人王子の叔父にあたる。
遠智の母は侍女たちに酒肴の用意をさせていたのだが、配膳を終えると誰も部屋に近付かぬように固く申し渡され、近侍たちが部屋の前と縁側の下り口に張り付いた。
日が暮れてその客たちが帰ったあと、中大兄が遠智の部屋にやって来た。
「吾子(大田王女)はもう寝たのか」
「母上が寝所に連れて行きました。妙に静かな宴でしたね」
遠智が言うように、酒を飲んで騒ぐ声も、歌を詠みあう声も聞こえなかった。
「それに軽王子さままでお越しになるとは思いもよりませんでした」
「誰も宴などとは言っておらぬ。この十二日に百済、高句麗新羅の朝鮮三国が大王に貢物を献上する。その儀式の手はずを打ち合わせていたのだ」
「それだけですか?」
集まった人々の表情が恐ろしげにこわばっているようであったし、人払いなどの警戒も尋常ではなかった。
「そのような大事ならば宮中でなさればよろしいのに」
「儀式は軽王子様が取り仕切っておられるのだが、三国の上奏文を読み上げる役目は石川麻呂殿と決められた。その打ち合わせだからここですることになったのだ。そなたの父上は宮中で最も信頼厚き方であるからな」
「そうでございましょうか。今は蘇我の大臣、入鹿どのが飛ぶ鳥を落とす勢いで大王の信を得ていること、知らぬ者はおりません」
入鹿の名が出て中大兄は視線をそらした。開け放した窓から上弦の月が目に入った。ゆっくりと雲間に隠れる半月を眺めながら中大兄が言った。
「入鹿は政治を私している。あれは信頼ではない。皆、恐れて口を噤んでいるだけだ。遠智も知っているだろう、廐戸王子の一子、山背大兄王の謀反を言い立てて、死に追い込んだことを。あれで上宮王家のお血筋が絶えてしまったのだ」
「あれには大臣の蝦夷どのもずいぶんお怒りだったとか。山背大兄さまの母は大臣の妹君でございましたでしょう」
「ああ、しかし山背大兄は蘇我本宗家の思うようにはならぬ方だった。それに引き換え、同じ従兄弟でも古人大兄は入鹿の言いなりだ。古人が然るべき齢になれば、母のあと、次の大王となる。何とあからさまなことか」
「ほんに、口惜しいことですが、それで今宵の秘め事ですか」
遠智は冗談めかして言ったつもりだったが、「秘め事」という言葉に中大兄の口元が一瞬こわばった。遠智娘は女ながら政治の話に通じている。中大兄は迂闊なことを言ってこれ以上この話を掘り下げられたくなかった。