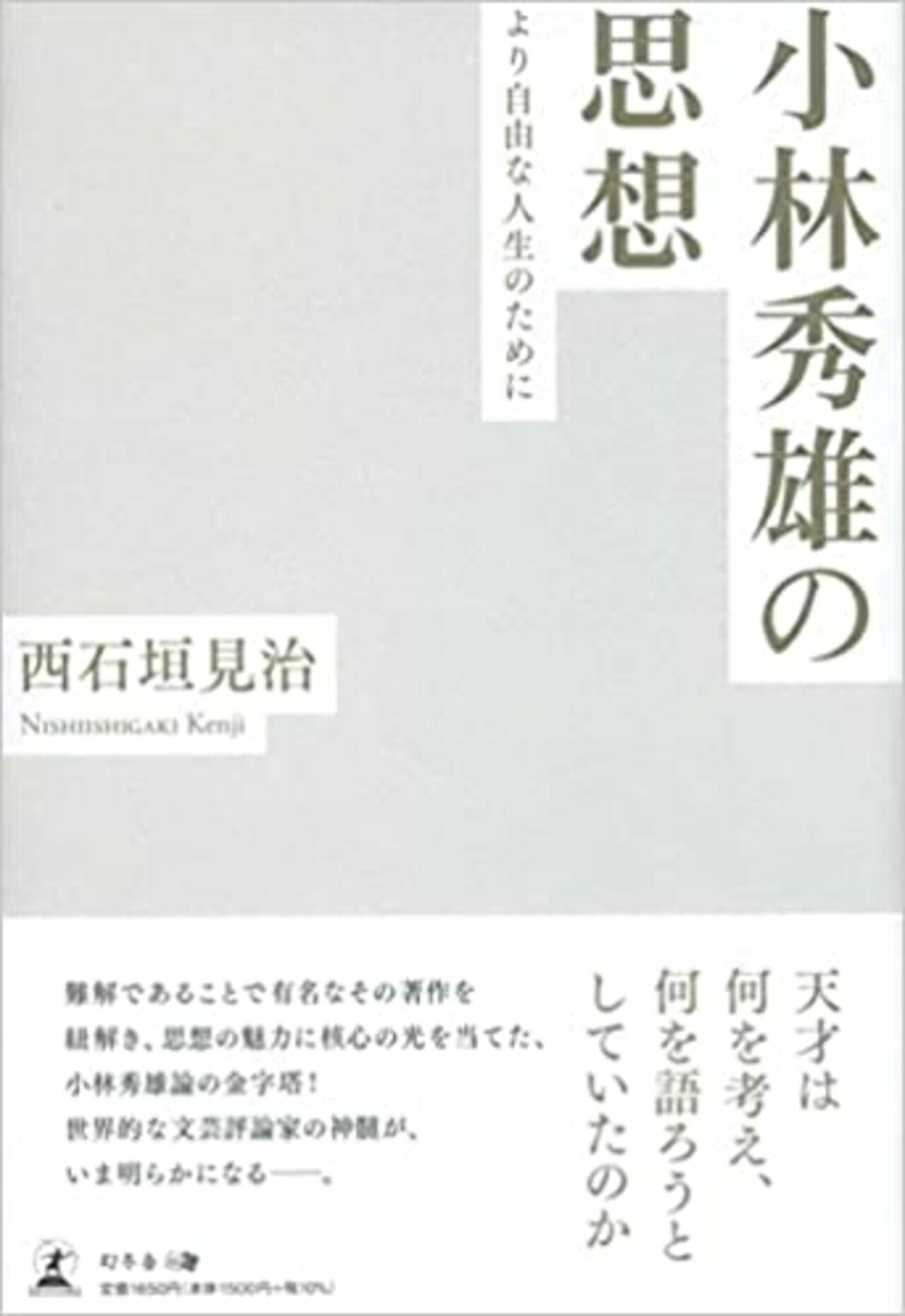【前回の記事を読む】「自明さとは、ほかならず、言葉の意味を鵜呑みにすること」
言葉と現実との同視は、実用的領域以外では成立しないこと
ちなみに、「明晰なる無知」との比較でいえば、先ほどの”花の美しさ”は、「混濁した無知」が、意識の反省の光がたまたま届いていない存在の一隅において、「花」という言葉ないし知識に寄生し、巣食っているのである。これは、我々の思考は、せいぜい自然や歴史、社会、あるいは精神世界といった、実在の無限の広袤のごくわずかな上っ面を、ともかくも意識の経験として擦過するにすぎないからである。
そのゆえに、その反省のもたらす認識作用は、十分に明晰であれば、本源的無知の自覚へと必然に向かうのである。そして、それが「明晰なる無知」と呼ばれるのは、分からないことも分からないなりに、徹底した知的探求のうちに自らを反省、自覚すれば、それ自体が認識的努力の極限の産物として、思考が置かれた意識の明晰な状態を物語るからである。
それはちょうど、測深鉛が深海の底に達したように、実在をめぐる日常的言語のもたらす認識の所与性を突破して、「説明できないもの」に衝突、停止した、その手応えの反省的直覚なのである。
それがまた、そのまま思考の日常的な知や論理、言語との関係の意識にはね返って、その自体的無知が、それらの関係を根底から照射する認識の底知れぬ深淵んとして、かえって、各々の本質的制約や限界、相対性を浮き彫りにするのである。
それは、認識上の紛れもない経験でありながら、日常的なあれこれの意味付けへと還元し得ないのである。そのため、実用的な概念的・言語的資源の豊富化に寄与するわけでもない。その意味で、その認識は、非実用的で、いわば余計者の認識なのである。
かくして、それは、己の認識を根底から動機づける”真知”への徹底した志向性や、それに相応する懐疑の精神のゆえに、かえって、ある種の謙虚さや自制を余儀なくされるのである。「明晰なる無知」は、世界における己の認識的位置を、「知」ではなく「無知」の側に分類するのである。
そしてそれは、「自覚された無知」として、ソクラテスのように、対世俗的なイロニーを背後に引き連れつつも、その行く手の自覚ないし憧憬の極点において、”真知”の導きの星をひそかに信仰していないわけではない……。