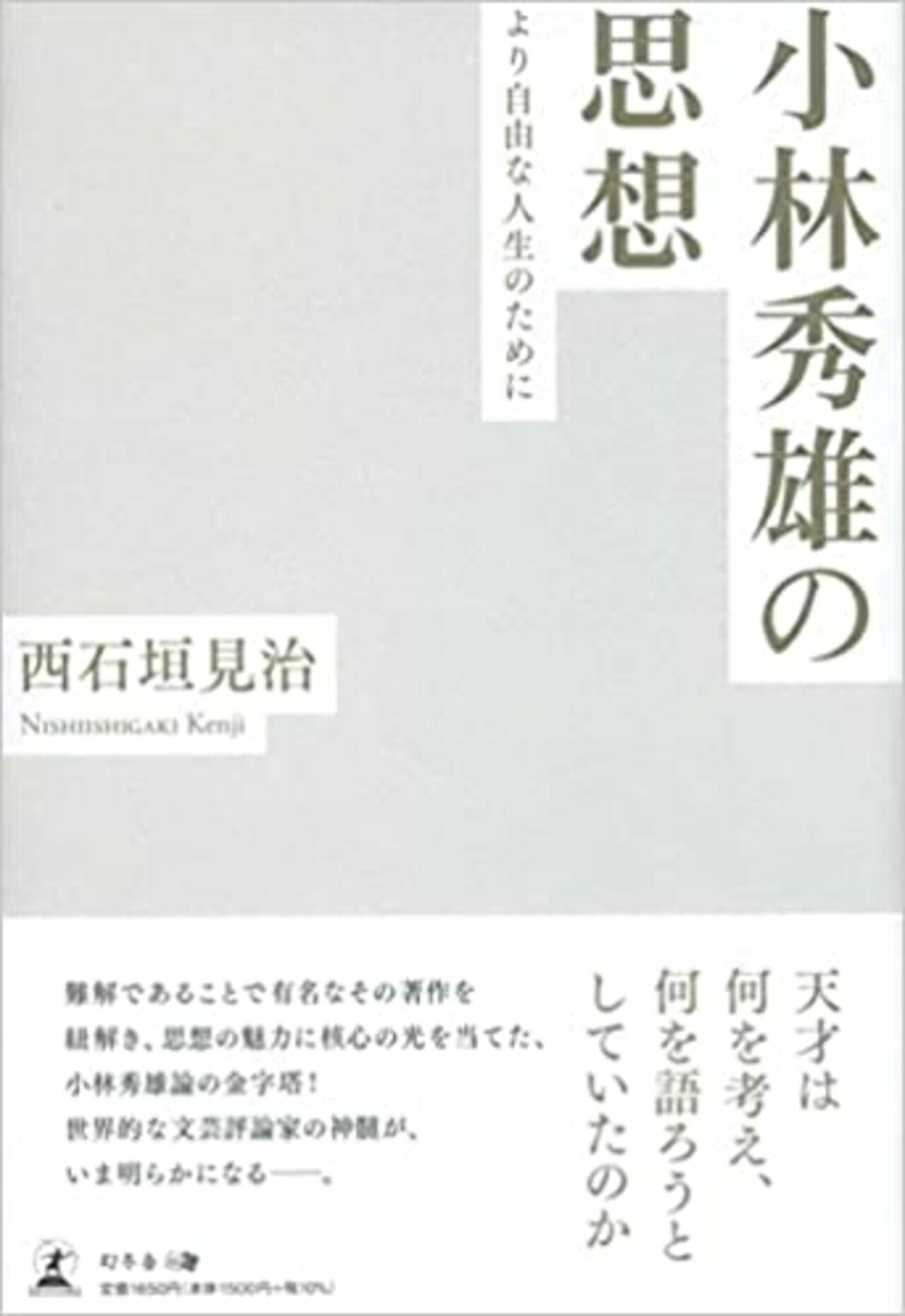小林作品の“難解さ”について
考えるという行為は、衣食住に加えて、人間存在の四大必要ないし条件を形成するのであろう。のみならず、それこそは又、人間を動物から唯一区別する、特徴的な営みでさえあるのだろう。
とはいっても、それは、衣食住とは異なって、その過不足が肉眼に見えたり、当事者に必ずしも自覚されるわけではない。又、その行為の場所についても、外部世界にとどまらず、内面世界の広がりにも及ぶのである。そのため、その充実や有無について、はっきりした物差しがあるとはいえず、その判定は決して容易とはいえないのである。
とはいえ、その行為は、社会に及ぼす影響力の大きさや、精神の自由ないし人間的自覚に関係することといい、その判定の必要性や要請には、不可避のものさえあるのである。それが、歴史社会の内面を突き上げる衝動となって、人類の精神思想史の原動力を形成してきたといっても過言ではない。
そして、その応答の形式が、例えば、ソクラテスや仏陀の例のように、哲学的問答体を取るにせよ、あるいは近代的批評の形式を取るにせよ、人類の歴史にその顕現を必然たらしめてきたのである。
ところで、それは、時代の所与としての「考える」という行為の一般性に対して、批判的な関係に立つもので、考えるという行為が反省的に徹底されたものなのである。反省の意識が、“考える”と言う行為の隅々に至るまでを貫き流れるなかで、いずれ方法の明確な意識へと高められ、洗練されて、その理想的な自覚のうちに、方法としての統一性や支配を自ずと実現しているのである。
その及ぼす効果は、日常的に見知っているはずの事物や世界を、反省の光の思いもよらぬ照明のうちに、いわば言語以前の裸の姿において浮き彫りにするのである。既知性という、自明性の無意識の殻に覆われた、言葉や事物、存在の日常的なアイデンティティが、破壊され、根こそぎにされるのである。
しかし、そのことは、そのような最上の精神的、思想的経験をめぐっては、その理解や解釈の行為自体が、自らの経験に躓いて、往々に面食らうことなのである。
例えば、ソクラテスは、同時代のギリシア人にとっては、その日常的な思考を根底から震撼させるために、「触れれば痺れる電気ウナギ」との評言を以もって迎えられたのである。