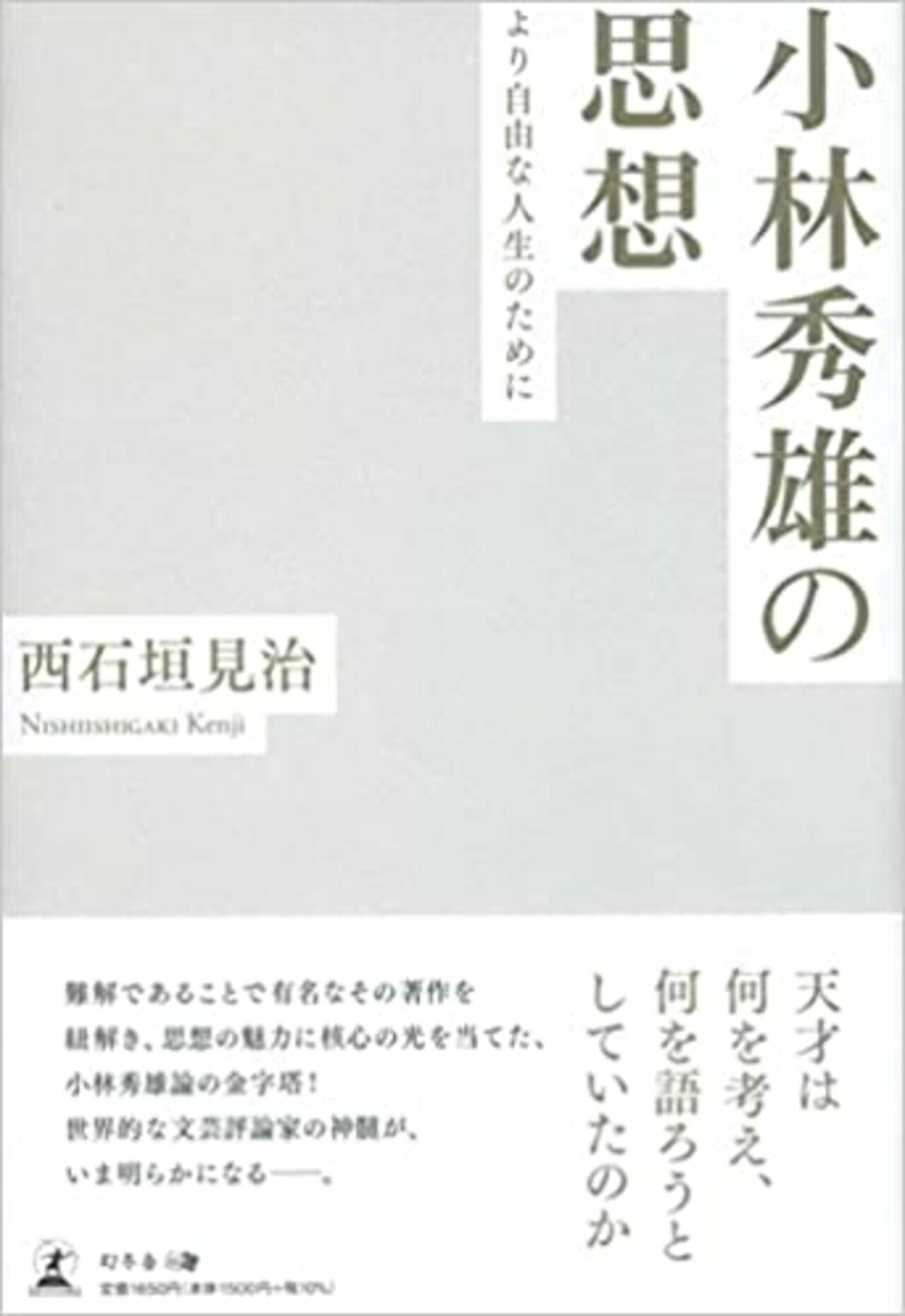小林の批評作品は今日、古典の殿堂入りして久しい。しかしながら、その作品には依然として“難解”の評が付きまとうのである。
しかし、文壇デビュー作「様々なる意匠」から始まって、晩年の大作「本居宣長」、そして絶筆「正宗白鳥」へと至る生涯の業績をざっと見渡すとき、むしろ次のことこそは明らかなのであろう。それは、初期作品のレトリック上の難解さはともかく、その高度の思想性や哲学、精神性に鑑みると、その生活者としての平明な言葉こそが際立っているのである。その難解さは、むしろ、難解なる平明さともいうべきなのである。本当の問題は、我々の思考習慣や日常的な知の在り方にこそあるのである。
実際、それは、その作品がもたらす言葉の経験が、我々の思考との間に惹き起こす、ある種の軋轢を思わせるのである。概念的な既成の意味経験に慣なれっこになった、我々の知が、いささか勝手の違う言葉との関係や意味経験の深みへと引きずり込まれることで、混乱し、面喰らっているのである。
「美しい花」と“花の美しさ”
例えば、小林に次の有名な言葉がある。
「美しい『花』がある。『花』の美しさといふ様なものはない。」(『當麻』小林秀雄全集第八巻「無常という事・モオツァルト」新潮社』)
「美しい花」とは、現前する経験そのものであり、その美的な経験やそれを形容する言葉は現実のもので、そこに嘘があるわけではない。それは、すでにそれ自体が個性化された、個別的、審美的な経験なのである。それゆえに、美しい花は、「ある」のである。
しかし他方、「花の美しさ」は、花弁やおしべのように、花に「属性として」付属しているわけではない。せいぜい、花に接して、それを美しいと感ずる人間経験があって初めて、その観念性が了解されるにすぎない。それは、習慣的な概念化作用が、言葉の上に作り出した幻影、錯覚なのである。かつて経験された「美しい花」の記憶から、「美しい」の形容詞が抽出されて、逆に、「花」の概念に投げ返されたのである。
そして、そのもたらす部分的な同一視がそのまま、凝固、属性化して、「花の美しさ」へと体言化したのである。そうであるがゆえに、それは、生きた経験の裏付けや実体から遊離した、言葉のバブルにすぎず、虚偽意識に照応するのである。─かくして「花の美しさ」は、現実には「ない」のである。