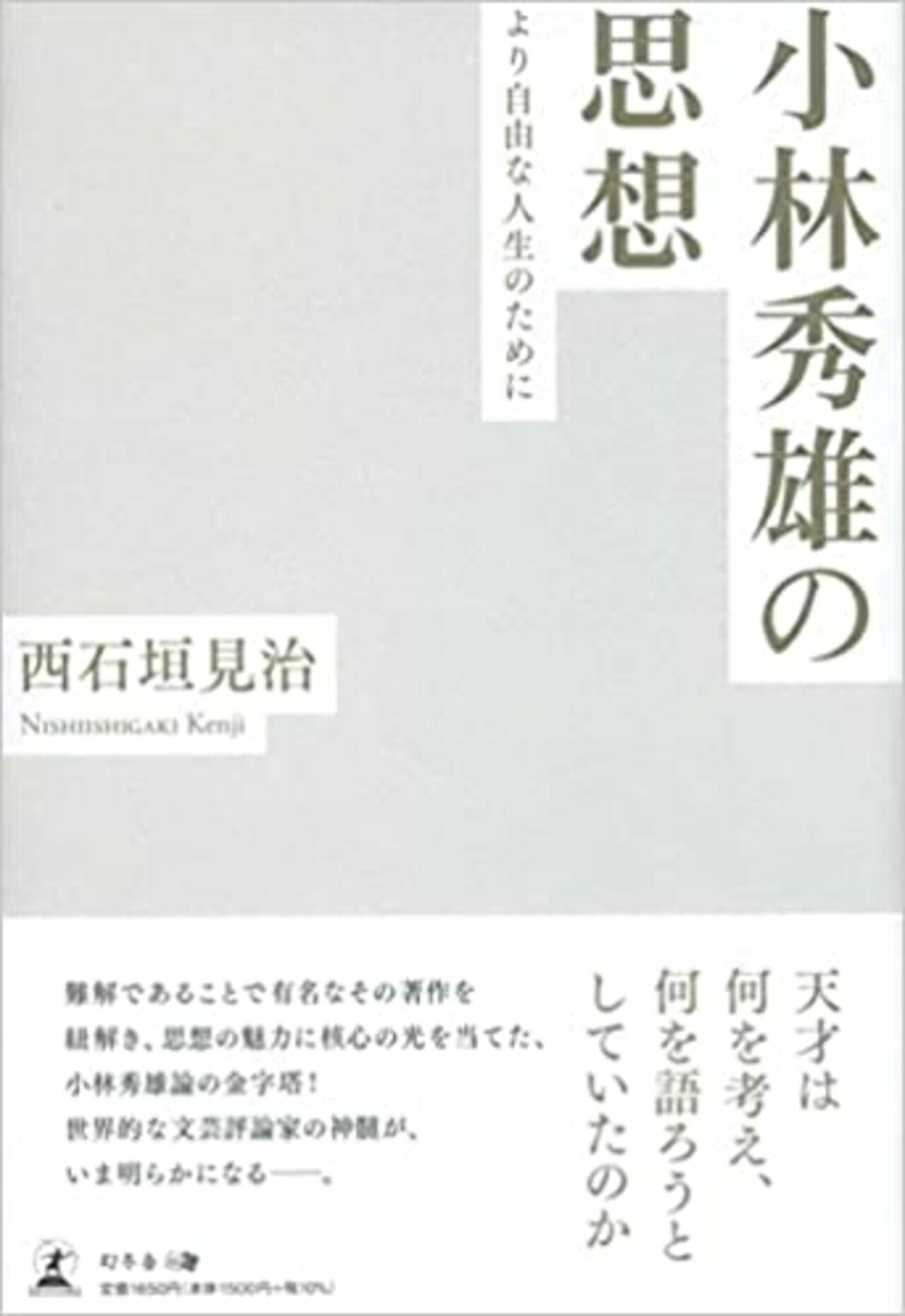【前回の記事を読む】古典の殿堂入りから久しい小林作品「難解さは、むしろ平明さ」
言葉の自動作用がもたらす、言葉と現実との同視
小林の難解さとは、自らの言語経験に対して批判的な距離を取ることの難しさなのである。言葉の本能的機制が、自らの自動作用のうちに形成、沈殿させた、言語意識の習慣的軌道から、思考が抜け出すことの難しさなのである。あげく、単なる言葉の上だけの存在や事物が、往々に現実と混同、同一視されて、行為や判断の前提や手掛かりとされるのである。
しかし、「花の美しさ」のように、言葉は、その示唆する事物や存在を、現実に担保しているとは限らないのである。かえって、“知っているつもり”の言葉が、内実を欠いたり、似ても似つかぬものであることは、ごく普通にあるのである。
これは、言葉の現実の意味は本当は知らないにもかかわらず、あたかも知っているかのような錯覚に、思考が陥っていることなのである。それは、書籍やインターネットで調べれば片が付くような、単なる知識の問題ではない。逆に、知識に巣食った、哲学的無知の問題なのである。思考が、言葉の貧寒なパターン化した所与性のなかに、牢獄のように閉じ込められて、自己の可能性や自由から隔絶されているのである。これは、夢や妄想に陥って、現実から遊離しているのと似ていないわけではない。
このような無知は、文字言葉を宿主としているため、かえって知の装いを得て、社会的な流布のうちに、あたかもエアポケットさながらに、思考の日常的空間の至る所に潜伏しているのである。そのなかには、「花の美しさ」といった、さほど罪のない類いもあれば、政治的神話のバブル現象となって、社会をのみ込むまでの勢いを得て、深刻な社会的害悪を及ぼすものもあるのである。
その結果、悪貨は良貨を駆逐する譬えの通り、本物の経験や現実に担保された真実の言葉や思考を、日常知の空間から駆逐さえするのである。